『知っておこう“人事”~法律から実務まで~』
第5回目:異動・昇進とは?

みなさん、こんにちは。社労士ライターの安森です。
やすもり社会保険労務士事務所の代表として各種メディアで発信をおこなっています。
前回は“評価“の解説をしました。
第5回目 異動・昇進とは?
2022年頃から「配属ガチャ」という言葉がさまざまな場面で用いられるようになりました。
専門的には「企業と個人の間で情報の非対称性が生じている状態」と説明されます。
『まるで商品の中身を見ずにパッケージだけで購入をしなければならない状態』とも例えられますね。
これに対して、異動や昇進は少し位置付けが異なります。
『異動カチャ』(ハズレ)という事態もゼロではありませんが、
入社後の数年で、成果を出し、成長し、次の機会をつかむための土台ができているはずですし、会社の状況や組織も見えているでしょう。
異動や昇進の仕組みを確認すると、会社が従業員にどのように働いてもらいたいか、希望する業務に就くためにどのように行動すべきかが分かります。
1.「人事権」と「キャリア権」
会社が従業員に対して異動や昇進などを命じる権利が「人事権」です。
終身雇用のもとではこの人事権が非常に強かったのですが、近年は会社側の都合だけでなく、従業員それぞれの事情にも配慮しながら
異動や昇進などを決めていく傾向にあります。
さらに、この「人事権」に対して、「キャリア権」という概念も登場しました。
大企業でさえ終身雇用の維持が難しくなってきたこともあり、会社が人事権に基づいて決める異動や昇進を通じたキャリア形成ではなく、
従業員自らの考えに基づくキャリア形成が求められています。そのための権利として「キャリア権」が提唱されました。
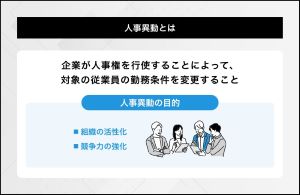
2.キャリア開発のための仕組み
キャリア権に基づき、従業員が自らキャリアを形成するために「キャリア開発」の仕組みを用意している企業が増えています。
キャリア開発は会社の支援のもと従業員がキャリアを築いていく仕組みで、上司やキャリアコンサルタントとのキャリア面談、
会社から提示されるキャリアパスに基づき、自らのキャリア形成の方針を考え、それを異動や昇進につなげることができます。
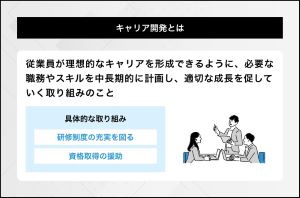
3.異動や昇進はどう決まる?
一般的には『需要と供給の関係』と説明されます。
異動: 「人材を求める部署の需要」 VS 「条件満たす人材」
昇進: 「ポストの数/性質上の需要」 VS 「条件を満たす人材」
会社としてもミスマッチのリスクは当然認識しているので、近年は特に若年層のマッチングには気を使っています。
他方、ローテーション的な人事として、性質の異なる業務への異動、生産拠点などへの異動は、実際にはあらゆる企業で起こります。
このため、基本的な制度と運用の実態の確認、またあなたがどう対処していくかなどについて想定をしておくことをお勧めします。
『異動の指示は絶対命令で質問も反論も許さない』という体質が残っている会社もあるかもしれませんが、
最近の動向としては、ここでひと手間かける(従業員との対話を行う)ことが一般化しつつあるので、
『期待されること』など、もし説明があるようであれば、しっかりと受け止める必要があります。

4.より良いキャリアを築くには
人事の目的は社内の人材を上手に活用して業績を高めることです。
先ほど述べた需要と供給の関係はもちろん、キャリア開発の仕組みがある会社では従業員のキャリア形成の考え方が異動を検討する際に考慮されます。
希望する仕事と、その仕事への適性をアピールすることで自律的にキャリアを築くことにつなげられるのです。
社内公募制度や社内FA制度を導入している企業もあるので、それを活用してみるのもよいでしょう。

まとめ
ありきたりなメッセージになってしまいますが、人事の専門家として言わせてください。
『ガチャに一喜一憂するのではなく、中長期のキャリアを見据えて主体的に行動していくこと』が大切です。
環境が変わっても転用できる市場価値を身に付けるというポジティブな姿勢が、あなたをプロとして自立させる一助となるはずです。