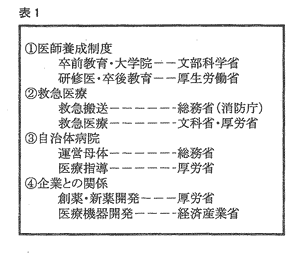学士会アーカイブス
これまでの医療・これからの医療 金澤 一郎 No.900(平成25年5月)
要 旨
これまでの匡療の成果~OECDの健康報告書から 三番目に、狭心症、冠動脈疾患などの虚血性心疾患による死亡率が男女とも世界一少なくなりました。 最後に、癌による死亡率が、世界最低ではありませんが、主要七ヶ国の中では最低になりました。
高い医療レベルは何が支えているのか? 次に、日本人の砂糖消費量が著しく少ないことや、BMI25を超える肥満人口率がわずか三.〇%で、世界一低いことも挙げられます。ちなみにアメリカは三二.二%で、世界一高い数値です。 三番目に、日本は急性期ベッド数が世界一多いことです。これは絶対数ではなく、人口千人当たりのベッド数で比較しています。一九九〇年の段階では圧倒的に一位でした。一五年後の二〇〇五年になると随分減りましたが、それでも世界一です。つまり、それだけよく診てもらえるということです。 四番目に、CTスキャナーやMRIなどの画像診断機器の数も圧倒的に世界一であることです。これも絶対数ではなく、一〇〇万人当たりの台数で比較しています。CTスキャナーは二位のオーストラリアの倍以上、MRIは二位のアメリカの一.五倍の台数を誇ります。今や街の開業医でさえ、CTスキャナーがないと不安に思うそうです。画像診断機器の保有台数は一九八〇年代に医療機関に導入され始めた当初から、常に日本がトップです。 最後に、日本は患者一人当たりの受診回数が世界一多い。どういう訳か、日本を筆頭に、チェコ、ハンガリー、韓国、スロバキアが非常に多い。医療費と関係があるのかもしれません。 以上をまとめると、我が国の医療の成果を支えているのは意外にも、①日本人の健全な生活習慣、②ベッド数と医療機器の豊富さ、③安い医療へのアクセスのよさ、そして②と③がもたらした、④勤務医と職員の過重労働、と言えるでしょう。 それでも患者も医者も現状に満足していない! 患者の立場からの不満は、まず「病院に行っても混んでいて、診てもらうまでに長時間待たされる」「夜間診療や休日診療を探すのは大変」ということが挙げられます。例えば休日に骨折をした時、大きな病院に電話をして診療をお願いしても、さんざん待たされた揚げ句、「今日は整形外科の当直がおりません」と断られる現実があります。次に、「診てもらえても、病名や薬の名前を教えてもらえない」「教えてもらえても、難しくてよく分からないし、調べるのも面倒」ということもあります。一番困るのは、「手術と言われたので驚いてセカンド・オピニオンを求めようとしたら、医師の機嫌が悪くなった」ということでしょう。 済生会栗橋病院副院長の本田宏氏によれば、患者が求める医師の姿とは、医学知識は完璧、技術はブラックジャック、心は赤ひげ、説明はプロのアナウンサー並み(ユーモア付)、チーム医療の中心としてリーダーシップを発揮し、気力・体力は二四時間対応可能、しかもお金は取らないというものです。これほど完璧な医者でも、何か起こると、「訴えてやる!」と言われてしまうのが現状です。 一方、現場の医師の立場からの不満をまとめると、勤務医と開業医で随分違います。勤務医、特に若い勤務医の不満は、「医者がやらなくてもいい雑用が多い」「大病院に直接来なくてもいい患者を含めて、患者が多くて忙しすぎる」「患者や家族への説明に時間がかかる」「当直の翌日も勤務がある」「一所懸命診療しても、結果がよくないと訴えられる」というものです。 開業医の不満は、「患者をたくさん診ないと収入が上がらない」「患者が多いために、休みがなかなか取れない」「研修のための時間を十分に取れない」「大病院への紹介は敷居が高い」「診療点数の計算などが複雑である」というものです。 これまでの医療の問題点が次第に明らかになった (1)医療界固有の問題 一九六一年に国民皆保険が導入されると、国民の医療需要に応えるために医師不足解消が目標となりました。しかし、医療費高騰が社会問題になると、政府は方針を転換させました。八二年、「医師の過剰を招かないように配慮する」という閣議決定があり、以後三〇年近くにわたって医師数を抑制する策が続きました。翌八三年、厚生省保健局長の吉村仁氏が「医療費増大は国を滅ぼす」と発言して危機感を表したように、医療費を抑制する政策も長期にわたって続くことになりました。小泉政権時代の二〇〇一年には医療の一部に市場原理主義が導入され、医療費削減策に拍車がかかりました。 二〇〇四年、国立病院と国立療養所が独立行政法人化されました。この時、卒後初期研修が必修化されました。どういうことかと申しますと、一九六〇年末までは、大学卒業後に一年間の臨床研修をしないと、医師国家試験の受験資格が与えられない制度でした(インターン制度)。しかし臨床研修期間中は学生でも医師でもなく身分保障がない上に、給与保障もほとんどなかったため、東大で東大紛争のきっかけとなったように、各地で激しいインターン闘争が起きました。その結果、六八年に同制度は廃止され、大学卒業後すぐに医師国家試験を受けられるようになりました。医師免許を取得した新米医師は、必修ではなく努力規定として、二年以上の臨床研修をすればよいことになりました。 二〇〇四年、この卒後初期研修が(努力規定ではなく)必修化されたのです。この際、研修医が研修先を自由に選べるようになったので、希望が都市部に集中するようになりました。その結果、「大学医局支配」と言われていた状況が一変しました。それまでは、「大学病院の医局から地方の関連病院に研修医も含めた医師が派遣され、一~二年ごとに配置換えされる」というシステムが機能していましたが、それが壊れ、地方の医師不足、ひいては地方医療の崩壊を招きました。二〇〇六年、長年の医師数抑制策が見直され、医学部定員増が一部容認されました。 以上のように、医療費抑制、医師不足に加え、初期研修必修化が今日の一医療崩壊の下地になったと考えられるので、それぞれ掘り下げてみましょう。
<医療費の問題> 「OECD諸国における医療費の対GDP比率」で見ても、アメリカが圧倒的な一位であるのに対し、日本はOECD諸国三四ヶ国中、下から数えて三分の一あたりに位置しています1)。注目すべきなのは、日本は医療費の中の患者負担の割合が二〇%以下であり、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、イギリスなどの社会保障先進国とほぼ同程度に低いことです。 次に「主要国における医療費と高齢化率の変遷」を見てみますと、アメリカは高齢化率が大して高くないのに、医療費は傑出して高額です。それに対して日本は高齢化率は深刻ですが、医療費は低く抑えられています。 では、実際の医療費総額の変遷を見てみましょう。この一〇年間で医療費総額は七.四兆円2)増えましたが、この増加分の七一%が七〇歳以上の高齢者医療費です。また、現在の医療費総額は三七.八兆円ですが、その四五%が高齢者医療費です。日本の超高齢社会に対応するには、既に限界に近付いているのではないかと思います。 さらに深刻な問題は、日本の医療費、特に患者負担分に関する意識の差です。「これらが高いと思うか」という問いに対し、医師で「高い」と感じる人は半数以下であるのに対し、一般人ではなんと約九〇%近くが「高い」と感じていました。このギャップは深刻です3)。
<医師数の問題> 次に、病院勤務医の不足状況を地域別に予測してみましょう。二〇一〇年と二〇三〇年で比較したところ、西日本では兵庫県を除き医師数がほぼ充足されていくと予想されるのに対し、東日本では医師不足解消が遅れ、特に北海道、(群馬県と栃木県を除く)関東地方、静岡県、愛知県では深刻な医師不足が残ると予測されています4)。 一方、病院勤務医の不足状況を(地域別でなく)全国レベルで予測してみると、徐々に不足は解消されていくとはいえ、二〇三五年まで一貫して医師不足は続くと推定されています5)。 以上より医師数の問題には、医師不足と医師偏在という二つの問題があることが分かりましたが、それぞれ異なります。
<医師不足の原因> 医師の実働時間が減少すると、医療現場に残る勤務医は彼・彼女達の分まで働かなければならないので、負担が増加します。こうなると過重労働を理由に病院を辞める勤務医が出てきます。「立ち去り」と言われています。勤務医と開業医には給与格差が大きいので、それによる立ち去りもあります。
<医師偏在(診療科と勤務地)の原因> 次に、大学医局の医師派遣機能の低下が挙げられます。どの科を選ぶか、どこで働くかの選択は今や完全に医師個人に任されているので、医師は大都市に集中し、地方で不足しがちです。医科大学や医学部が人口に対して少ない上に、大都市に集中していることも理由に挙げられます。 最後に、若手医師の価値観や生活様式の変化が挙げられます。「赤ひげって何ですか」と尋ねられてがっかりしたことがありますが、「自分の時間が大事」「自由な時間が欲しい」という考え方がかなり浸透し、勤務が楽な診療科に集中しがちです。 (2)医療界と社会との軋轢の問題
<脳死移植と医療倫理> 医療倫理に関するものとしては、九九年、患者から採決したDNAのゲノムを本人の了解なしに解析した事件があります。この事件の二年後、ヒトゲノム・遺伝子解析の倫理指針ができました。
<医療事故> 同年、都立広尾病院で誤って消毒液を点滴して患者が亡くなる事件が起こりました。点滴ミスをした看護師は業務上過失致死罪、主治医と病院長は「異状死は二四時間以内に警察に届けなければならない」とする医師法第二一条違反で有罪判決を受け、〇四年、最高裁6)で刑が確定しました。厚生労働省も二〇〇〇年、「異状死の疑いのある場合は必ず警察に届けるべし」という通達を出しました。 この通達は医師業界に大きな波紋を広げました。「異状死を届けると、警察はあたかも犯罪の自白であるかのように捉え、乱暴に捜査のメスを入れてくる」「医師に過失がなかったとしても、警察からもメディアからも犯罪者扱いされ、社会的制裁を受ける」「異状死のうち、明白な過失と予見不可能な合併症をどう判断するのか」「医師側の弁明のためにも医療事故調査委員会の設立を」など、医師達は大きな脅威と不安に晒されるようになりました。 その延長上に、〇六年、福島県立大野病院医師逮捕事件が起こりました。帝王切開の手術中に産婦が出血多量で死亡した件で、精一杯力を尽くしたはずの担当産婦人科医が業務上過失致死と医師法第一二条違反容疑で逮捕されたのです。 医療上の過失か、予見できない合併症か、福島地裁で争われました。治療内容と医師の判断にまで捜査当局が踏み込んだ裁判として大きな注目を集めましたが、無罪判決となりました。マスコミや医療界や一般世論においても、「事実上の冤罪事件」「カルテ改竄や明白な過失ではないのに、医師を逮捕するのは行き過ぎ」「事件の背景には産婦人科医不足という問題があり、医師個人の責任を追及するのはそぐわない」「昼夜を問わず地域医療に貢献してきた医師を萎縮させる」「地域の産科医療を崩壊させる」など、医師を擁護する意見が相次ぎました。 この事件で少し冷静さを取り戻したのか、医療界を揺るがす医療事故は起きていません。しかしこれらが医療崩壊を具体化させたのは間違いありません。 これからの医療の望ましいあり方
(1)国や地方行政のこれからのあり方 二番目に、行政は「必要医師数」という考え方ではなく、「医師免許保有者の総数」という考え方をして欲しいと思います。医師免許保有者の活動領域には、基礎医学、社会医学、臨床医学の三つがありますが、通常、「必要医師数」というと、臨床医学に属する開業医や勤務医しか数えません。しかし、基礎医学での教育、保健所関連の業務、薬の開発研究、医療関係の出版、医療事故への対応の専門家、医療関係の団体の活動の担い手など、医師免許保有者の活動の場は他にもたくさんあります。にもかかわらず、これらの場で活躍する医師免許保有者は極めて少数です。医師の絶対数が足りないからで、大変残念なことです。 三番目に、一部の地域や診療科に医師が偏在するという問題については、医師不足とは異なる理由があるので、別に対策を講じるべきと思います。 四番目に、日本では国民皆保険制度と専門医へのフリーアクセスが保障されていますが、「総合診療医」を明確に認知して機能させる必要があると思います。日本人は専門医志向が強く、「基本的な医療が一通りできる医師」よりも「専門性を持った医師」の方を信頼しがちです。医学部教育においても専門医を目指すことが推奨されてきたので、日本では「総合診療医」が十分に育ちません。 現在、厚生労働省で「専門医の在り方に関する検討会」が開催されていますが、そこでも「総合診療医を日本に定着させよう」と議論されています。現在、若い人の中には総合診療医を目指す人が出てきていますが、彼らが総合診療医となって日本に根付くかどうかは、国民の皆さんの理解と支持にかかっています。若い人達が総合診療医を続けていくインセンティブを作るべきと思います。 五番目に、行政は日本の医療費などについて、未来像も含めたグランド・デザインを国民に提示し、国民の合意を得る必要があると思います。例えば医療費については、抑制すべきとされてきましたが、総医療費は高齢者医療を中心に増え続けています。国は総医療費の増加をどこまでなら許すでしょうか。 先進医療についてはどうでしょうか。例えば、「iPS細胞治療が予防的な意味も含めて非常に効果がある」と分かった場合、健康保険で賄うような制度設計はできるでしょうか。他にも、高額医療費補助の在り方、障害者医療の在り方、難治性疾患治療事業(難病対策)の在り方、医療と福祉の一体的政策の今後などについても、国民が了解できるグランド・デザインを提示して欲しいと思います。 最後に、医療行政は厚生労働省一省で完結する問題ではないので、「医療庁」のような各省横断的な機能を持つ行政組織が必要であると思います。表1をご覧項ければ分かるように、現在、医療行政には多くの省が絡んでいてあまりに非効率です。これを「医療庁」に一元化するべきと思います7)。
(2)医師のこれからのあり方 以下私案ですが、日本医師連合(仮)が結成されるならば、持つべき機能と持たざるべき機能があります。持つべき機能は、①医師の懲戒処分機能です。現在、厚生労働省の医道分科会が医師の行政処分を行っています。私は座長を務めていますが、本来は、弁護士や公認会計士の懲戒処分が日弁連や日本公認会計士協会で行われているように、医師の懲戒処分も医師の職能団体で行われるべきです。その他、②医師の質保証機能、③医師の管理機能、④医療への提言機能、を持つべきだと考えています。 一方、持つべきではない機能は、①労働組合的機能、②保険点数算定機能、③政治団体的機能、です。この日本医師連合(仮)は、あくまで臨床医師が強制的に全員加盟する職能集団ですので、基礎医学者など臨床医ではない医師には関係ありません。医師免許保有者全員が任意で加盟する「日本医師会」とは趣旨も機能も違います。ですから、日本医師連合(仮)は、日本医師会の存在を否定するものではありません。
<誠意をもって公開する> 最後に、医師は医療事故やそれに類似した事態が起こった際には、責任ある立場の人間がその時点で明らかなことを丁寧に説明し、結果について謝罪することが必要であると思います。隠したり嘘をついたりしてはいけません。これまでの医療訴訟のほとんどの事例は、家族に不信感を抱かれてこじれてしまったことに基づいています。民事の医療訴訟になるのはある程度やむを得ず、補償はきちんとすべきです。しかし、故意や重大な過失でない限り、刑事事例にすべきではありません。再発防止のために、第三者の調査と被害者救済のための過失補償制度が望まれるところです。
(3)国民・患者のこれからのあり方 私は「かかりつけ医」の定義をこう考えています。①自宅近くの小規模な医療機関の医師であること、②自分を長く診ているので、自分の身体の癖を知っていること、③幅広い医療とアドバイスができ、健康相談にも乗れること、④いざという時、適切な医療機関に紹介してくれることです。 ある調査で、日本、台湾、オーストラリア、韓国の開業医各八〇名弱に、「過去二年間に高脂血症の患者を専門医に紹介したことがあるか」と尋ねたところ、「ある」という回答が日本と台湾では非常に少なく、オーストラリアと韓国では多いという結果が得られました。国民性の差かもしれませんし、他の病気ならここまで差が出ないかもしれませんが、④は大事です。
<医療に参加し、納得する>
<医療事故の可能性を理解する>
<終末期医療について考える> これまでの医療、これからの医療を考える時に、行政、医師、患者という三者の共同作業は非常に大事です。共通するキーワードは「相互信頼」であると最後に申し上げて、私の話を終わります。 (注) 2)国民医療費は、二〇〇一年度は三〇・四兆円、二〇一一年は三七・八兆円である。 3)二〇〇七年四月六日~八日、大阪で岸本忠三氏を会頭として第二七回日本医学総会が開催された。その準備段階の五ヶ月間に、岸本会頭がインターネットや病院を通じてアンケート調査を行った。医師五五三四人、一般市民一九〇八三人から回答を得た。 4)国際医療福祉大学大学院教授・池田俊也氏の論文(二〇一二)より。女医の割合や高齢者医療の必要性などは現状のままと仮定し、病院勤務医の現在の週当たり労働時間(六一~六六時間)を、労働基準法に定められた週四〇時間にするために、必要となる医師数を算定した。過剰算定を避けるため、現状の週六一時間を用いた。 5)国際医療福祉大学大学院教授・池田俊也氏の論文(二〇一二)より。なお、データはあくまでも病院勤務医の需給についてであって、需要の中に、開業医、特に高齢者の増加に対応できる在宅医、基礎医学者、社会医学者、会社所属の産業医、行政にいる医師、製薬産業に所属する医師、メディアなどで活躍する医師などが今後必要となることは考慮されていない。 6)病院長は、医師法第二一条は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」とする憲法第三八条違反ではないかと訴えて、最高裁まで争った。 7)参考書籍『医療立国論Ⅱ 厚生労働省解体―医療庁を設置せよ!』(大村昭人著、日刊工業新聞社二〇〇八)。 8)日本医師会の羽生田俊副会長も、二〇一三年一月一四日付読売新聞に掲載された同会の広告において、「日本では患者さんがどの医療機関を受診してもよい「フリーアクセス」が確保されていますが、いきなり病院を確保するのではなく、まず、「かかりつけ医」に相談していただきたいと思います」と述べている。 9)二〇一三年二月四日、厚生労働省研究班報告書より。 (国際医療福祉大学大学院長・前宮内庁皇室医務主管・東京大学名誉教授・
東大・医博・医・昭42) (本稿は平成25年2月8日夕食会における講演の要旨であります)
|
||||