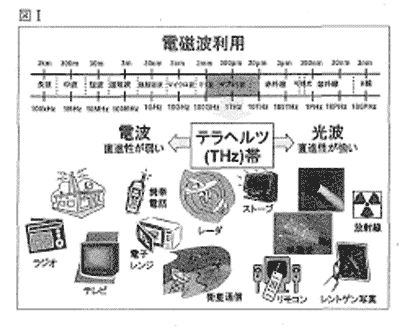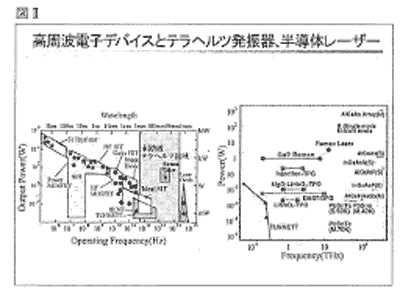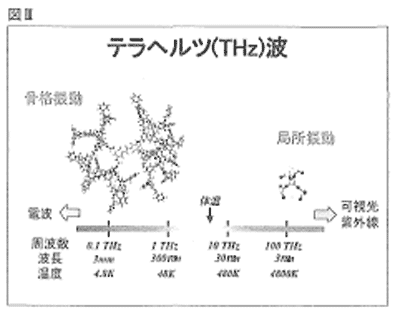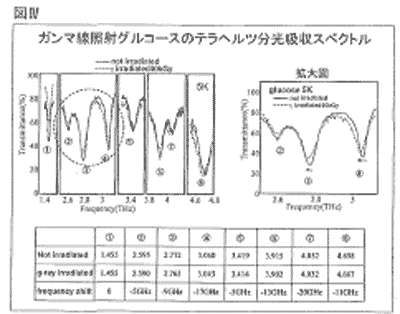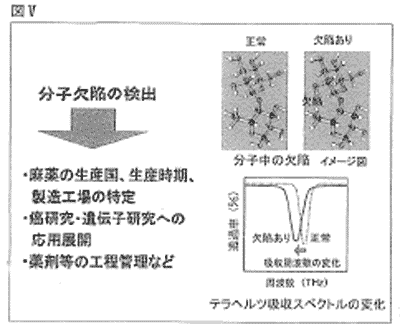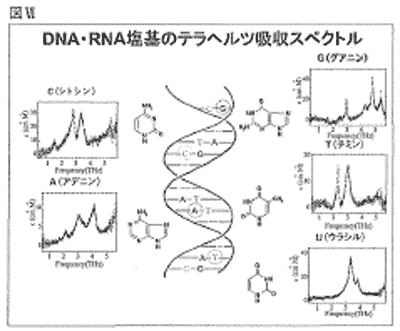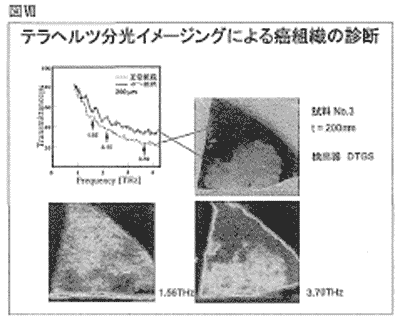学士会アーカイブス
光通信五十周年 西澤 潤一 No.883(平成22年7月)
要 約
アジアで始まった光通信 インディアンもまた、アジア系と言われていますが、焚き火を動物の皮などで覆って煙が出るのを止め、開閉によって煙を断続させ、モールス信号のように合図を送ったといいます。 ヨーロッパでは、フランス革命の頃、フランス人が、「腕木を適当に上下させ、それを見た人がまた同じことをする」という、いわば手旗信号の機械版のようなことを行いました。 無線通信の始まり まず、スコットランドの学者マックスウェルがファラデーなどの実験結果をもとに、「光とは電気の波であり、磁気の波である。そして空気中を伝わっていく」ことを方程式で理論的に表しました(一八六四年)。これを実験で証明したのは、ドイツのハインリッヒ・ヘルツです(一八八八年)。電波なるものが存在することが確認されたのです。 一八九五年、ヘルツの実験結果を受け、最初に無線通信して見せたのがイタリアの金持ちの息子のマルコーニでした。彼は部屋の端から電波を送り、途中を遮蔽しても、反対側にいる人に伝えたい事項が正確に伝わることを見つけ、世の中の人を大変驚かせました。これが実際に電波で通信を行った最初の例です。マルコーニはこれでノーベル賞をもらいましたが、基本的にはハインリッヒ・ヘルツの行った仕事が、マルコーニの基礎固めになっています。殆んど同じ頃、サンクト・ペテルブルグでポポフ教授も公開実験を行っており、どちらが早かったかいつも論戦が行われています。 マルコーニは、イタリア人の反応が冷たい為に、イギリスに渡りました。ロンドンでも税関に理解されず、持参した無線通信機を壊される苦難もありました。しかし、当時のイギリスでは、貴族階級が新技術実用化を非常に奨励していました。彼らの援助を受け、一八九七年、マルコーニ無線株式会社を設立、通信技術として一気に進歩の道を辿ることになりました。
日本でも無線通信の実験が始まる 所長から研究を命じられたのが、電気試験所技官の松代松之助でした。勿論、ヘルツが出した論文などは調べていたようですが、材料はどうしたとか、どういうことを実験したかという情報が全くないまま、一年間実験を繰り返し、ついに東京湾に浮かべた軍艦とお台場との間で無線通信を成功させました(一八九八年)。 松代松之助は、雑誌に出た数行の記事だけを頼りに、実験用器具を全て自作するなど幾多の困難を乗り越えながら成功させた訳で、相当実力がある人です。これが、日本における電気通信技術の最初です。
日本の無線通信の発展~日露戦争 帰国後、二高の物理の教官をしていましたが、松之助の実験成功の話を聞いて、ニ高で無線通信の実験を始めました。そのうち海軍が彼に着目し、「海軍教授」として招きました。木村は、三六式無線電信機の開発に成功し、日露戦争の前年の一九〇三年、全艦艇に装備されました。 世界で最初に戦争で無線通信を利用したのは日本でした。バルチック艦隊も、テレフンケン(シーメンスとAEGの合弁会社。一九〇三年設立)の無線機を装備し、技術者まで同行させたと言いますが、故障の連続だったようです。 日本海海戦では、まさに無線通信が重要な役割を果たしました。戦いの行方は、バルチック艦隊が対馬海峡・津軽海峡・宗谷海峡のいずれを経由してやってくるか、正確な情報にかかっていました。そこに、海軍に徴用されて特設巡洋艦になっていた商船「信濃丸」が、五島列島でバルチック艦隊と接触し、連合艦隊に対し「敵艦見ゆ」と無線で連絡してきたのです。 実は、バルチック鑑隊を日本で最初に発見したのは、沖縄・粟国島の商人だったようです。彼らは警察にすぐに届けました。当時、鹿児島~沖縄本島~石垣島~台湾間に海底ケーブルが完成していたので、五人の漁師は一五時間かけて丸木舟をこいで石垣島まで行きました。そして、石垣島から出来たばかりの海底ケーブルを使って電信で連合艦隊に伝えたそうです。しかし「信濃丸」の打電より一時間遅かったそうです。 このように、日本の無線機の開発は、極めて効率よく行われましたし、また、これがあったが故に、その後の日本の歴史にプラスになりました。当時、貧しい国であったせいもありますが、国民が一致団結して日本が繁栄する方向に向かって集中していました。
日本人の発見 これは、周波数を二つに分けて、一つの周波数では送る方の話を送り、別の周波数では、聞く方の話を受けるようになっているのです。この同時送受話法は、一九一七年、日本人技術者(烏潟右一ほか)が開発したもので、世界的にも非常に評価されました。
周波数とは 電気についても同じものが描けます。二つの点に電圧をかけ、片方を急にプラスからマイナスに変え、反対側をマイナスからプラスに変えると、磁力線の場所は変わりませんが、向きが一変します。一秒間に何回向きを変えるかが、周波数に対応します。
高い周波数の開発 私が東北大学に入学した時、八木秀次先生は既に大阪大学理学部に移っておられ、直接講義を受けることはありませんでした。しかし、残った先生方が八木先生のお話をして下さり、それがその後の私の研究人生の道筋をつけてくれました。つまり、「いつでも、どこでも、誰とでも」という八木先生の言葉です。 この三つの要素が満足出来て、相手にきちんと通話路線が設定出来ることが、通信の重要な役割です。 そのやり方は、一人ひとりに周波数を与えることです。携帯電話に使っている周波数は、その人しか持っていない周波数です。「電話番号を与える」とは、「周波数を与える」ことなのです。 乱暴な言い方をすると、一人ずつに少しずつ切って与えるのですが、切る時の厚みは、普通、三kHz(三千Hz)はないと困るので、それが携帯に使われます。三千Hzないと、何を言っているかわかりませんし、他の人に話が漏れたり、いろいろな問題が起こります。 このように、電波を作って希望に応じて与えていくと、あっという間になくなってしまいます。慌てて研究室に帰ってまた作り始め、次が出来るとまた持っていき、分けてあげるとまたなくなる。そういうことを繰り返しているので、「通信屋は、自分が新しい周波数を作ることをいつも前提にして、仕事をしなければいけない」と学生の頃、よく言われました。そんなことが、とうとう一生、「雀百まで踊り忘れず」で、新しい周波数を作ることに狂奔することになりました。 更にこれについで、八木先生の間接の言葉として聞いたのは、「通信屋として、周波数をどんどん開拓していくと、最後は光になるよ。だから、おまえたち通信屋は、光のところまでちゃんと通話に使えるようにしていくことが重要だ」ということです。ですから、ずっと周波数を開拓していくことになりました。
図Ⅰは、波長の欄で左端から、「三km」、「三百m」、「三十m」、「三m」と、一つ一つのメモリのところが十分の一ずつになっています。これは、波長が短くなっていることを示しています。次から次へと短くなって、一番右端の「三nm(ナノメートル)」は、非常に短くなっています。 「nm」は、「十のマイナス九乗m」(十億分の一m)で、非常に波長の短い所です。もっと短い波長のところは放射線という高いエネルギーを持った範囲になり、人体に悪影響を与えることもあるので、通信には使わない方が良いということになります。 右から、「紫外線」、「可視光線」、「赤外線」と並びますが、斜線部分が「テラヘルツ波」になります。終戦時には、テラヘルツ帯から二目盛下の「極超短波」の辺りまでは、何とか使えるようになりました。
八木アンテナ 電気屋がよく行うように、西村さんは、早速、巻いたコイルを置くとどうなるか等、様々な関係性を調べ始めました。その彼がある日突然、「とんでもないことが起こった」と、教授室に飛び込んできました。 出した電波を受け取ると、受け取る側で少なくなるはずです。ところが、西村さんは、「途中で約千倍に増えることがある」と言いました。通常だと、どこからか新しい電波を出さないとそうなりません。西村さんが答えを得られないまま卒業すると、八木先生がこのテーマを引き取り、ご自身で研究を続けられました。が、なかなか埒が明きませんでした。 翌年の一九二六年、先生はついにアンテナの基本となる原理を発見し、「八木アンテナ」として特許出願しました。この時、「間に置いた金属棒の位置によって、電波の強さが急に約千倍に上がってしまうことがある」ということが初めて分ったのですが、この辺から、高い周波数の電波の性質が新しい技術的な内容を生むことになるということが見えてきました。これは、世界的なホットニュースになりました。
岡部マグネト口ン 学生が実験していると、カーブが少しおかしくなりました。「周波数を高くしていくと、一遍下がっていったものはそのまま下がっていく」と言われていたのに、また上がり始めるのです。ところが、学生達はそれをあまり気にせず、消しゴムで消して直している人もいました。 岡部先生は、はじめ間違っていると思われましたが、そうでないことが分ると、「そういうカーブが出ているのに問題にしないのは、全くけしからん」と思われました。そして、発振しているのではないかとご自分でいろいろと調べると、やはり発振現象が起きていることが分りました。こうして、未経験の高い周波の電磁波を発振させる「岡部マグネトロン」が完成し、「八木アンテナ」と並んで、レーダーの材料が揃ったのです。
レーダー開発まで、あと一歩だった これは下に向けて距離を測っていますが、横に向け、飛行機にぶつけて、跳ね返ってくるのを計測するとレーダーになります。 このように八木研究室では、レーダーを考えつく紙一重のところまで迫っていたのです。しかし日本の学界や軍部は、「敵前で電波を出すなど暗闇で提灯を灯して位置を知らせるも同然」と有用性を理解しませんでした。 戦争が始まると、欧米の学界や軍部はいち早く八木アンテナに着目し、レーダーを作り出しその性能を飛躍的に向上させました。マルコーニ通信会社の技師長は仙台までわざわざやってきて、「八木特許のイギリスにおける実施権を買って帰った」と言います。八木先生は受け取ったお金の一部を「子沢山だった宇田新太郎先生にあげた」そうです。 このように当時は、外国でも、日本人の創造性豊かないろいろな通信の発達に目が向けられていました。光通信の分野に限って言うと、アジアが独特な発達を遂げていましたが、電気通信に関しても、「アジアの技術展開は、世界的にもリードしていた」と言えるくらいに、ユニークな展開をしていました。 レーザーの特許を巡る争い この分野の先行研究では、アメリカの物理学者チャールズ・タウンズがノーベル物理学賞をもらっています。ところが、これに関連した特許について、当時隣室だった大学院生(ゴードン・)グールドが「アイデアを盗まれた」と訴えました。裁判の決着に五十年以上かかりましたが、ついに認められ、タウンズの特許は無効になりました。同時に、裁判所はグールドに対し、「その当時の自分の知識の証拠になるものを集めてきて、それをまとめて特許を申請し直せ」と命じました。特許の審査過程で、タウンズ側と非常に高度な論争がありましたが、数年前、グールドの特許が確定し、あの辺の周波数の出し方の特許の権利者が移りました。 特許を巡る争いは、電子計算機でもありました。これも、五、六年前にかなり難しい論争が裁判所でありました。最初の発明者と言われる(ジョン・)エッカートが、別の人の仕事を見て勝手に特許を出したということで、これが無効になりました。ブルガリアからの移民の(ジョン・ヴィンセント・)アタナソフが本当の発明者ということになり、電子計算機の発明者が移りました。 余談ですが、裁判所はタウンズを呼び出し、「弁理士に払った分だけは費用として認めるが、今まで受け取った特許料を全部出せ」と言いました。今は大変な年寄りですが、それがそっくりそのまま、グールドのポケットに移行しました。その金額はわかりませんが、私達のような口さがない連中は、「よく残してあったね。我々だったら、一遍で使って返すことが出来なかったのではなかろうか」と余計なことを口にしました。 長距離直流送電網の夢
図Ⅱの左図をご覧下さい。横軸が周波数です。右端は完全に光になってきます。長方形で表された部分がテラヘルツ帯です。その右の細長い三角形が、私が考案した半導体レーザーで発振可能となった周波数範囲です。 しかし、半導体レーザー開発前から「SIT(静電誘導型トランジスタ)」というトランジスタを開発し、随分沢山の周波数を発振することに成功してきました。 話は脱線しますが、この頃、私は、「PINダイオード」と「静電誘導サイリスタ」という半導体を開発していました。この二つを用いると、損失が殆どゼロで直流・交流の変換が可能となります。これが現在、環境の観点から思わぬ有用性が見いだされました。例えばヒマラヤで水力発電をし、それを東京まで送電するといったような長距離送電が可能となるのです。 エジソンがはじめて大電力を直流で、電線を通して運んできました。しかしその後、交流の方が良いということで、交流に切り替わりました。ところが最近になって、やはり直流の方が良いということになりました。今まで、交流五〇Hzで運ぶ場合、電線などを使うと約二百kmしか行きません。二百kmというと、少し小高い丘に登って遠くが見えるくらいの範囲です。それ以上先に電気を送ることは出来ませんでした。 ところが、今の送電線の基準でいっても、直流ならば大体一万km(北極から赤道まで)運べるのです。北極から南極まで表面に電線を張ったとすると二万kmです。二万km運べれば、よほど特殊なことがない限り、それ以上は必要ありません。届かない場合は後ろを向いて張れば良いのですから。 一方、今家庭で使われる電気機器は全部交流です。ですから、直流・交流の変換が非常に重要となりますが、「PINダイオード」と「静電誘導サイリスタ」を使えば、殆ど損失ゼロで可能となるのです。 水力は再生可能でクリーンなエネルギーでありながら、交流で遠くから運ぶとすると長距離送電の際、ロスが多いせいで今まで注目されず、近くに火力発電所や原子力発電所を造って使いました。しかし、水力発電だけで電力需要を賄うことが出来る量がありますから、これから水力発電所を造り足して使う日が来るかもしれません。地球規模で直流発電による電力ネットワークを造れば、世界のエネルギー問題も環境問題も好転するのでしょう。 今後、周波数の低いところで大電力を取り扱うことが、半導体に課せられた重要な任務となっていきます。現在、「静電誘導サイリスタ」は世界で最も良い変換器で、二〇kHzまでが高い効率で出せます。 半導体レーザー~特許取得と研究費不足 半導体の中身を変えたり、構造を変えたりすることで、波長約一mmのミリ波までは出すことに成功しました。しかし、それから上がなかなか出ません。これから上の電波は別の原理で出さなければいけないのではないかということになりました。 あれこれ考えているうち、ふと中学二年生の頃、物理の先生が授業中になさった雑談を思い出しました。 ドイツのレンズ工場の少年職工フラウンホーファーが趣味の天体観測に熱中していた時、「恒星が太陽コロナの向う側に行くと、強い光を放つことに気がついた」そうです。物理の先生は、「恒星の光が太陽コロナの中に入ってくると、いろいろなエネルギーを持った粒子と出会い、光が増倍される」と説明してくれました。 私は、これをヒントに一九五七年、半導体を使った光の発振源として「半導体レーザー」を考案し、特許を取得しました。その後、何とかこのアイデアを日本で開発したいと思いました。当時、電電公社(日本電信電話公社)が、通信事業を一手に収めて非常に大規模に事業展開をしていました。そこで、三鷹にあった日本電電公社電気通信研究所に出向き、「まもなく光通信時代がくる」と説き、「半導体レーザーを開発したい」とお願いしました。関心をもって聞いてくれる研究室長の方もいたのですが、結論は、「出来るか出来ないかわからないものに、金は出せない」というものでした。 帰ってから先輩に、「お前、本当に出来ると思っているのか」と尋ねられたので、「根拠は全くありませんが、何とかものになりそうに思っています」と答えたところ、「じゃ、もう一遍行こう」となりました。しかし、前と同じ結果でした。とうとうギブアップしました。世界最初の特許だけが残りました。
アメリカに抜かれる 別のアメリカ人の友人から、「お前が余計なことをしゃべったからだ」と忠告されました。自分のアイデアが日本より先にアメリカで開発されてしまう、とても残念な経験でした。しかし、特許はアメリカより早くとれましたし、私のアイデアが競争相手のアメリカによって実現されたのですから、誰も実現しなかったよりよいと考えてあきらめることとしました。
テラヘルツ波の発振成功 私は同じ原理でここも出来るはずだと思い、いろいろと調べたところ、インド人のラマンが見つけた「ラマン効果」に思い当たりました。「ラマン効果」とは、「物質に光を入射すると、散乱光の中に、入射光とは結晶格子の振動数だけ異なる波長の光が出る」現象です。これをヒントに、テラヘルツ波を出すことを目指して研究を続けました。 この研究はうまくいき、一九八〇年から一九八三年までにテラヘルツ波は、一一THzくらいの領域がいきなり出てきました。これが一つのマイルストーンになりました。その後、次から次へとテラヘルツ波の発振に成功しました。 図Ⅱ右図の点が打ってある部分は、実際に発振した部分です。棒でつないである部分は、例えば角度を変えたり、磁場の強さを変えたり、様々な工夫によって、どの周波数も発振出来た部分です。厳密に言うと、所々少し抜けているのですが、「やる気になって行ったら出るだろう」と大目に見てもらえるならば、「全テラヘルツ帯は、西澤研究室で発振に成功した」と言えます。
光通信へ大きな一歩 今、地球上に人類が六〇億人います。その六〇億人全てに、三kHzずつ与えなければいけません。今はまだ、「周波数は要らない」という人が大勢いますが、世の中が進歩してくると、皆、「携帯だけは持っていたい」となるものです。 櫻井よしこ先生に、「携帯なんて作るから、援助交際まで出てきたのよ」と叱られたことがありますが、それは別の問題として、これからは「持ちたい」という人全てに周波数を渡し、いろいろな連絡を可能にすることが必要になります。その時の為にまず、「どなたにも差し上げられます」という環境にしたいと思っています。 厳密に言えば、まだ余裕があって、一人に二チャンネル程度は割り振るだけの周波数はあります。しかし、公共用通信とかその他の通信が他にもいろいろあるので、一人二チャンネルないしは三チャンネルくらいの周波数を持っていないと、地球上の人類全てに通信の恩恵を十分味わってもらうことは出来ません。「ようやくその夢がかなった」と言っても良いと思います。 人類の通信分野の要望が、私達のささやかな科学技術の展開によって可能になりました。我々、技術者の仕事とは、人類が困窮することが発生した時、科学技術の力を使って解決することである、と思っています。 余談ですが、科学技術者の仕事は、もう一つあります。先端的な発明をどんどん行って、世界中に特許を出していくことです。特許を取得し日本の権利としてきちんと活用していかなければ、工業利益の大半が日本から流出してしまいます。このことを記憶しておいてもらえば幸いです。 光ファイバーの発明 光を大気空間に向かって出しても、殆どが大気中に吸収されてしまいます。光で通信したいなら、相当部分を導波管のようなものを通さなければなりません。 日本でも、電電公社にいた関(杜夫)さん達がその研究をなさり、東京・大阪間に石英の棒を置くことを考えていました。石英の棒だと、置くだけでも大変ですが、更に表面で反射して何割かは外に出てしまいます。二〇回も反射すれば、光は殆どなくなります。 私は、グラスファイバーを使うことを考えました。管の中心部の屈折率を最も高く、周辺にいく程低くなるよう工夫しました。中を伝わる光は、屈折率の大きい方に向かって曲がっていくために蛇行します。ガラスの線の中をぐにゃぐにゃ曲がりながら、表面に一遍もぶつからずに行けます。表面にぶつかれば光は逃げますが、表面にぶつからないので、そのまま逃げずに遠くまで電送されます。こうして私は、光の長距離伝送路=集束型光グラスファイバーを考案しました。 この論文を発表するために呼ばれてロンドンに行った時、STLという会社にいる友人のところに寄って挨拶をしました。その時、「最近、STLでも光ファイバーの実験を始めたんだ」と言われて紹介されたのが、カオさんでした。それから何十年と因縁が出来ることになります。 当時、カオさんは、ガラスの純度を上げれば遠くまで行くだろうと考えて研究していました。しかし、これでは表面で反射して逃げるので、いくら純度を上げても、途中でなくなる分を減らすことが出来ません。私がそのようにアドバイスすると、カオさんは研究方向を変えました。 その後のカオさんがやった光ファイバーの研究の功績でノーベル賞が授与(二〇〇九年)され、私がもらえなかったのは、甚だ悔しいものでした。
光通信五十年 私が半導体レーザーを考案した一九五七年が、光通信発祥の年となります。タウンズの一年前、グールドのと比較してさえ七カ月早い。ただし、依然として「西澤が行ったのではない」と言う人がいますから、その人達はいらないと思いますが少し遠慮をして、「近代化された光通信が始まって以来五十年」と言えるでしょう。「トランジスタは、発明されてから使われるまで非常に早かった」と言われますが、光通信はこれよりも早いのです。アイデアが出てから、近々五十年で、これだけの発展を遂げました。 日本では、光ファイバーケーブルの敷設は一九八〇年代に入ってから本格的に始まり、一九八五年には主要都市間の殆ど、地方都市間の八割近くで完成しました。国際光回線についても、一九九〇年代以降、光ファイバーによる海底ケーブル網が本格化していきました。 「俺は光通信なんて使っていない」という人がいるかも知れませんが、その人の声が電話で伝えられる際、一寸遠いところなら必ずどこかで使われているのです。使っている人が知らないだけなのです。 テラヘルツ波の利用、私の夢 次に、今日、通信以外の分野でのテラヘルツ波の利用をご紹介したいと思います。
①有機化合物の分析 この結合で二つの原子は強く引っ張り合いますが、あまり引っ張り合うと、ファンデルワールス力が働いて、今度は逆に離れようとします。ですから、ばねで二つの原子がつながっているような状態となります。 結合の仕方は原子の種類によって異なるのですが、有機分子にテラヘルツ波を当てると、結合の度合に応じて固有の振動を見せるので、その結合が水素と炭素の結合なのか、あるいはフッ素と酸素の結合なのかなどが分るのです。つまり、分析が出来るわけです。 また、わずかに欠けていたり、あるいは、例えば酸素が入るべきところにほかの原子が入っていたり、ところどころに変な原子が入っていたりすると、振動周波数が少しずれます。それを見ていると、何がいくつ入っているかということまで分ります。 あまり小さく描くと分らないので、右側の分子は拡大して描いているので寸法が少しずれていますが、小さな分子は右側の高い周波数で共振し、巨大分子は左端の低い周波数で共振します。ですから、これだけを見ても、大きい分子か小さい分子かが分りますから、分子を毀さないでどんな原子から出来ているか測ることが出来ます。こんな研究を始めたのは水島三一郎先生です。 電気測定は、毀さないで測れることが重要になります。ですから、テラヘルツ波による有機化合物同定は、今後、非常に大きな発展が期待されています。
②ウイルスや細菌の検出 本当はもっとダイレクトに測りたいと、夢物語を考えています。街角にテラヘルツ波発振装置を設置し、通る人全てにテラヘルツ波を照射します。すると、薄い着物は通してしまうので、一部は人体に吸収されますが、一部は跳ね返ってきます。この反射スペクトルを測定して、病気を早期発見するのです。
③新薬の開発
④分子欠陥の検出 薄い線で描いてあるのがガンマ線を当てた後で、当てる前が濃い線です。この実験によって、有機分子の分子欠陥がテラヘルツ吸収スペクトルの変化として観測されることが、世界で初めて示されました。 「何だ、これっぽっちか」と言った人がいますが、私たち科学をやっている人間は、その「これっぽっち」が対象です。堂々と大きくしようとは思っていますが、とりあえずは、ここにやっと一歩、測定方法として確立したのです。
図Vはその応用の一つです。左図は正常な分子、右図は欠陥のある構造です。これにテラヘルツ波を当てると、下のグラフのように新しい吸収特性を生むことになるので、吸収特性を測っていくと、分子欠陥の有無が分かるのです。これからの遺伝や様々な疾病の研究には、非常に重要な測定方法になると考えています。
⑤癌研究への応用の可能性
既にここにも出ていますが、「特に太くなってがちゃがちゃになっている所は一体何か」ということになりました。「少し乱れた構造のものが混在しているのではないか。もしそうだとすると、もう少し測定精度を上げれば、例えば、アデニンが毀れたものが入っているとか、チミンが毀れたものが入っているとか、このDNAの構成にはどこに欠陥が入っていると言うことが出来るのではないか」。これを何とかしてつかみ出してみようと考えました。 その後、癌研の所長さんの、ある講演を伺った時のことです。その先生は、「癌も、DNAに入った欠陥である。この欠陥をつかまえることが出来れば、癌研究は、非常に進歩する」とおっしゃいました。それを聞いて、「テラヘルツ波発振装置の精度を上げて、癌がDNAの欠陥によって出来ることを立証したい」「その欠陥はどんな時に出来るか。欠陥の発生を防げたら、癌自体も防げるのではないか」と、勝手に夢を見ています。これはそんな意味のデータです。 ⑥癌発見の簡略化
図Ⅶ・右上は癌に冒された器官です。下半分が癌化した部分で、上の黒っぽい部分は、まだ癌化していない部分です。ここに、一・五六THzを当てて測ったのが左下の絵ですが、これではあまり差が出てきません。 右側の絵は、三・七THzを当てたものです。癌化した部分が薄くなっていて、癌化していない部分は濃くなっています。これは、顕著に差を出すために色を付けていますが、極めて簡単に、患者に癌が発生しているか否かを区別することが出来ます。 現在、癌の疑いがある時、手術をする直前に傷口を開けて少しスライスを採り、顕微鏡で見るそうです。顕微鏡は表しか見えないので、医者が癌と確定診断する為には、腫瘍を裏から見たり、薄く割いてみたりと、いろいろと試さなければなりません。現在、癌診断確定まで四日かけて、ようやく本当の手術に入れるそうです。 しかしテラヘルツ波によって、この病理診断が、短時間で、患者の体を傷つけずに可能になるのではないか。そして、研究を更に深め、様々な癌の種別ごとに綿密なデータを揃えて、癌の早期発見と治療に役立てたく思います。
⑦薬剤の工程管理への利用 薬の錠剤を流しながら、そこにテラヘルツ波を照射すると、中に混じった光学異性体が識別されます。異常な薬が検出される度に取り除くことによって、医薬品の安全性を守ります。なるべく早くこの製品化が出来るように、これからも努力を続けていきたいと思っています。
まとめ 大変散漫な話となりましたが、以上で私の話を終わります。本日は概略ではありましたが、これからいろいろな分野でこの発見が活用されることが分って項けたと思います。 ご清聴、ありがとうございました。
(学校法人上智学院顧問・上智大学特任教授・首都大学東京名誉学長・
東北大・エ博・工・昭23) (本稿は平成22年2月22日午餐会における講演の要旨であります) |
||||