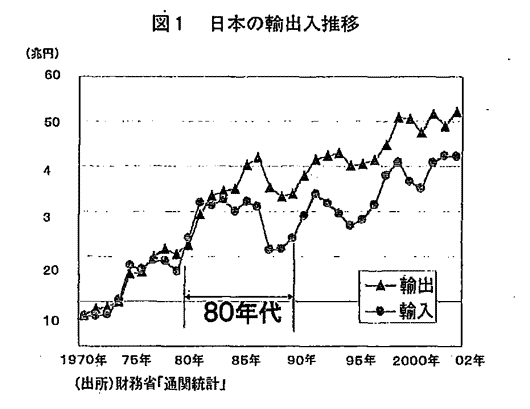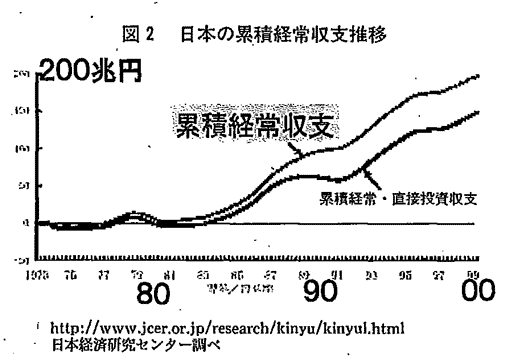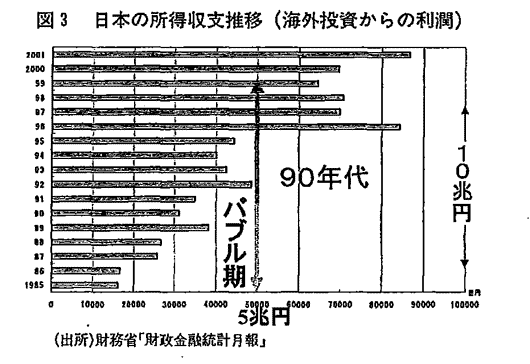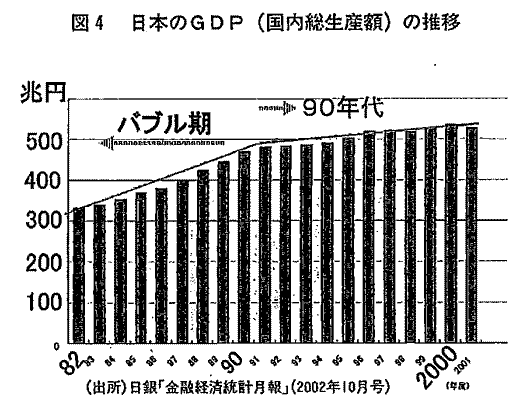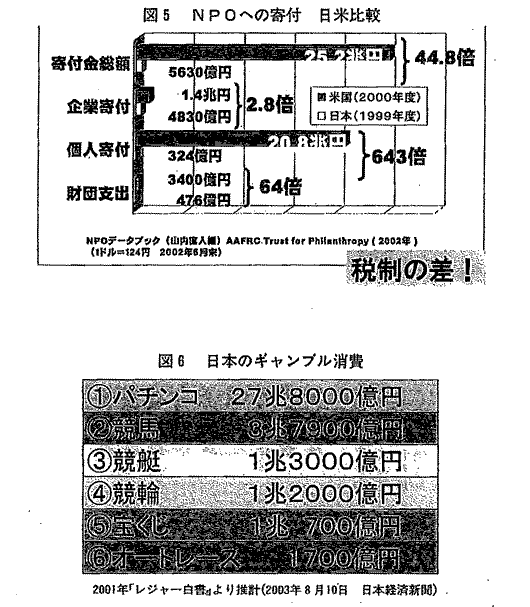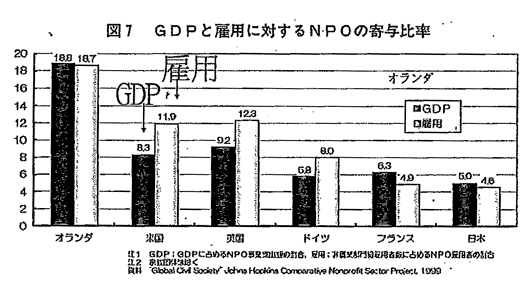学士会アーカイブス
科学技術の新しいマーケット―――仲間と地域の活性化――― 北澤 宏一 No.852(平成17年5月)
はじめに 私は、東京大学新領域創成科学研究科物質系専攻で超伝導の研究をしておりました。二年半前に辞職、現在の科学技術振興機構に移らせていただきました。私がなぜ移ることになったのかとよく尋ねられますが、科学技術振興機構を米国のNSFやNIHのようなFunding Agency として確立して欲しいというリクエストを受けたことは事実です。 さて、本日は「科学技術の新しいマーケット」という演題でお話をさせていただきます。科学技術振興機構に移って、「科学技術を振興することにどういう意味があるのか」を考えざるを得ない立場に置かれました。 産業革命以来、科学技術の発展によって生産性の向上と新製品開発とが繰り返し行われてきました。これにより私たちはより多くの価値を手に入れることができました。我々の生活は産業革命以来二桁以上豊かになったとされます。科学技術振興の目的のひとつは、さらに生産性の向上と新製品の開発を推進することであることはたしかですが、二十一世紀にはさらに新たな展開の方向を必要としていると考えます。 国際競争力失墜が日本の不況の原因? 経済大国日本を育ててきた世代の人たちは、この国際競争力失墜という言葉におびえています。自信を喪失して肩をすぼめ、萎縮しています。しかし、メディアが繰り返し流布している「国際競争力失墜」は事実でしょうか? 客観的に冷静に見てみましょう。 誰かが「だめだだめだ」というと日本人はすぐに「そうだ日本はだめだ」と同意します。皆で日本がいかに駄目かの大合唱が始まります。そして、皆が萎縮した十五年を過ごしてきました。私はこれを「一億総『だめだ』大合唱症候群」と呼びたいと思います。しかも、「だめだ」論には確たる根拠がありません。ムードに流されているのです。 最初に、国際競争力失墜の根拠とされる事実を見ていきましょう。ビデオ生産量の推移を見ますと、一九八〇年代には日本国内のビデオ生産(アナログ)は非常に好調でしたが、九〇年代になりますと国内生産は急速に減り、海外生産に移ってしまいました。ここ四十年半導体の世界市場は指数関数的に伸びてきました。日本のシェアは八九年には世界の五〇パーセントを越え、「半導体王国」といわれた時代となりましたが、九〇年代にはどんどんシェアが下がり、二〇パーセントほどになっております。日本の産業空洞化を示す典型データです。多くの製品について九〇年代に日本から海外に売ることができなくなったものはこのほかにもたくさんあります。 一方、日米の失業率の推移を比べてみましょう。日本の失業率は、ずっと二~三パーセントの間に入っていましたが、九〇年よりじりじりと増加、九九年には下がりつつあったアメリカの失業率と逆転、大騒ぎになりました。〇二年には再逆転していますが、雇用形態の差から日本の失業率は他国よりもずっと低く保たれてきただけにショックは大きなものがありました。 一方、日本法人の海外での雇用者数の推移を見ますと、九〇年に百五十万人であったものが、二〇〇〇年には三百四十五万人になりました。この数は国内の失業者数三百五十万人とぴったり一致していました。このためもあってか、日本法人が海外で人を雇うから、国内に失業者が出るという単純な説明が受け入れられたのではないかと思われます。ただし同じ時期、米国の海外への製造拠点移行はさらに進んだにもかかわらず、国内の失業率は下がっていったのですから海外雇用と国内失業率には直接の関係はありません。 しかし、本当に空洞化は起きているのでしょうか。もしもある製品が輸出できなくなっても、ほかの製品が出てきて、その輸出を代替していれば、それはむしろ「産業移行」と呼ぶべきです。ここ十年以上、ファックスや時計完成品、三五mmカメラも売れなくなり、日本から輸出できるものがなくなって行くのだと警告されていました。 七〇年以降の日本の輸出入の推移を図1に示します。凸凹はありますが、総じて言えば、日本の輸出入は七〇年代までは絶対額が小さく、貿易黒字がありませんでした。八〇年代になって、貿易黒字がほぼ十兆円出るようになりました。国民一人十万円ずつです。九〇年代の不景気の時代になっても、貿易黒字十兆円という傾向はオイルショックの年を例外としてずっと続いており、ごく最近の報道では、ここ二年は特に史上最高の黒字を更新しています。
単純に言えば、十兆円ずつの貿易黒字が二十年間続くと海外に二百兆円貯まることになります。より詳細に見ると、貿易黒字にサービス収支や所得収支、移転収支などを加えると、最終的な日本の財布が経常収支になりますので、それを見てみましょう。 図2に日本の累積経常収支黒字を示します。これが基本的には日本の海外純資産を形成するのですが、日本は九一年に英国を抜いて世界最大の海外純資産保有国となり、その後現在までさらに資産を倍増させてきたことが分ります。これが不景気といわれた九〇年以降もずっと続いていることは注目に値します。
日本のサービス収支の大半を決めるのは海外旅行です。バブル期に増大し、現在五兆円近くの赤字です。つまり、貿易で十兆円もうけて、その内半分近くを海外旅行で使う国ということです。移転収支も赤字ですが、これは日本がODA、あるいは湾岸戦争の協力金など、海外の支援に使うお金ですが、乱暴には平均一兆円弱、戦争があると臨時に増える支出です。 海外投資からの見返りは所得に計上されます。海外資産が八〇年以降増えてきたために、所得収支の黒字は図3に示すように急速に増大し、〇四年には九兆三千億円を超えました。つまり、貿易黒字に匹敵するようなお金を日本は海外からさらに付加的に受け取る国になったということになります。これが九〇年代の変化であることに注意せねばなりません。
労働コストの高い日本は「輸出するものがなくなる」とずっと言われ続けてきました。確かにカラーテレビ、電卓、ミシン、ワープロ、ピデオプレーヤー、腕時計完成品、カセットテープ、電子レンジといった製品は海外に売れなくなりました。むしろ、輸入国となりました。逆に、しかしながら九〇年代になってから輸出できるようになったものもあります。その例は、ポリプロピレン、複層自動車ガラス、リチウム電池、ICパッケージ、光ファイバ、液晶パネル、携帯電話、カーナビ、ディジカメなどたくさんあるのです。通常、空滑化が叫ばれるときにはこのような製品群はみていません。しかし、実際にはこのようなよく売れるようになった製品群があり、全体としては輸出額が増えてきたというのが実情です。 財務省の『貿易統計』の中の「各年の輸出好調品」リストを見ますと、輸出好調品は、毎年、次々と変わっていることが見て取れます。 日本からの輸出だけを野放図に増やすことはできません。輸出と輸入はバランスをとりながら、やっていかなければならないのです。 日本の輸出は現在、GDPの一割の五十兆円程度です。日本国内で競争力のある製品を順に並べた時に、自分の製品がベスト五十兆円の中に入っていれば輸出できるし、それより以下なら輪出できない。つまり、日本国内のほかの会社が自分のものよりもより競争力のある製品を作ってしまったら、自分の会社のものは売れなくなるということを意味します。つまり、国際競争力というものを海外に輸出できるのか、という観点から考えると、真のライバルは日本国内にある。ライバルは韓国や中国ではないと言わざるを得ません。中国や韓国を国際競争力のライバルと思っていると大変な過ちを犯してしまいます。しかも、輸出できる製品はめまぐるしく変化しているのです。 まとめますと、日本という国はこの二十年以上にわたって貿易で世界最大の十兆円程度の黒字をずっと出し続けてきました。一九九〇年以降の長期不況期間においても、毎年「まもなく輸出はだめになる。」と警告されつつ、結局はそうはなっていません。九一年には海外純資産保有高で英国を抜いて世界一位となり、不景気の九〇年代になってもさらに経常収支の累積黒字は倍増しています。これによる投資から年間九兆円もの投資所得を受け取る日本の収支構造が出来上がってきています。日本はまもなく「貿易立国」の国というよりは、「金貸し立国」にさえなる傾向にあります。 貿易黒字と所得収支黒字の二十兆円に近い黒字の内の一部を海外旅行とODAに使い、最後に残る約十兆円が海外投資にまわされます。海外純資産は毎年約十兆円増えていく構造です。 世界のどこの国からみても、こんなに羨ましい国はないと言わざるを得ないのです。
不景気の真相 それは、国内の経済に問題があるのです。図4を見ると、日本のGDPは九〇年までは成長を続けていましたが、その後現在に至るまで飽和状態になっています。
GDPが飽和して何が悪いと言われるかもしれませんが、実は経済上では問題が生じます。歴史的に社会は、年間平均二パーセントずつ生産性の向上(合理化)を果たしているそうです。したがって、GDPが二パーセント上昇しないと失業者が出ることになります。失業が増えるときには社会に不景気感が広がる。その意味で、GDP二パーセント向上は不景気と好景気の分かれ目です。 GDPはなぜ飽和してしまったのでしょうか。GDPの構成比率の主要な部分は個人消費で、六割ほどです。個人消費が伸びないと民間の設備投資が伸びない。個人消費が九〇年以来飽和してしまったのです。
巨大な官民共同老後保険形成時代 しかし、本当にそうなのかはきちんと確認する必要があります。例えば日本の郵便貯金は、一九八〇年代に増え始め、九〇年代にはさらに二倍に増えました。個人資産は、現在千四百兆円。GDPの約三倍という巨額です。一家四人の家庭で平均五千万円。貯蓄の所有者は六十五歳以上の高齢者が七五パーセントを占めるとされます。 昨年度のニッセイ調査によれば、日本人の遺産はアメリカの四倍に達したそうです。可処分所得の二十一年分が平均遺産ということです。貯蓄は使われずにそのまま遺産になる。日本人のメンタリティであると言っていいのかもしれません。 それでは、老後のために貯えた個人貯金は一体どこにいったのでしょう。株式投資には一割しかいかなかった。アメリカは五割です。元本が保証される郵便貯金や銀行預金にほとんどがいっています。 預けられた郵便局や銀行は、借り手を探さないとなりません。金利が低いといえども、手数料をかせがねばなりません。しかし、九〇年代民間企業には貸すわけにはいかなかった。むしろ、「貸しはがし」の時代でした。では九〇年代、郵便局や銀行は誰にお金を貸したのでしょう。この間、国や地方自治体が作ってきた財政赤字七百兆円がそれです。国民の金融資産、千四百兆円の半分は政府と地方自治体に貸し出されていることになります。 七百兆円は国の税収十四年分です。税金を一銭も使わずに返却しても、政府の作ってきた七百兆円の財政赤字を返すには十四年かかるのです。私たちが生きている間に、政府はこのお金を国民に返せるでしょうか。そのはずがないと、私には見えます。しかも、逆にこのお金が老後保険であるとすると、国民は返されても困ってしまいます。この膨大な貸借の関係はしたがって、当分塩漬けにするしかないと見えます。 一方、もしも金利を払ったとします。年利五パーセントとすると、七百兆円に対する利息は三十五兆円。税金五十兆円の大半が無くなってしまいます。つまり、日本はゼロ金利時代を続けざるを得ないのです。 ただし、日本人が貯めた千四百兆円のうちのある部分は海外に貸されている。海外純資産二百兆円がそれに当たります。それが米国の国債購入などの投資に充てられていて、毎年十兆円に近い所得を海外から得る構造となってきました。現在、金利を生んでいるのはこの部分だけです。 ここまで見てきたようなデータから、一九九〇年代に形成された日本の巨大な個人金融資産の増加分は政府に貸し出された。その所有者は高齢者である。高齢者は老後の不安を除こうとこのお金を蓄えている。借りた側、貸した側ともに当分そのままにしておくしか仕方がない事情をかかえている。 したがって、一九九〇年代の日本は長期的な「巨大官民共同老後保険形成時代」にあったと言わざるを得ません。
借りた人は使ってしまっている 海外に貸したお金を例外として国内だけで考えますと、次のことが言えます。「国全体として後世にお金の貯蓄を残すことはできない」ということです。つまり、現在、千四百兆円の貯金を国民がしていても、それは後で必要なときにいっせいに返してもらえるという訳には行かないということです。なぜなら、そのお金は使われてしまっているからです。あるいは逆に、「後世に借金を残すことも、国全体としてはできない」ということになるわけです。 新聞などでは、「政府財政赤字は子孫に赤字を残していること」とよく言われております。「後世に借金を残すことはできない」という意味で、その意味は誤解を招く言い方です。 すなわち、国民が貯めた千四百兆円はなにかに使われざるを得なかったのです。問題は何に使うか、将来の子供たちを幸せにするようなことに使えるのか、それが実は問題だったと言うことになります。政府が使ったからいけないということでは決してないのです。一九九〇年代は、国民が巨額なお金を貯めたが、その良い使い道を見つけることができなかった時代ということになります。良い使い道であったなら、国民はそれを支援し、さらにそこに自分たちのお金を加えて伸ばしていくでしょう。批判に終わってしまったということは、このようなお金の有効な使い道を考える上で、政府にのみ任せたことが失敗であったことを意味しています。お金を使う主体が政府であった一九九〇年代があまり評判の良い時代ではなかったということになります。国民はそれに呼応せず、消費は不活発でありました。
生産性向上の果実の受け取りかた しかしながら、九〇年以降は、「飽食の時代」とか、「もの余りの時代」、「サービス過多の時代」と言われるようになり、第一次から第三次までの産業のすべてについて生産過多の時代になってしまいました。お金を持っているのは高齢者であったこともこの「三あまり時代」をより顕著なものにしました。 しかも、そのような状況になっていながらも、輸出は十分やっている。それなのに、三百五十万人の失業者が出ている。生産性を向上させてきたからです。 これだけの事実を足し合わせると、出てくる結論は、「日本人は生産性を向上させたのに、果実の受け取り方を知らない」ということになります。これまでは、技術開発が活発に行われれば新規産業が興り、景気はよくなると、単純に考えられておりました。しかしながら、それだけでは飽和傾向を打破することはできていません。 「新製品」に皆が価値を感じられるようにし、それを購入できるようにしなければならなくなってきているということになります。
生産性向上と新たな価値創成 サービス業も、生産性を向上させ、そして現在、五パーセント近い失業者、すなわち労働力の余剰が出てしまいました。GDPが五百兆円程度であることを考えると、単純には、失業率五パーセントは二十五兆円分くらいの産業の不足を意味します。 それではこの五パーセントの人たちはどうすればいいのでしょう。単純に考えますと、第四次産業を興せばよいことになります。ただし、これまでの一次から三次産業とは質的に何か違うものでなければなりません。この第四次産業が作り出すべき新しい価値を、「第四の価値」と呼びたいと思います。 科学技術の進展によって「生産性向上」と「新製品開発」の二つが繰り返されて、経済成長が成し遂げられて来ました。しかしながら、どうも九〇年以降、これだけでは不足しています。もちろん、科学技術は従来型のこのような経済成長への努力はしてきています。しかし飽和状態に至っているのです。 その「飽和」を招いている一因が、高齢化であることは既に述べました。そして、さらに、よく言われる「環境破壊」の問題であり、多くの人々が「これ以上資源やエネルギーの浪費に加担したくない。」と考えるに至ったことも大きいと考えます。そして、「飽食の時代」「もの余りの時代」「サービス過多の時代」が到来したのです。 したがって、二十一世紀の日本の経済成長があるとすれば、それはこれまでの第一から第三までの価値とは質的に異なる「第四の価値」を実現する新製品の開発であると言うことができます。第三までの価値はいずれも飽和に近いからです。では、第四の価値とは何でしょうか。
個人の欲望の充足から仲間や地域の正義感へ 私は学生たちとよく議論しました。「今お金があったら何を買いたい」と聞いても、学生たちは首をかしげる場合が多いのですが、「仲間や地域で欲しいものはあるだろうか?」と訊ねると、実は「たくさんある」と言い出しました。しかも、欧米に比較して「日本では入手が難しい」と言うのです。
個人では入手の難しい第四の価値 こころ、美しさ、生き甲斐、社会正義といったキーワードと関連することが日本では満たされていないというのです。 それらの価値を追うことは、いずれも一人で努力しても難しい。しかしながら、それらの価値の規模は非常に大きなものがあります。もしも、このような価値を社会が価値として認めることになれば、あるいは、資本主義の国では貨幣価値に置き換える工夫をすることができれば、これらの価値は非常に大きな経済価値をも有するものです。
科学技術の意義 「第四の価値」は、したがって、仲間や地域の願いや正義感を実現することに使われる科学技術と関連するはずです。これからの科学技術は、個人の夢だけではなく、「仲間や地域の夢」を果たしていく。集団で夢を語ると日常個人では意識する事の少ない「正義感」のような価値観が人の行動を決める面が出てきます。
未来は現在の中に胎動している 二十人ほどの学生が大学近くの我が家に遊びに来たことがあります。そこで、私は「今生きている日本人で、君たちに最も影響を与えている人を一人挙げるとしたら、それは誰か?」と彼らに訊ねたことがあります。これは驚きでした。最初のうち彼らは、「イチロー」とか、「田村亮子」とか、いろいろな名前を挙げていました。ところがそのうちに、ある学生がこの人の名前を挙げたら、全員直ちに「異議なし!」と答えたのです。私はびっくりしました。そして私はその名前を知ってはいましたが、その人の作品をきちんとは見たことがありませんでした。「宮崎 宮崎駿は、ひととひととの争いとこころの優しさ、ひとと自然との間に生じる矛盾と自然へのおもいやりといったメインテーマを扱うアニメ作家です。今では、日本だけでなく、アメリカ、ヨーロッパの人々の心をも捉え、「宮崎駿」の存在が「日本の文化」を世界の人たちに感じさせる。そういう存在です。学生たちが、全員「異議なし!」と力のある言葉で答えたことは、私に強い印象を与えました。これはすごいことだなと思いました。 私の世代は、日本を豊かにし、おなかいっぱい誰でも食べられるようにし、便利に、快適に生きることができるようにとがんばってきた世代です。それに対して学生たちは、違うスタートラインに立っています。豊かさの中に育った彼らのもとめる生きがいは何か。「宮崎駿の世界」にその解の一つがありそうです。 実は学生たちが「異議なし!」と答えたとき、私は「君たちはそんな低俗な漫画が好きなのか」といった感じの対応をとったようです。私の息子と娘はちょうど学生たちと同じ年代でありました。私のその言葉を非常に恥ずかしく思ったようです。彼らは週末に宮崎駿の代表作の一つである『もののけ姫』というビデオを借りてきて、私にどうしても見るようにと迫りました。私が「漫画なぞ見ている暇はない」という態度をとったところ、「そんなことだったらもうお父さんとはつきあわない」と、思いつめた雰囲気を感じました。 私がテレビを見ている間、息子と娘が後ろに座りました。私は監視される形でした。そして、見始めてから私が流した涙の量がある程度に達して以降、急に息子と娘が、私を話の中に入れるようになったという雰囲気の変化を感じました。 それまでの彼らの心の中に、「お父さんは工学部の人間」。工学部は「開発」。開発は自然の「敵」、といった感覚があった。一緒に住んでいながら、口では言わないが、「いずれは征伐されるべき対象」といった気持ちがあったのでしょう。その父親が『もののけ姫』を見て涙を流している。 いまの若い人たちにとって非常に大切なことは、こころとか自然とか美しさといったことになってきている。しかし、現在の社会はまだ豊かさを追うためのシステムしかできあがっていない。若者たちの願いを十分に汲み上げられる社会になっていない。彼らはそのことにもどかしさを覚えている。そのもどかしさに、我々大人は気づいていない、ということなのでしょうか。 このような若者たちは、刹那的に生きているとか、無気力であるといった批判を受けています。私は彼らが自分たちの新しい夢を果たしたいという気持ちと、現実の社会システムの中でそれが難しくもどかしさを感じることとは裏腹であり、願望の方向は似ているように思えます。これは社会システムの問題であると感じるのです。
環境投資はネガティブ投資か いま、よりコストのかかるクリーンなエネルギーに頼って電力を得ることを考えたとします。私たち大人は風力や太陽光発電など、いまよりもコストが二倍以上かかる発電方式はだめと考えています。少なくともコストがいまと同じレベルに下がらない限り「ネガティブ投資」でしかないと考えます。これは若者たちに受け入れられるでしょうか。 よくよく考えて見ますと、個人の使うお金で最大のものはいまや娯楽費です。娯楽費は今、百兆円を越しそうな勢いです。GDP五百兆円の二〇パーセントです。この中には旅行やパチンコなどの遊興費も含まれます。パチンコ売り上げ二十七兆円は我が国最大の産業の一つです。ごく最近三十兆円を超えたとも言われます。日本の製造業は百三十五兆円くらいですから、まもなく娯楽産業が製造業を抜く時代に入ってきている。そのような時代に、「環境がネガティブ投資」といった私たち世代の考え方は通用するだろうか。 つまり、若者たちが「お父さん、僕たちはこれからクリーン電力を娯楽費の中に入れます。お父さんたちは電力のコストを必死に下げて十五兆円で賄い、その代わりパチンコに二十七兆円を使う社会を作ってきました。僕たちは二倍高価になっても構わないからクリーンな電力に三十兆円のお金を使い、その残りの十二兆円だけパチンコに回そうと思います。」と提案してきたらどう答えるのか。 幸せという言葉と生き甲斐との間にはかなりの共通点があると思います。ひとが幸せや生き甲斐のために生きようとするとき、それはネガティブ投資と呼ぶのか?さらに、娯楽に投資するのはどうなのか?娯楽は百兆円。また、健康費は三十兆円。教養費は?教養と娯楽はほとんど区別がつかないと私は感じます。私たちの食費は「カロリー摂取と栄養補給」とはもはや言えない。個人消費のほとんどはこういうものになってきました。生活必需項目への出費は個人消費の中のかなり少ない部分になってきている。私たちの若かった頃の常識は、いまの常識とかけ離れてしまってきているということであります。 「環境はネガティブ投資」になってしまうかどうかは、誰がそのコストを負担するかで決まります。ある電力会社が環境投資してゼロエミッション発電にしたとします。その会社だけが自分で払うのでは、ネガティブ投資と言わざるを得ません。次にそれを価格転嫁したとします。しかし、その電力会社管内の人たちだけが負担するのでは、その地域の企業は他の地域と比較して競争力で損をします。平準化の必要があります。さらに、日本だけで平準化すればよいかという疑問があります。これは日本の国際競争力に余裕があるかどうかにもよる問題です。 しかしながら、一つだけ確かに言えることがあります。日本は百兆円ものお金を娯楽につぎ込んでいても、「国際競争力は最も強い国」であるという事実です。 すなわち、環境をネガティブ投資にしないためには、そのコストを社会全体で負担できる社会制度ができればよいと言えます。たとえば、電力コストが二倍になったとして、その増分十五兆円を娯楽費から工面するとしましょう。つまり、パチンコをすこし節約して二十七兆円から十二兆円だけにするのです。これが第一の方法です。この場合の問題点は、お金の動きが変わるに連れて産業移行が生じ、従事者の移動も必要になるということです。しかし、これはお金が動くにつれて自然と人は流れるはずですから、お金が自然と流れるような社会システムを作ることができるかどうかに懸かります。その典型的なやり方は国民の意識を変えることです。これには教育や国民運動などが力を持つことになるのでしょう。 もう一つの極端な方法は完全に税金などによってその事業を始めてしまうやり方です。これはスモールガバメントに逆行するやり方になりますので、基本的に増税の方向です。つまり、人々にお金の支払いを何にするかを決心させる代わりに、国が決めようとするものです。しかし、このやり方は一九九〇年代の誤りを繰り返す可能性があります。 第三の道は、国民が自然にライフスタイルを変えていく「お金を使う決心段階」を多様化することです。すなわち、個人が決める方式と国が決める方式との中間に、「仲間や地域」という単位を活動できるようにする。そうなると今までとお金の使い方が自然に変わっていきます。 この第三の道がこれまでの日本では弱かった。
国際競争力と第四の価値追求 第一に考えられることは、電力代の上昇分を例えば娯楽費から工面した場合には、人々の支出総額はまったく変わらないのですから、国際競争力に特に変動は与えないはずと言えるでしょう。 さらに、もっと積極的な方法として、これまでの日本の経済活動のどれをも削ることなく、新たに十五兆円のクリーン電力増分を作ることを考えたとします。 この場合は経済活動として「生産性を向上させ新製品を作る」という活動の「新製品を作る」ことに対応します。つまり、国民の意識が変わることで、これまで「新製品」になれなかったものが新製品の資格を得るのです。 その場合にはGDPがいままでよりも十五兆円増えることになります。日本は第一から第三次産業の製品を十分に作り、しかも輸出はしっかりやっていました。しかも、約五%の余剰労働力を抱えています。 GDPを十五兆円分増やすということは、この五%の余剰労働力分をちょうど吸収する程度の経済活動に相当します。いまでもこの余剰労働力分については、生活ができる程度のお金は福祉など社会として工面されているはずなので、ここにあともう少しのお金とリーダーシップが発揮されれば十分に自発的に経済として回転し始めるものと考えます。そのちょっとした呼び水をどうして撒くことができるかが問題でした。第三の道、すなわち「仲間や地域」の活動を活発にすることがその呼び水になるのではないでしょうか。 第四の価値を社会に浸透させるための仕掛けとして「仲間や地域」の活性化はどうしても必要です。 私たちの意識としては次のように言えます。娯楽に百兆円も使える国が、なぜ町の美化や緑化、リサイクルの推進といったことに数兆円も使えないのか。日本はそんな志の低い国なのか。 そういう見方で我々がこれまで築き上げてきた日本の経済社会システムを見直さなければいけない。どうやったら若者たちの気持ちを素直に表現できるような経済社会構造にしていけるか。「仲間や地域」が考える正義感に添うような選択ができるよう、国民がお金を負担できるような仕掛けを作っていかなければいけないと言えるのではないでしょうか。 なぜ私が、科学技術振興機構という立場でこのようなことを申し上げるかといいますと、これまでの科学技術振興策は、常にプロセスイノベーションと新製品開発に向けられていた。仲間や地域の正義感を生かすような科学技術の方向を露わに考えるといった観点が欠けていたことが反省されるからです。このままではもはや飽和してしまう。二十一世紀にはさらに「仲間や地域」を科学技術の振興の際の重要な担い手として意識していく必要があると思うからです。 NPOの経済規模 未来への胎動として、現在、急速に始まりつつあるNPOの活動に注目してみます。NPOの最大の特色は「集団の正義感」を基本として活動する法人であるということです。お金をとって活動しても構わないし、人を雇用することもできます。ただし、利潤が得られた時にはそれを経営者たちが分けてしまってはならず、本来の目的のために再投資しなければならないということです。「第四の価値」の定義は「集団で考えた時にのみ入手できる価値」でしたからNPOとは密接な関わりができるのは当然です。 まず、NPO経済を過小評価してはならないと申し上げたいと思います。私たちの心の中に「NPOやボランティア活動は国の経済の主要な部分にはなり得ない」と思っている人が多いからです。 先ほど、日本の失業者数は三百五十万人と申し上げました。アメリカではNPOに雇用されている人がすでに一千万人もいます。アメリカの人口は日本の二倍ですから、同程度の規模のNPO活動が日本にあったら、日本には失業は生じないということになります。 アメリカの家庭では、「自分のサラリーの中から五パーセントをNPOに寄付できるようになるということが、一人前の市民になることの証」と、両親が教えながら子供たちを育てているとされます。宇宙飛行士の毛利衛さんの奥様のお話では「宇宙飛行士仲間ではさらにこの目標値が高く、一〇パーセントだったので、年度末の税の申告期には、どこのNPOに寄付するのがよいのかが、皆の集まりでは話題の中心であった」ということです。ごく自然にNPOに寄付をできる国民性を育てる社会経済構造がアメリカにはできてきている。それが、アメリカの広範なNPO雇用を支えています。 アメリカでは、図5のように、個人によるNPO寄付は一人当たり年間十万円です。日本は三百円、赤い羽根三本分です。その代わり、図6のように、日本人はギャンブルに一人当たり年間平均二十万円以上を消費していますので、日本の個人にお金がない訳ではないのです。社会の仕組みがどのようにできているかの差によって、NPOに活躍してもらおうとする国民が増えるか、それともギャンブルにお金を投入せざるを得ない国民ができるかが決まっているのです。
アメリカでは税制が寄付の文化を後押ししています。税の申告をするときに、どのNPOにどれだけ寄付するかを記入すると、それに応じた税控除がなされるのです。税の申告時期にはこのために、家庭の奥様方の井戸端会議の話題が「どこのNPOがどんな活動をしているか、自分が味方したいのはどのNPOか、その理由はなにか」といったことになる訳です。アメリカの国民の税負担は日本より高いにも拘わらず、二桁以上も大型の寄付が自発的になされているのです。日本の財務省は「税が減ってしまう」という理由でNPOの税控除制度を認めようとしないとされていますが、アメリカの例は非常に参考になります。 さらにすごいのはオランダです。ここ十五年ほどでオランダのNPOは急成長を遂げ、GDPに占めるNPO活動の経済比率は図7に示すように一八パーセントを超えました。日本で一八パーセントというと、自動車産業より遥かに大きな産業に相当します。日本の娯楽産業が全体でGDPの二割程度ですから、オランダ国民はNPOに日本の娯楽と同程度の重要性を与えているということができるのではないでしょうか。
オランダのNPO活動活発化の最大の理由は、勤務時間の自由化(一九八二年の労使協定によるワークシェアリングの奨励)にあるとされます。余暇を得た国民がその時間を何に生かそうとするのか。その例として学ばねばなりません。 結局のところ、衣食の足りたひとびとはさらに幸せを求めて活動しようとします。その時にパチンコに行くしか生き甲斐のない国を目指すのか、NPO活動を通じて文化活動や環境・アメニティの改善、介護や青少年活動の支援などに時間を使うことのできる国を目指すのか、それは余裕のできた国がどちらを選ぶかの差ということができると思います。個人では与えられた社会制度の中でしか行動できない。日本の個人はNPO活動の自由度を非常に限られた範囲でしか与えられていないと言えるのではないでしょうか。 いま、NPOへの寄付に対する税控除による支援策の導入が最も大切なことになるのではないかと思います。 本日は、「第四の価値」創成が今後の日本の経済活性化に大きな役割を果たし、失業を解消するための道であると考えられること、「第四の価値」創成の包括的な方向は「仲間と地域」の活性化と深く関わると考えられること、また、その方向は日本人の生き甲斐や若者の夢と関わるものであることをお話させていただきました。 ご清聴ありがとうございました。 (科学技術振興機構理事・東大・理・昭41・工博[MTI])
※本稿は平成16年11月22日午餐会における講演要旨です。
|
||||