学士会アーカイブス
「日本的経営」の何が残るか ロナルド・ドーア No.849(平成16年11月)
はじめに 多様な資本主義 日本ではよく、「日本と欧米」という概念の規定をします。欧米ではもう既にこうしているから、日本もこうしなければならないとか。ところが欧米は、決して一つではありません。先のアルベール氏の類型はどういうものかというと、彼はアングロサクソンのキャピタリズムと、その対極としてのライン・キャピタリズム(ライン川キャピタリズム)という二つの類型を出します。 アングロサクソン・キャピタリズムとはアメリカ、イギリス、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアのような経済で、株式市場を中心とする、市場主義を貫徹したような経済制度をいうのであって、ライン川キャピタリズムの原型として、彼はドイツをあげていました。しかし、ドイツと、日本は非常に類似している。これは初めて指摘されたのではないのですが、アルベールのお陰でかなり広く知られるようになった説です。 「支配的常識」の変遷 六〇年代になって日本が一〇%以上の成長率を獲得すると、「まあ、さほど変えなくてもいいんじゃないか」というムードになってきます。当時アメリカのアベグレンという人類学者が、日本の工場を調査して、その本が訳されて日本でも相当はやったのですが、日本はその特殊的文化、伝統に適応した、アメリカと違うシステムを作っており、それもまた結構バイアブルであるという考えが段々常識となりました。
『ザ・アート・オヴ・ジャパニーズ・マネージメント』『日本的経営と禅』『日本的経営と茶道』等々、優れた日本的経営は、日本の伝統的文化に根付いていても、それをアメリカ人がまねできるし、まねすべきだという考え方が普遍的になりました。同時に日本人が横柄になって嫌だなあというような印象をもつ外国人も多くなりました。事実、日本で、自国の制度が世界一であるというような意識が芽生え、やや傲慢になる経営者も無きにしも非ずでした。 ところが、バブル崩壊後、なかなか日本の景気が直らない九〇年代になると、そういうムードは全く変わってきました。高度成長期には合っていたかもしれない日本的経営がもう機能不全になった、これから、グローバル・スタンダードに適応するように、日本的経営を抜本的に変えなければならないというような考え方が、日本でも外国でも支配的になりました。 二つの資本主義における「企業」の相違点
また経営者も、日本の場合は生え抜きで企業の中で育つ、組織の人間ですが、アングロサクソン型経済における経営者のキャリア形成はというと、まず小さな会社の社長で成功し、より大きな会社の社長になるため、外部労働市場を通じてキャリアを作っていく。それも組織志向型と市場志向型という対照的規定の根拠の一つです。 もう一つの規定の仕方は、日本の企業は「準共同体的」で、アングロサクソンの企業は、単に個人間の契約のマトリックスでしかないという主張です。どういう意味かといえば、前者は、東大の岩井教授が強調するように、企業の実在、法人実在という概念を基礎に据えています。 「法人実在」という意味は、企業はたとえば大学と同じように、学生・教授の世代が代わって行っても東京大学は永遠に残るというような、同じ意識を企業の人も持っている。会社の人はそういう意識を共有しているという指摘です。もう一つの規定の仕方、伊丹教授の規定ですが、日本の企業が「人本主義的」で、アングロサクソンの企業が「資本主義的」であるといいます。これは、ヒューマンリソーセスを最も大事なものとするか、あるいは資本的・金融的リソーセスを最も重要視するかという違いに着目しています。 「長期継続関係」対「限定的契約的関係」という物々しい規定の仕方は明らかでしょうが、前者は、雇用の関係だけでなく、協力会社、下請け会社、納入する会社との取引関係にも当てはまります。金融についても、銀行と会社との関係をなるべく長期的関係として、大事に育てていくというものです。それに対し後者は、その場その場の市場の需給関係や価格関係に支配された短期的契約によって自分の選択の自由を失わないで最大のコスト低減を図ることが奨励されている資本主義であると規定しています。 最後に「従業員主権」、あるいは「株主主権」という対比の仕方もあります。この抽象的規定の具体的な意味は何かというと、このスライドにいくつかの特徴が羅列してありますが、まず終身雇用ですね。次の「官僚的昇給昇級システム」ですが、英語でも「bureaucratic」といえば、けなす意味で使うことが多いし、日本でも「官僚的」といえばそういう意味ですが、日本の企業の給料や、ランクを上がっていくシステムは、イギリスにおける警察とか軍隊とか、官僚の昇給システムと非常に類似していますし、日本の官庁のシステムにそっくりです。
日本は「生え抜きの経営陣」つまり、ほとんどの経営者が、その企業へ大学を出てすぐに入った人が非常に多いのです。ところがアングロサクソンの場合では、外部労働市場から取締役会の指名委員会、報酬委員会との長い交渉の末、契約をして採用される社長や役員が多いのです。 また従業員の利益を株主の利益に優先させる経営方針が、少なくとも九〇年代までの日本には一般の常識でした。九〇年代前半、バブル崩壊後に段々企業の経営が苦しくなって、利益が益々減っていったとき、株主にはなるべく安定配当だけは払ったが、従業員の首も切らずに、内部保留を取り崩しても賃金も世間並みに維持していこうとしていました。 そして最後の制度的特徴としてあげられるのは、こういう従業員優遇を許した重要な条件として、たいていの企業は敵対買収される可能性がほとんどない位、安定的な株主を持っていたという条件です。多くは株の持合いの形で。九〇年代までの日本では当たり前とされていた企業のあり方はだいたい以上のようなものでした。 ところが、特に九〇年代の後半に、それを改革しなければならないという議論が非常に活発になりました。その時指摘されたのは、景気が悪く企業利益の上がらない時には、今まで強みとされていた長期的関係が、逆に会社の足かせになる点です。リストラをする際、希望退職者に相当な報酬を出したり、下請け会社を大事にする余りに中国などからの非常に安い部品調達の機会を逸したり、また、取引銀行の手前、市場において有利な株や社債を調達するのが難しいなどの弱点がある。そういうようなことが盛んに言われるようになりました。そして終身雇用制にいたっては、全く根本的に考え直さなければならないということが強調されました。
日本の不祥事という言葉の使い方は、非常に面白くて、エンロンとかワールド・コムが問題になった時には「不正事件」と言うのに、日本の場合だけ「不祥事」という言葉になります。その使い分けの理由は何でしょう。 しかし性質は確かに違います。あるアメリカの友達が非常に面白いことを言いました。「In America, directors steal from the firm, in Japan, directors steal for the firm」。つまりアメリカの役員は企業から物を盗む。ところが日本の役員は、企業のために物を盗むと。そのような違いは確かにあります。 日本の不祥事には三種類あると思います。一つは総会屋への供与の問題です。もう一つは、たとえば山一證券のように法律違反の粉飾決算を秘密に行うが、その動機は、会社が倒産してみんな駄目になるよりも二、三年粉飾を続けて、もし景気が持ち直せばなんとかなるというものでした。同じようなことがアメリカの大銀行で一九八〇年の前半の南米危機の時に、ありました。やはり粉飾決算して生き延びて、景気が良くなったから問題にされなかったのですが、日本の場合は不景気が長引いて、山一證券はご存知のように倒産し、その粉飾決算が明るみに出てきたのです。 当時お詫びに出た山一證券の社長がテレビのインタビューで謝罪した際、最後に「山一證券の従業員はどうなるのか」と聞かれて涙を流したという場面がありましたが、それこそが「会社のための不正」を象徴しているのではないかと思います。 第三の不祥事というのは最悪で、雪印とか三菱モーターズのように、会社のために、消費者やお客を欺いたり、害をなすようなものをいいます。それこそ、今頃はやりの企業の社会責任問題として大いに取り組まなければならない間題だと思います。 「日本的経営」見直しの気運
そこで、米国をモデルにしなければならないとされていた理由として、概ね二つの点があげられました。一つは、不祥事や粉飾決算などができないように、透明性を確保すべくアメリカのようにコーポレート・ガバナンスのシステムを導入しなければならないこと。もう一つは、大企業の研究開発部だけに依存する日本の技術開発システムより、アメリカのようにベンチャー資本と大学などの個人の発明家を融合させるシリコンバレーのモデルの方がずっと効果的であって、大企業病の元凶のような日本の研究開発制度は、だめであると指摘された点です。 その二つの米国モデルの魅力的特徴はその後多少陰りを見せるようになりました。シリコンバレーはナスダックの暴落の後でさほどモデル的に見えなくなりましたし、アメリカのコーポレート・ガバナンス・システムが最も優れているという神話も、その後のワールド・コムとかエンロンのスキャンダルなどによって、かなり損なわれたのですが、依然として少なくとも先入観としてやっぱりアメリカをモデルとしなければならないとする人が大勢いると思います。 もう一つ、改革ムードを醸し出した要因としてはアメリカの大学やビジネススクールでMBAやPhDを取って帰って来た若手官僚、若手ビジネスマン、経済学者がだんだんと日本の大学や政財界を支配するようになったということがあげられます。 また、そこで「知的領空」という言葉が当てはまるかどうかは解りませんが、ともかく彼らが「知的領空」を支配するような雰囲気に変わってきたことがあげられると思います。 そして最後に、外資系の投資家が、九〇年代に入ってかなり流入してきました。九〇年代初め、日本の証券取引所の取引額の一〇%以下だった外資系投資家が、九〇年代終わり頃になると二〇%になりました。しかも証券取引の半分位が外資系の投資家間の取引でした。それは大きな変化であり、その外国の投資家、たとえばカルパースのような年金基金などが、日本の企業の株主総会で発言したり、また、特に法律の改正などについても、東京のアメリカ商工会議所の金融小委員会の人たちが財務省、通産省、また自民党の若手代議士や議員立法の草案者などに、外資系投資家に有利なように、日本の法制度を変えなければならない、という意味の圧力をかけていたことが大きく影響しているのではないかと思います。 改革の気運がそういうところから来たと思いますが、その主な枢軸というのはどういうことかというと、一つにはコーポレート・ガバナンスの改革によって、経営と監視の機能を分離して、そして、企業に対する外的監視の強化をはかる。それはたとえば、株主の代表訴訟制度を確立させたり、取締役会と執行役員とを区別して、取締役会にも社外の重役や監査役を入れるというようなことです。実際来年からあらゆる日本の企業は監査役会に社外監査役を多数、持たなければならなくなります。そういう外的監視・外的規制を強めることが一貫した軸の一つです。
金融危機で銀行が非常に景気が悪かった折、法律も手伝って銀行はかなり持合い株を放出していきました。実際敵対的買収の可能性が大きくなったようです。最近の日経新聞をご覧になると「新会社論」という面白いシリーズを載せていましたが、いかにして今の経営者が、それを恐れなければならないようになっているかを具体的な例をあげて面白く書いています。 安定株主構成を作り直そうという意欲は経営者にはあると思いますが、その一つの障害になっているのが、会計制度の変化です。今自分が持っている株を簿価でなく時価で資産計上しなければならないようになったことが、資産構成を変動的なものにしてしまい、非常に具合が悪い。時価評価主義に移ったということは、長期的な目標を持っている経営者にとっては、ありがたくないのですが、敵対的買収をしようとする経営者には願ってもないことではないかと思います。 最後になりますが、やっぱり従業員福祉優先から株主福祉優先へ移ろうという動きが、かなり強く出ていると思います。また「物を言おうとする株主に物を言わせなければならない」という意識が普及してきました。株主の代表訴訟権が強められたし、「シャンシャン総会」のように、従業員株主を前列に座らせて、何でも「異議なし」と十分位で終わるような株主総会は、もう通用しなくなりました。 現実はどれくらい変わったか、この間見たある統計によると、一九九〇年においての株主総会の平均時間は、二十九分だったのが、二〇〇〇年には三十九分になっています。また、いわゆる集中日を避けて、より多くの株主が出席できるようにする会社も多くなりました。 「物言う株主」には二種類あると思います。一つは、たとえばアメリカの年金基金、カルパースがその草分けですが、彼らは、株主の金銭的利益を追求する「物言う株主」です。今は、たとえば厚生年金基金連合会のように、そういう半ば安定株主になっている株主の声を代表する大きな組織が現れてきました。同時により投機的な投資ファンドもあります。最近、非常に物議を醸したのは、もと通産省にいた村上世彰さんという方のファンドが東京スタイルの総会で大攻撃を展開しました。「総会屋まがいの物言う株主だ」という評判もありますが、この東京スタイルという彼が標的にしていた会社の社長は、二十四年間も居座っていて、全くワンマン社長であったそうですから、いい刺激になったかもしれません。 このように株主の利益だけを考える株主総会もあれば、また株主オンブズマンのような、市川房枝さんの「一株一票」、「一株買い運動」に根を下ろした、会社の不正(三菱モーターズとか雪印)を代表訴訟制度を利用して是正させようとする市民運動など、私に言わせれば非常に称賛に値するようなものもあります。 そういう改革の枢軸が三つであったとすれば、実質的に日本的経営はどう変わったかというと、まず企業内の昇給昇級制度には多少の変化がありました。企業再生の場合には、外から社長を迎え入れることが以前も今も多いのですが、倒産やあるいはそれに近い状態でない企業において、社長を外から迎え入れたところは非常に少なくて、やっぱり経営陣が生え抜きである点は依然として残っています。
この間非常に面白いコンサルタントの論文を読みました。彼はある企業で、業績給の制度を取り入れて、二年間その運営を監督していたのですが、その論文によれば、四十歳の経営者の給料のばらつきを計って、業績給を入れる前の年功序列制だった時と今とを比較してみたが、あまり変化がなかったと言っています。それを彼は「けしからん。やっぱり経営者が、我々が考えたすばらしい制度を歪めて運用しているんだ」というふうに結論づけていましたが、「公平なばらつきは何であるか」ということについての調査によると、数年前のデータですが、現状はさほど多くは離れていませんでした。給料制度、賃金制度を名目的に変えても、結果的にはあまり変わらない例が多いのは当たり前だと思います。 職務発明と知的所有権については、最近日亜化学工業という企業に勤めていた中村修二という人が二千億円という膨大なお金、それは日亜化学という小さい企業が六年間であげた利益の総額に近い額ですが、それを法廷で取り付けたというような事例がありました。これは今まで共同体主義的な企業であったものが、非常に個人主義的になってきているということの象徴かもしれません。ウエットではなくて、よりドライに、没我的ではなく、より個人主義的になっているという傾向はこのように多少は見られますが、それでも全体としてはさほど雰囲気が変わらないと思います。 しかし二番目の変化は、実質的に大きなものではないかと思います。つまり、経営者が株式市場における自分の株価をますます、意識して経営するようになってきている点です。この間ある社外重役の話を聞きました。その会社の取締役会で最近話題になった案件はというと、たとえば「儲かっていない子会社の株を五五%持っているところを四五%に減らして、連結決算からはずせば、ROA(Return On Assets)が上がって株価も上がる。そうしよう」というのがありました。これは対株式市場戦略がますます経営陣の時間や意識を占領するようになってきている一つの例です。こうした傾向は、長期的展望に基づくという従来日本的経営の特徴とされてきた経営志向が失われる結果に終わるのではないかと危惧されます。 もう一つの大きな変化は、先程、普通の社員の給料制度や昇級制度はさほど変わらないと申しましたが、正社員の数を減らして契約労働者や派遣労働者、フリーターとかパートとかという人をより多く使う傾向が、最近強くなってきました。現在はそういう非正規的な労働者の数がもう既に三〇%を超えている状況です。 最後の実質的変化は、労使協議会や労働組合の発言力が最近弱くなっているのではないかということです。春闘さえ、もう要らないというような声がよく聞かれるようになりました。 「日本的経営」の何が残るか
では何が残らないかというと現場の高卒の労働者、ブルーカラーの労働者が持っていた、自分たちも含む、準共同体としての企業への帰属意識がますます薄れてくるのではないか。言い換えれば、よりドライな関係、より個人主義的な契約的な関係になるということでもあります。そして企業内の報酬分布が、今まで比較的平等であったのが、つまり、社長の給料と従業員の平均給料との差は開いていくでしょう。『フォーチュン』誌によればアメリカのトップ会社の社長の給料と平均従業員の給料間の倍率はというと、一九七〇年においては、三十九倍でしたが、最近は千倍以上になりました。それに比べて日本はわずか十五倍か二十倍位でした。しかし今後の傾向としては、ますますアメリカ的に格差が開く方向になってくるのではないかと思います。
株主がいまして、経営者がいて、経営者は株主の代理人であるという意識が出発点。また、様々なステークホルダーもあり、うまく株主のためにいい成績を上げるのに、彼らの利益も考えて彼らの協力も得なければならない。地域社会や、販売会社、それから下請け会社、銀行、債権者、そして従業員、つまり、従業員はこの図式では銀行と同じように一つのステークホルダーにすぎないということを表しています。 しかし日本の場合は、ここで一つのピラミッドがあり、権力の上下はやっぱり権限の違いであって下は組合員。左は高校卒、右が大学卒の人で、そして生え抜きの役員が頂点にいる。そして気をつけなければならないステークホルダーは、株主とか、銀行とか、下請け企業、販売企業など変わりはないのですが、違うのは従業員は外のステークホルダーではなく、企業全体の構成要素です。そういうように図式化できる大きな違いがあるということを示そうとしています。 トヨタは非常に面白い会社です。特にスタンダード・アンド・プアーズが、トヨタが人員整理を簡単にできないからといって格下げをした時に、奥田会長がプンプン怒ったという有名な事件もありました。トヨタはやっぱり日本的であって、色々アメリカをモデルにしたコーポレート・ガバナンスの勧めを蹴ってきた会社なのです。他の会社が、みんな執行役員制度に移行している時に、トヨタも同じようなことをしたのですが、「トヨタは違う」といわんばかりに、あえて執行役員といわないで常務役員という称号を作った。そして業績給に移ろうとするのは、それもとにかくトヨタ独特のWay、日本的な会社としていますが、トヨタの重役による先日のプレゼンテーションの中に、こういうガイドプランがありました。
企業と社会 皆さんが大学に入った頃には、東大生の中に自分の親も東大、あるいは国立大学を出た人は少なかったと思います。その比率が現在だんだんと高くなりましたし、そして、特に二十年前に東京の教育制度――高等学校入学制度を変えた時以来、私立の受験校が非常に隆盛してきたのとは逆に、公立出身者が減ってきて、その受験校に入るような人たちは、ますます中流の家庭の坊ちゃん・嬢ちゃんであることがだんだんと顕著になってきたことは色々の調査が示しています。
それはどういう原因かというと、一つは教育制度の結果ではないかと思います。日本には明治時代以来、非常にメリトクラティックな教育制度がありまして、いくら金持ちの親であっても、入学試験でいい成績をとれなければいい大学や、いい高校に入れないというようなメリトクラシー(能力の支配する社会)の制度が一貫して行われてきました。 その結果として、たとえば二十年前位までの、労働組合のブルーカラー出身の指導者、あるいはその企業の改善運動を指導したQCサークルの職長達はどういう人かというと、多くは学力的に非常に優秀であっても、家庭が貧乏で、中学校あるいは高校を出てすぐ働いた人たちです。今だったら彼等ほど頭のいい人は、余裕綽々といい大学に入れるのですが、当時はやむを得ず現場の人間になりました。そういう人がもう現場に入りません。つまり労働組合の指導者になるような経歴を作らないで、直接経営層に入ったりする世の中になったのです。 それが一つの大きな原因であって、それは日本だけの現象ではなく、イギリスでも同じように労働党の教育政策をめぐって悩みの種となっていたり、論争の的になったりしていることなのです。もっとも顕著に現れてくる形はオックスフォードやケンブリッジの大学への入学システムをめぐってです。どうして公立高等学校で教育を受けた人が入れないのか、大学の方で努力して、公立高校の人たちを優遇しようとしても、そこの卒業生が選抜試験において、やっぱり落ちてしまう。そういうような階級分化の傾向が日本だけではなく、近代工業社会の普遍的な現象としてあるのではないかと思います。 そしてもう一つの要因は、中流階級が金融資産の集積をしてきたということです。ということは、戦後の十年、二十年の間はほとんど皆が貧乏であって、企業の経営者も少し株を持っている人でも、やっぱり自分の働く所の給料がいちばん大きな資産でした。しかしだんだんと金融的資産を集積してきた階層が、それでも日本にはまだアメリカのように四五%の家庭が株を持っているという状態までには到達していませんけれども、それでも自分の利益や生活の具合が資本の収益率によって大いに変わってくるという状況にいる人達が増えてきています、それが結果的に、従業員主権の企業形態から株主主権に移っていった、一つの大きな要因ではないかと思います。 そしてその教育制度の変化、階級分化が、つまり労働に依存するか金利に依存するかという利益の問題ばかりではなくて、二十年位前の経営層の人たちはどういう経歴の人が多かったかというと、まず農村生まれ、しかも兄弟が五、六人いる人が多かったのです。そして自分がその中で一番優秀な子供で、高校、大学に出してもらったような人達です。兄弟の中には、現場の労働者をしている人もいれば、八百屋をやっている人もいるというような家族関係を持っている人も非常に多かったのです。ところが今の経営層あるいは役所の官僚になるような人たちの家族関係を見れば、みんな同じ中流の上の人たちだけであって、階級を超えたような人間関係がだんだんと薄くなってきているということが、企業の変化に反映してきているのは見過ごせない点ではないかと思います。 これが、最後になりました。何だかうまく全部総括するようないい言葉があるはずなんですけれども、見つかりませんのでこれで終わらせていただきます。 (ロンドン大学名誉教授・LSE特別研究員・ロンドン大・昭22・東大特別研究生・昭25/26)
(本稿は平成16年5月20日午餐会における講演の要旨であります)
| ||||
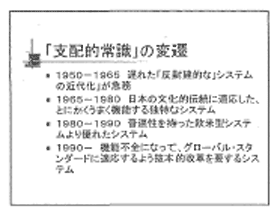 そして、八〇年代となると、アメリカの経済が停滞して、日本がアメリカよりもずっと成長率が高くなってきたら、今度はアメリカで『日本的経営の妙味』とかいうようなビジネス本が沢山出るぐらい、日本的経営には、長期的成長を重んじ、労使関係の協調を得るなどの普遍的な特性があり、アメリカも日本を見習わなければならないという説の本がアメリカにも日本にもかなり出るようになりました。
そして、八〇年代となると、アメリカの経済が停滞して、日本がアメリカよりもずっと成長率が高くなってきたら、今度はアメリカで『日本的経営の妙味』とかいうようなビジネス本が沢山出るぐらい、日本的経営には、長期的成長を重んじ、労使関係の協調を得るなどの普遍的な特性があり、アメリカも日本を見習わなければならないという説の本がアメリカにも日本にもかなり出るようになりました。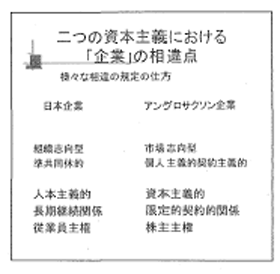 日本的経営は「組織志向型」、そしてアングロサクソンの方は「市場志向型」であるというような規定の仕方は、何を指すかというと、たとえば溶接工だと、日本だったら自分の賃金が公平であるかどうかを考える時には、同じ企業、同じ組織の中の、他の人たちと比べて考えます。ところがアングロサクソン企業における溶接工は何を見るかといえば、他の会社で、溶接工はどれだけ賃金を得ているかということです。そして組合に入れば、日本は同じ会社に雇われている人たちと一緒になるが、英米では、市場における溶接工の価値をなるべく高めようとすることに同じ関心を持っている他社の溶接工と一緒になる。
日本的経営は「組織志向型」、そしてアングロサクソンの方は「市場志向型」であるというような規定の仕方は、何を指すかというと、たとえば溶接工だと、日本だったら自分の賃金が公平であるかどうかを考える時には、同じ企業、同じ組織の中の、他の人たちと比べて考えます。ところがアングロサクソン企業における溶接工は何を見るかといえば、他の会社で、溶接工はどれだけ賃金を得ているかということです。そして組合に入れば、日本は同じ会社に雇われている人たちと一緒になるが、英米では、市場における溶接工の価値をなるべく高めようとすることに同じ関心を持っている他社の溶接工と一緒になる。 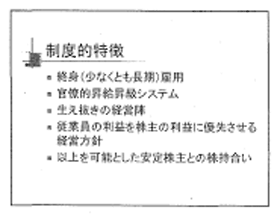 ところがアングロサクソン・キャピタリズムにおける、一般企業の人の使い方、あるいはその報酬構成は全然違います。今、日本では、「年功序列システムくたばれ」のムードが普及していますが未だ主をなしています。
ところがアングロサクソン・キャピタリズムにおける、一般企業の人の使い方、あるいはその報酬構成は全然違います。今、日本では、「年功序列システムくたばれ」のムードが普及していますが未だ主をなしています。 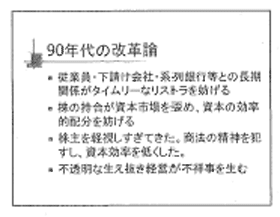 また株の持合い制度それ自体が資本市場を歪め、バブル発祥の一つの原因であったということや資本市場の効率的な機能を妨げるものだとする非難がしばしば聞かれるようになり、持合い解消の方向に持っていかなければならないという議論が非常に盛んになりました。株主を今まで軽視しすぎてきたということも大いに非難の的になって、株主を主権者とする商法が描く理念に全く違反しているから、正すべきであるという声も多くなりました。そしてまた、生え抜きの経営陣が何でも内輪だけで決定して、悪いところは隠すような不透明さが原因で、不祥事がたくさん生まれる。そんな話題が新聞にあまりにも頻繁に出るようになりました。
また株の持合い制度それ自体が資本市場を歪め、バブル発祥の一つの原因であったということや資本市場の効率的な機能を妨げるものだとする非難がしばしば聞かれるようになり、持合い解消の方向に持っていかなければならないという議論が非常に盛んになりました。株主を今まで軽視しすぎてきたということも大いに非難の的になって、株主を主権者とする商法が描く理念に全く違反しているから、正すべきであるという声も多くなりました。そしてまた、生え抜きの経営陣が何でも内輪だけで決定して、悪いところは隠すような不透明さが原因で、不祥事がたくさん生まれる。そんな話題が新聞にあまりにも頻繁に出るようになりました。 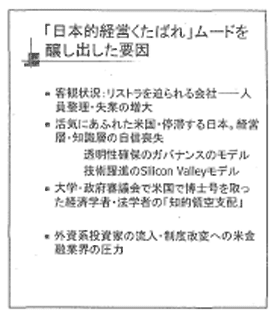 しかし、その客観的状況とはまた別の要因もありました。特に一九九七年以後の話なのですが、米国の経済が大変な勢いで躍進している時に、日本が依然として金融危機に陥って、停滞していた。私に言わせればデフレなどマクロ経済の問題が主だったのですが、そうではなくてシステムだ、日本のシステムが悪いと、日本の経営層及び新聞雑誌などに書いている学者などで主張する人が多くなった。つまり、日本人としての自信を喪失する雰囲気が蔓延したと言えるのではないかと思います。
しかし、その客観的状況とはまた別の要因もありました。特に一九九七年以後の話なのですが、米国の経済が大変な勢いで躍進している時に、日本が依然として金融危機に陥って、停滞していた。私に言わせればデフレなどマクロ経済の問題が主だったのですが、そうではなくてシステムだ、日本のシステムが悪いと、日本の経営層及び新聞雑誌などに書いている学者などで主張する人が多くなった。つまり、日本人としての自信を喪失する雰囲気が蔓延したと言えるのではないかと思います。 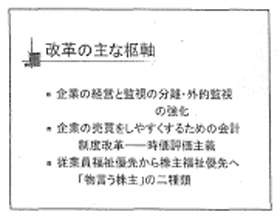 二番目には、株式市場を通じての企業に対するMarket Disciplineを、強化するというものです。一般的な経済学者の理論によれば、何が経営者をしてなるべく能率的且つ効率的な経営をさせるかというと、その一つは株式市場から来るプレッシャーであるというものです。経営がうまくいかなければ株価が下がり、その下がり方によって、株式市場における時価総額が場合によっては資産よりも安くなる。そうなれば、その会社を買収できれば、その資産をより効果的に運用するか売るかによってかなり儲かることになります。日本の企業の資産を、より効率的に使わせる方法としてそういう敵対的買収がより簡単にできるように制度を整備するために、まず安定株主の持合い制度を解消しなければならないという理論になります。
二番目には、株式市場を通じての企業に対するMarket Disciplineを、強化するというものです。一般的な経済学者の理論によれば、何が経営者をしてなるべく能率的且つ効率的な経営をさせるかというと、その一つは株式市場から来るプレッシャーであるというものです。経営がうまくいかなければ株価が下がり、その下がり方によって、株式市場における時価総額が場合によっては資産よりも安くなる。そうなれば、その会社を買収できれば、その資産をより効果的に運用するか売るかによってかなり儲かることになります。日本の企業の資産を、より効率的に使わせる方法としてそういう敵対的買収がより簡単にできるように制度を整備するために、まず安定株主の持合い制度を解消しなければならないという理論になります。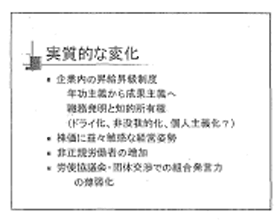 ただ年功主義から成果主義への移行については、実際には摑みにくいのです。抜擢昇級をするということを標榜する会社、たとえば日産のようにゴーンさんが抜擢昇級にはなったのですが、取締役になる年齢をみれば、結局のところ、それまで五十一歳が最低であったところが、最近、四十六、七歳になったという、マージン変化に留まっています。
ただ年功主義から成果主義への移行については、実際には摑みにくいのです。抜擢昇級をするということを標榜する会社、たとえば日産のようにゴーンさんが抜擢昇級にはなったのですが、取締役になる年齢をみれば、結局のところ、それまで五十一歳が最低であったところが、最近、四十六、七歳になったという、マージン変化に留まっています。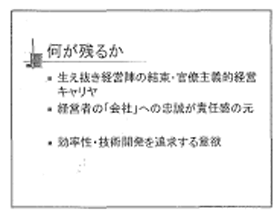
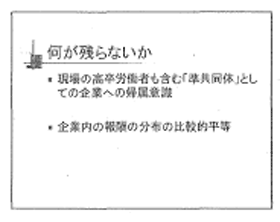
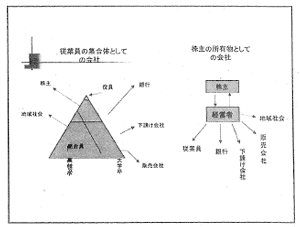 この図を作ったのは一九八〇年代、九〇年代に、イギリス人に日本の企業とアメリカ・イギリスの企業との違いを図で表そうとしたためです。一方は、株主の所有物としての会社。そしてもう一方は、従業員の集合体としての会社。左は日本の現実であって、右はアメリカ・イギリスの現実であると同時に、日本の商法の理想とする関係でもあります。しかし日本ではその商法の規定と実質は、かなり違っていたということです。
この図を作ったのは一九八〇年代、九〇年代に、イギリス人に日本の企業とアメリカ・イギリスの企業との違いを図で表そうとしたためです。一方は、株主の所有物としての会社。そしてもう一方は、従業員の集合体としての会社。左は日本の現実であって、右はアメリカ・イギリスの現実であると同時に、日本の商法の理想とする関係でもあります。しかし日本ではその商法の規定と実質は、かなり違っていたということです。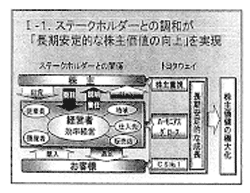 それは経営者と株主との関係は委託と説明責任の関係で、効率的な経営をするために色んなステークホルダーの福祉をも考えなければならないとしています。しかし、従業員はどうかというと、先ほどの図の右側のイギリス型と同じように、ステークホルダーの一つでしかないわけです。トヨタでさえも、やっぱりそういう思想に移ってきているということです。
それは経営者と株主との関係は委託と説明責任の関係で、効率的な経営をするために色んなステークホルダーの福祉をも考えなければならないとしています。しかし、従業員はどうかというと、先ほどの図の右側のイギリス型と同じように、ステークホルダーの一つでしかないわけです。トヨタでさえも、やっぱりそういう思想に移ってきているということです。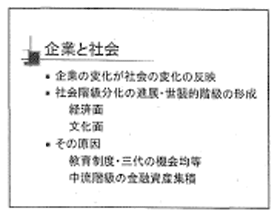 そして、特に九〇年代に入ると貧富の差も開いて、それが経済面ばかりではなくて、文化面における階級差がますます見えてきたのではないかと思います。一般労働者が見るテレビや読む新聞と、都会のサラリーマン・インテリ・経営者の見たり読んだりするものが、ますます違ってきているのではないでしょうか。
そして、特に九〇年代に入ると貧富の差も開いて、それが経済面ばかりではなくて、文化面における階級差がますます見えてきたのではないかと思います。一般労働者が見るテレビや読む新聞と、都会のサラリーマン・インテリ・経営者の見たり読んだりするものが、ますます違ってきているのではないでしょうか。