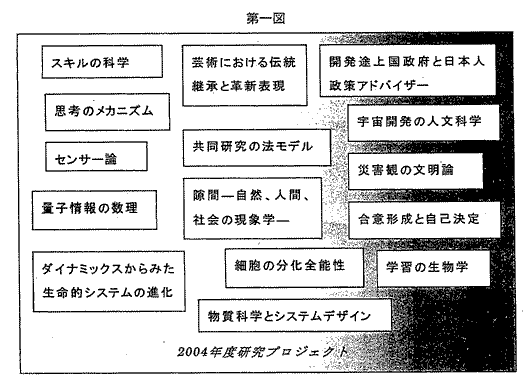学士会アーカイブス
国際高等研究所という試み 金森 順次郎 No.849(平成16年11月)
1、はじめに
2、研究事業の概略 事業の第1は毎年10人程度の各界の優れた学者をフェローとして国内外から招聘し、1年間の期限でオフィスと研究費を提供して、自由な研究活動を行っていただくプログラムである。1998年から2003年までに、海外から15名、国内から43名を招聘している。第2の事業は、特定の題目についての研究プロジェクトであって、比較的少人数での長時間の討論を主体とした研究会を行う。第一図に2004年度に実施しているプロジェクトをその略称で示している。図の左側は人の心、右側は社会システム、下側は自然をあらわし、各プロジェクトの配置はそのカバーする分野を大雑把に表現しているが、二次元的配置で表現し切れない関係があることは当然のこととご理解いただきたい。現代社会の提起する多様な問題について、人類社会の調和のとれた発展に貢献する基礎的研究を行うために、各プロジェクトのネットワークで対処しようというのが基本的な考えである。プロジェクトの大半は所外の方々が主宰されている。スペシャリスト養成事業と総称する第3の事業は、新しい課題について、原則として若手の受講生を集めて、各地から専門家を講師に招き可能ならば合宿スタイルで行うスクールないしはワークショップである。受講者が、新しい知識の獲得と同時に、所属組織を超えて親しくなり、我が国の将来を担うスペシャリスト集団を形成することを目指している。前副所長松原謙一阪大名誉教授が主宰され、2001年と2002年に行った「情報生物学適塾」(受講生20人、約3週間、講師は毎日交代)がこの事業の最初である。その後他分野で同趣旨のワークショップを開いている。学術情報に関する第4の事業は、研究成果の出版が第1の目的であるが、後に紹介する北川副所長が提唱されたコピーマートの概念に基づいて新しい学術情報システムを構築する実験的研究でもある。
その他特定題目についてのフォーラム、国際会議もかなり頻繁に開いていて、研究会の開催延日数は年間150日にもなる。また、公開講演会、親子サイエンススクール等を主宰して学術情報を社会に公開することも行っている。研究事業の費用の大半は現在政府からの科学研究費補助金に頼っている。詳細はホームページ (http://www.iias.or.jp/) をご覧いただきたい。
3、自由とコミュニティ 我々のフェローの制度も、束縛のない環境で、自由な発想のもとに長期的な展望を考えていただくという点では同様であるが、給与を支給できないという財政的制約と、また他に勤務をもっている場合に勤務先から一時離れる制度がないという現状から、NIASのように滞在義務を課することはできない。このためだけではないが、コミュニティ形成という面では、第2の事業である研究プロジェクトの方が大きい比重をもっている。各研究プロジェクトは、大学その他の組織のしがらみから離れて、参加者個人の思考が伸び伸びと展開され、相互のディスカッションが相補的相乗的な役割を演じるコミュニティを形成することを心がけている。このようなコミュニティから長期的には新しい概念やアイデアが創造されることを期待するが、目先の成果を云々しないことが我々の事業の特徴である。 このような性格のプロジェクトの評価が分野によって必ずしも一致していないことについて個人的な感想を述べたい。我が国の自然科学分野では、数学と理論物理学の分野を除いて、実験やフィールドワークが研究であって、概念形成ないし追求はその前段階と見られる傾向が底流として現存している。これが現代に及ぼしている影響として、日本人は概念形成が得意でないとしたり、新しい概念が知的財産として尊重されるべきものという認識がやや希薄であると感じさせられることがある。一方人文社会科学については、研究成果は個々の研究者が完成した著作であると理解されていて、その根底にあるアイデア自体が個人の知的財産であるという認識が足りない場合があるということを、高等研究所での耳学問として学んだ。高等研での研究プロジェクト運営に当たっては、自由な討論と同時にお互いのアイデアを尊重するコミュニティを形成することに大きい意義を感じている次第である。 このような背景のもとで、私が代表者を務める第一図記載の「物質科学とシステムデザイン」と題するプロジェクトで、新しい産学連携ないしは共同研究のルールが生まれた。このプロジェクトは、最近我が国を中心として開発が進められている新物質をエレクトロニクスに利用し、省資源、省エネルギー、高速化等で現在の技術が直面する壁を乗り越えるアイデアを創造することを目指している。大学、エレクトロニクス関係の企業やその他の研究機関から80名以上の研究者の参加を得て、年に6、7回以上の研究会を開き、基礎研究者とシステムデザイン等の生産技術研究者、また大学の研究者と企業の研究者等の異分野間の対話を実現している。その際、公表していることだけに話を限定せずに将来の夢を腹蔵なく討論するために、知的財産についての取りきめをあらかじめ行っておく必要に迫られた。知的財産に関する法学研究のパイオニアの1人である北川副所長は、我々の要請にこたえて参加され、新しい考えに基づく規約(産学連携高等研モデル)を提案された。従来から行われている産学連携共同研究は、組織間の契約に基づいている。この場合、個人は所属組織の知的財産に関するルールに常に制約され、組織間の壁のために共同研究に参加する研究者間での自由な討論を行うことにはいろいろな困難がある。また知的財産の帰属は常に組織の間の話し合いで決まることになる。北川氏が提案された新しい法モデルでは、個々の研究者が集まって1つの組合(パートナーシップ、研究機構)を作る。研究機構に登録されたメンバーは、研究会等で得られた情報については守秘義務がある。共同研究から生れた知的財産はこの研究機構内の「知的財産評価委員会」でまずそれがメンバーの誰に帰属するかを決める。このようにして帰属が決まった知的財産については、その後はその所有者が属する組織のルールに従って取り扱われる。高等研は研究機構を主宰するが、一切権利を主張しない。この考えを具体化した規約(研究機構規約、知的財産規程、研究会記録管理規程の3つからなる)が参加者の同意を得て発効し、実行されている。詳細は文末の文献に譲るが、このモデルは、各研究者がその所属する組織での知的、財産についてのルールに従いつつ、共同研究においては自由な議論を行うことを可能にすることを発想の基底とし、そのための必要な最小限度の規約を設定しているのが特徴である。 北川副所長は以前に情報流通に関して「コピーマート」という概念を提唱された。 http://www.copymart.gr.jp/ からその説明を少し変更して引用すると(変更個所は傍線で示す)、コピーマートとは『ディジタルコンテンツの流通に関する契約モデルであり、権利者があらかじめそのコンテンツの利用条件を決めた権利データを登録し、その条件が満たされればコンテンツのコピーが広く提供される取引市場のことを指す。』である。その主宰者が、情報の自由な流通と知的財産を保護尊重するという場を確保するという意味で、この概念を一般的にとらえれば、前記産学連携高等研モデルにも、様々な形での高等研の自由とコミュニティ形成での役割の具体化にも対応する。この概念は現在北川副所長とその協力者によって高等研の学術出版事業、自然科学、人文科学の各種学術情報の利用方法開発等で具体化されつつある。
4、学際と国際 最後にInternationalについて述べたい。高等研では、一方で国際あるいは異文化の交流・衝突・誤解を主テーマとしてその意味と実態を掘り下げるために中川副所長を中心として幾つかのプロジェクトを実施してきた。他方、どのプロジェクトでも、その議論が国際的に共有ないしは評価されることを必要条件としている。高等研究所に「国際」を冠する理由はこの努力を象徴するためであると解釈している。事実使用言語が日本語でないという意味の国際的な研究会もかなりの頻度で行われている。 紙面の関係でやや抽象的な紹介に終始したが、現状だけが国際高等研究所の可能性のすべてではない。ご理解とさらなる進化のためのご批判を切望して終わりたい。 〔文献〕北川善太郎、高等研研究報告書205「産学連携高等研モデル」、国際高等研究所2003年
(国際高等研究所長・大阪大学名誉教授・阪大・理博・理・昭28)
|
||||