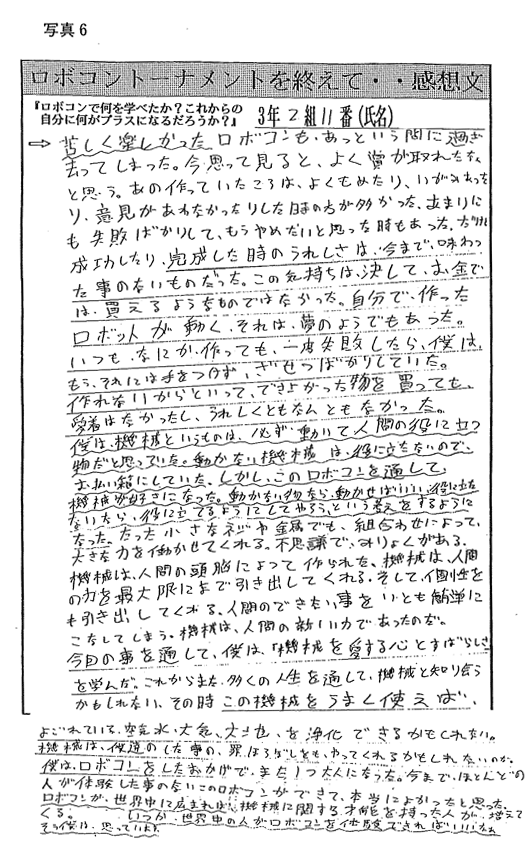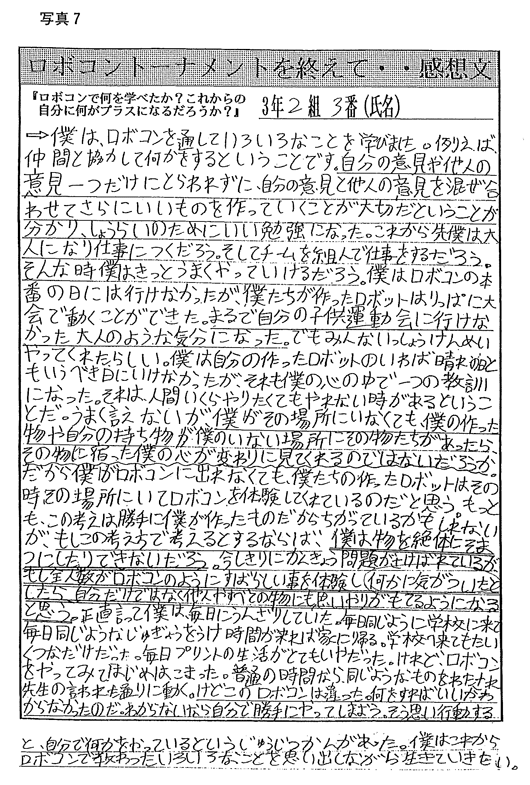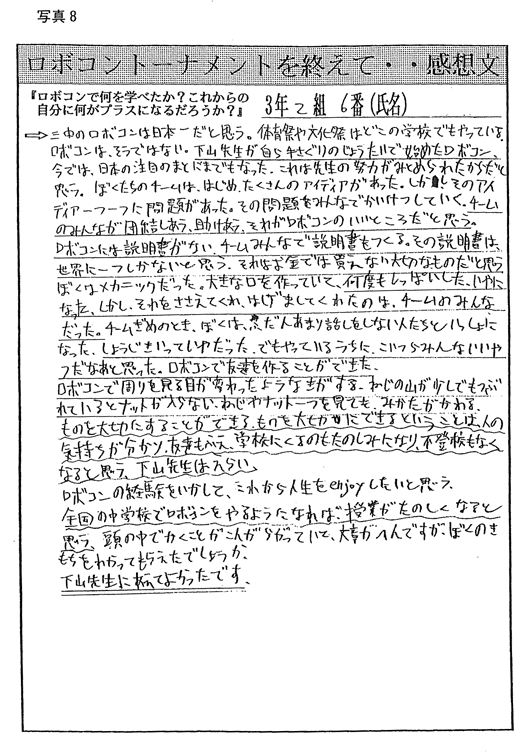学士会アーカイブス
ロボットコンテストの教育的意義 森 政弘 No.833(平成13年10月)
*——————————–* きょうは、今私が力を入れております、ロボットコンテスト(略してロボコン)の教育的な意義についてお話しさせていただきたいと思います。 私は昭和二十五年に名古屋大学工学部電気学科を卒業して、主に電気の分野を専門にしておりましたが、二十六年から研究を自動制御(オートマチック・コントロール)に変え、今日まできました。その研究の一環として昭和三十四年からは“手”の研究を始めました。これは仲間たちとは発想が違っていたのですが、当時、自動化と言いますと、すぐにベルトコンベアーという風潮がありました。私は、日本は工業立国ということはわかるが、我が国の工業は器用な手先で成り立っているのだから、まずは“手”の研究をしなければ自動化にならないのではないかと思い、ベルトコンベアーや自動機械に先立って“手”の研究を始めたわけです。しかし、“手”は手だけでは存在しえませんで、腕がいります。腕は腕だけではありえないので胴体がいるというようなことで、結局はロボットにいきついてしまいました。 振り返ってみますと、早稲田大学に私より少し年上の加藤一郎先生という方がおられまして、その加藤先生と私とで日本のロボット工学をリードしてきたところがありました。加藤先生は惜しくも若くして亡くなられ、結局、いまでは私がロボットの草分けということになっております。 ご承知のように、ロボット関連の記事が新聞や雑誌に載らない日はないほど、昨今はロボットブームと言っていいかと思います。私たちのような専門のものでも、ロボット技術がどこまで進むかについては予測を許しません。実現は二十年も先だと言っていたのが、もう十年も先には実現できてしまうといった予測ばかりが先走って、いまは大変騒がしい世の中であります。しかし、ロボットは大きな資金や設備がいりますし、大規模なコンピュータもいります。私のような定年退職した者には手が出ませんので、今はロボットそのことよりも、むしろロボットを教育に応用することに力を入れております。 これはひょんな事から始まりました。昭和六十二年一月の學士會会報(第七七四号)にも「教育活性化のひとつの試み─乾電池アイデア競技」という小論文を載せていただき、そこにも書きましたが、ちょうど今から二十年前の昭和五十六年頃、私は東京工業大学で教鞭をとっておりましたが、学生たちの顔を見ると、目に輝きがなく顔がトローンとしているのです。私は第八高等学校出身で、八高の寮歌に「望みにたぎる若き頬を云々」という歌詞がありますが、青年の顔から望みが消えて、目に輝きがなくなったら危険です。 私のようなジェネレーションの学生時代は、戦争が全てを壊してしまった後ですから、やることだらけで何をしなければならないかを考えるまでもなかったのです。ですから学生生活は希望に輝いていたと思います。悪いことに、やるべきことを私たちがみんなやってしまったものですから、今の若者に「大学で、君は何をやりたいのだ」と問い詰めてみても、「さあ、わかりません」と言うわけです。大学院生でさえも「人生の目的は?」ときくと「わかりません」と答える。私は、今の教育を変えなければ日本はだめになる、といった危機意識をもちました。 しかし、危機意識をもつだけでは事は解決しませんので、何かをしなければなりません。でもどうしていいかわからない。私の深層心理の中に危機感がどんどん蓄積していきます。やがて、その危機意識を夢に見るようになりました。夢に見るぐらいのときに、何か外から刺激が入ると心の中で熟成してきたものが爆発して、意識の上に出てまいります。禅哲学者の鈴木大拙先生が著された禅の本などを読みますと、禅僧が悟る瞬間とは、心の中で悩みに悩んで考え抜いて、坐禅し抜いた挙げ句、日常の作務の中で石ころに箒がぶつかって見性した、あるいは警策で叩かれた瞬間に悟ったという話が出てまいります。それと同じパターンで、心の奥底で熟成され、深層心理の中にグッと収めていたものが、昼間は忘れているけれども夜には夢に出てくるといった状況でした。そして八月のある日、私は熱い風呂に入りました。面白いもので、風呂でいろいろとアイデアを出す人がいますが、私もいろいろなアイデアが出るのは、風呂に入っているときがいちばん多いのです。ポッと出ます。ただし、その前によく熟成させておく必要がありますよ。 どんなアイデアかというと、実にばかばかしいものですが、単一乾電池、つまり懐中電灯の乾電池一個だけのエネルギーで、人間を乗せて走らせることのできる車ができないかと思ったのです。乾電池でモーターを回して、回転数を歯車で落としていくと、回転数が二分の一になれば回転力は二倍になります。十分の一に落とせば十倍になり、千分の一に落とせば千倍になりますから、さらに回転数を落とせば、人間ひとりを乗せた車を動かせるぐらいの回転力は出るだろう。百メートルぐらいの距離を時計の短針ほどのスピード、つまり見ていても動くか動かないかぐらいのスピードで一日かかって行けと言うのなら、単一乾電池一個でも人間を運べるのではないかと思ったのです。しかし一方で、そんなにたくさんの歯車や軸受を使ったら、摩擦か何かで動かなくなってしまうのではないかということも思いました。結局、やってみなければわかりません。 *——————————–* そこで九月の新学期が始まって、学科会議で諮りましたら、「面白いからやろう」と言う先生が出てきました。しかしすでにカリキュラムがいっぱいで、そういうことをやっている暇がありません。 話が少し横にそれますが、私が学生の頃でも一日は二十四時間、これだけ技術が進んだ今でも一日は二十四時間で、授業時間にも限りがあります。同じ授業時間で我々が習ったことと、今の学生が習うのとでは中身は全然違いますし量も違う。いったいどうなっているのかと思いますが、今から二十年前でもカリキュラムはびっしりでしたから、その中でどうやるか。製図の時間がありまして、製図には機械工学設計製図と制御工学設計製図の二つがありました。これからの製図は CAD や CAM といったコンピュータで製図する時代になるから、基本的な事項だけわかればいいということで、機械工学設計製図は残して制御工学設計製図の時間を乾電池の競争にあてたのです。ちょうどそれが三年次の授業でしたので三年生にさせようということになり、十月から始まって二月に終わる後期の授業に取り入れました。 一クラス三十四人の学生を四班に分けて八人の組と九人組をつくりました。各班に指導の先生をひとりずつ付け、工面して小さい部屋もひとつずつ与えました。予算は五万円、ただし国立大学は先生が現金を扱ってはいけないことになっていますので、伝票をきって事務が部品を調達するわけですが、部品を買うことも練習になりますから、調達も学生にまかせることにしました。さて、調達資金をどうするか。「指導教官は運が悪いと思ってポケットマネーを五万円ずつ出せ」ということにして、その現金を学生に渡して、とにかく乾電池一個で人間が乗って走る車を作れという、一種の限界への挑戦とも言える課題を出しました。 そしたら学生の顔を変わりました。「先生、走りますか」とききます。指導教官もわからない。先生が「わからない」と言うと学生は俄然やる気を起こしました。普通の授業では先生は正解を知っています。それを学生に隠しておいて答えを言わせて、正解だ、間違っているというわけで、こういった汚い教え方をしてはいかんということを私はそこで覚えました。学生は世界中の誰も知らないことには挑戦してみようという気が起きるようで、「やれ! やれ!」と揺さぶりをかけるだけで、一人ひとりの役割分担のようなことは、こちらは決めませんでした。 そうしましたら、人間というのは面白いもので、五本の指に一本一本役割があるがごとくに、ちょうどその八人の学生の特徴を活かして、リーダーシップをとる学生はリーダーになって采配を振るいだす、計算好きはコンピュータにプログラムを入れて、日本中から小型モーターのカタログを山と取り寄せ、それをコンピュータに入力して、どのモーターを使うのがいちばんいいかと研究する、秋葉原あたりに行ってものを買ってくることが好きで、値切ることの上手な学生はそれをやりだすというようなことで、ひとりでに役割分担が決まってゆきました。 そうすると、どういうわけかこちらもハッスルしてきて夢中になってきました。大学のことですから、何時に追い返さなければならないということはありませんので付き合っていますが、学生はだいたい夜になると一所懸命やるのです。夜の九時ごろに「アッ」とか言っているので、「何が、アッだ」ときけば、家庭教師のアルバイトに行くのを忘れていたと言います。じゃあ、というわけで、九時から教えに出かけて十時半ごろ、また研究室に戻ってくる。そんな学生に付き合わされて結構大変でしたが、教官お学生も熱が上がってきました。 当時、学園には文章で言うと叙事文と命令文しかありませんでした。例えば、「オームの法則はこうですよ」というのは叙事文です。「ああせい」「ここせい」というは命令文です。この二つしかない。感嘆文が抜けていました。つまり学園に感動がない。授業を受けても感動しない。何とかの定理をきいても、「あぁ、いいなあ」とか、「あぁ、美しいな、すばらしいな」といった感動がない。しだいにしらけてきて、顔をポカンとしてくる。ところが、それがだんだんと変わってきたのです。 そして二、三ヵ月たった頃、ともかくもアイデアが出てきました。初めはとても走るまいと思っていましたので、大学の屋内に研ぎ出しのピカピカの廊下が直線距離で八十メートルありましたので、そこを走らせてみることにしました。車まで旋盤で削っていたらとても五万円ではできませんから、学生たちは古自転車を改造して使うことにしました。駅前にたくさん古自転車が乗り捨ててあって、それを警察が持ってゆきますから、警察に行けば無料でくれるのではないかと考え、学生たちは警察に押し寄せました。そしたら警察曰く、「お前たち、古物商の鑑札はあるか」と言うのです。古物商の鑑札があるともらえるらしいのですが、授業のために古物商の鑑札をとってはいられませんので、それでは古物商に行けばあるだろうということで、今度は古物商へ押しかけました。そのために我が学科の廊下はもらってきた古自転車の山になってしまいました。 それを改造して、タイヤを外して金属リムのままで三輪車を作りました。マブチのおもちゃ用モーターの中で最大のものを使用して、単一乾電池一個、つまり電圧一・五ボルトで体重約六十キロの人間一人が乗ると、研ぎ出しの廊下の上では、四つの班のどの車もが、だいたい歩く程度のスピードで動いたのです。これでは競技としてつまらないから、外でやってみようということになりました。普通に言えば平らであるアスファルト舗装の駐車場がありまして、直線距離で六十メートルがとれました。しかし実際にそこでやってみたら、スタートさえできないのです。テカテカに磨いた屋内では小さい埃があっても問題はないのですが、屋外では直径一ミリの砂粒があっても、その一ミリの砂粒を乗り越えるだけの回転数が出ないといった、非常に面白い結果が出てきました。体重六十キロプラス車の重さで百キロ弱あると思いますが、それを一ミリ上げるだけの回転数が出ない。さあ、面白くなってきた、これならば競技になるということになりました。 そこで条件を変えて、単一乾電池を二個にしました。「スタート十分前に新品の電池を渡すから、何らかの工夫をして、単一乾電池二個のエネルギーを別の恰好のエネルギーに変えなさい。運動のエネルギーでも位置のエネルギーでも、どのようなエネルギーでもよろしい。その蓄えたエネルギーを一斉に吐き出させて走り出すこと」と決めました。そうしたら、いろいろな工夫が出てまいりました。 第一班は、ロープを幾重にもかけ牽引力を高めました (図 1 ) 。モーターを回してロープを巻くと、リンクが人字型に狭まっていって、乗っている人間が上に上がってゆきます。つまり人間のポテンシャルエネルギーという恰好で、単一乾電池二個のエネルギーを変えて蓄える。その蓄えている間に車が動き出さないように、タイヤを押さえる係が一人いて、その係が一気にタイヤを放すと、人間が下がろうとしますから、人字型のリンクが開こうとする。それでロープが車輪を回して動き出すという原理です。これは六十メートルを二十一秒ぐらいで走りました。
第二班は、電気エネルギーを別の電気エネルギーに変えました( 図 2 )。このごろのコンピュータは大丈夫ですが、以前は停電すると入力したデータが消えてしまったものです。それを防止するためのバックアップ用の大容量コンデンサー(スーパーコンデンサー)が、その頃はじめて製造されました。普通、コンデンサーの単位はマイクロファラッドで呼ばれ、大きなものなら一万マイクロファラッド、あるいは普通の容量ならばコンマ一マイクロファラッドとかです。ところがマイクロの付かない単なる(つまり百万倍の)ファラッドという単位のコンデンサーが製造されるようになり、NECから一ファラッドのものが、またナショナルから三・三ファラッドのものが出ました。それに電気エネルギーを溜めようということになったのです。 電気を溜めるというと、蓄電池に溜めればいいではないかという発想になります。たとえばニッカドの蓄電池に溜める方法がありますが、この蓄電池は溜まることは溜まりますが、ゼロになったときの立証がうまくゆかず、いつまでたってもダラダラと電気が出てきます。放電しつくしたかと思って一、二分待っているとまた出てきて、完全にカラになることが立証できません。これでは競技にならない。 そこで彼らはコンデンサーに目を付けたのでした。中古の自転車に付けた小さいお菓子箱の中に三・三ファラッドのコンデンサー(蓄電器)を三十個並列にしました。なんと九十九ファラッドになります。当時としては、世界最大の容量のコンデンサーだったと思います。蓄電器というだけあって、なるほど電気は溜まるのだなと、私は初めて実感しました。普通のマイクロファラッド単位のコンデンサーは充電にしても放電にしても、パチンと瞬時に終わってしまうのです。ところが九十九ファラッドですと、充電するだけでも十何分もかかりますし、放電させたらモーターがビュンビュン回るという代物でした。要するに、単一乾電池二個を直列にして、DC – DCコンバーターという電子回路を作り、電圧を十二ボルトに上げ、これに蓄える方式だったのです。もう少し細かく言いますと、ギアチェンジをするメカニズムが付いており、モーターから出たシャフトをタイヤに押しつけてリムドライブで走るのですが、ギアチェンジの最良の瞬間を示すメーターも付けたのです。 第三班は実に変わっていました( 図 3 )。最初に「道路に仕掛をしてはいけない」という規則がもうけてあったのです。たとえば、道路にモーターを置いて紐で車を引っ張るようなことはしてはいけないといったことです。「スタート線よりも手前ならばいいですか」とききますから、「それは読んだ通りだ」と答えました。こういう競技では規則に触れるスレスレのことをすると勝つのです。第三班は規則スレスレで、スタート線の手前に仕掛をしている。彼らは三万円でベニヤ板を買ってきてスロープを作りました。そしてウインチを作り、自転車のタイヤを外して三輪車を作って、ワイヤーで十分間かけて引き上げます。そして、用意ドンでニッパーで一気にワイヤーを切ると、車がサーッと滑り下りるという仕掛で、これはすごく速くて、六十メーターを十二秒で走って一位になりました。
図 4 は第四班の装置です。この班はうまくリーダーシップをとる男がいなかったので、烏合の衆になりました。十月から始めたのにもかかわらず、翌年の一月になっても案がまとまらない。部屋に集まるとマンガの本を読んでいるという状況でしたが、放っておきました。競技会は二月の初めですから、一月も末になると、いよいよお尻に火がついてきて、一週間ぐらいで何とかでっちあげてきました。 石油の空き缶をモーターで引っ張り上げる。その空き缶の中にはトランスやモーターの古手など、重いものをたくさん入れたのでした。それを一気に下ろすと、ロープ仕掛でフッシャーの棒で車を押す。しかも巻き上げただけでは乾電池も残っているので、巻き上げたときの電池とモーターを走り出す寸前に、前輪車へ付け代えて、リムドライブで走らせるという方法です。やはりさぼっていただけのことがあって大失敗しまして、ゴールから三メートルほど行ったところで止まってしまいました。しかし、十数秒見守るうちに、ゆっくりと蝸牛が進むがごとくに動き出したのです。それで、敵見方を超えて、みんなが集まってヤンヤヤンヤの声援をかけ、七分ぐらいかかってゴールしました。これで本当に感動が学園に蘇りました。みんなの顔が笑顔でウワッと燃えて、後で学生にきくと、大学に入ってあんなに面白かったことはなかったというんですね。 それからは学生たちの態度がさらに変わりました。これ以降、こうした授業を何らかの恰好で続けることになりました。ようやく学園に感嘆文を取り戻すことができました。 いま紹介した四種類の車は、それぞれ原理も恰好も違うことに気づかれたと思いますが、本当に面白いものが出ました。人のものを見ずに、参考にせずに作れば必ず違ったものが出てきます。同じものになるのは、まず参考のために人のものを見るからです。ですから、創造的にものごとを運ぼうと思えば、調査などしてはいけません。とにかくまず自分で作って、できた後で人のものを見ることをお勧めします。 翌年には、乾電池の電圧を倍に上げるのに、DC – DCコンバーターなどという、ハイテクの常識は使いませんでした。ご承知と思いますが、昔は電気の電圧を上げることは、電気が交流で変圧器によってだけしかできませんでした。しかしトランジスターやサイリスターが登場してからは、直流でも電圧が変えられるようになりました。直流を一度発振させて交流に直して、トランスで電圧を変えて、さらにそれを整流してという具合にして、直流電圧をさらに高い直流電圧に変えることができるようになったのです。それがDC – DCコンバーターです。ところが二年目はDC – DCコンバーターも使わずに電圧を上げたのです。 どうしたかというと、乾電池を貰うときに、学生達は金鋸と柱をV字に切ったVブロックを用意して持っていました。そして、電池を渡すや否や、いきなり乾電池を真っ二つに輪切りにし出したのです。そうすると一個の電池が二個になります。金具を付けると二個の電池が四個になって、あっという間に六ボルトが出ました。私はこの発想には感動しましたね。ノーベル賞級の発想です。乾電池を切って電圧を倍にすることは学校では教えませんので、発想においては日本人も劣りませんね。 *——————————–* アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)の機械系学科では、小さいロボットを作って対抗戦をしているという情報をNHKがきき出し、それを取材して放映しました。そのときにNHKが私にその感想をききにきました。私は「あれも面白いが、あんなことならうちでもやっているよ」と言ったのです。東京工業大学でもMITでもやっているのなら、両校一緒に競争したらどうだろうという話が持ち上がり、両校合同でロボットの競技会を開催することになったのです。しかし、さすがに大MITで、手続きに手間取るのです。ところが東工大は一学科の中で競技しているだけですから、「やろう」と言えば、それで決まってしまいます。結局、MITの承諾が出るのに三年もかかってしまい、NHKはそれを待ちきれずに、大学のほうは交渉中のままで、その前に高等専門学校でやりましょうということになりました。 対象を大学の工学部や工業高等学校にしなかった理由は、単に数の問題です。高等専門学校は全国で六十二校しかありません。ところが大学や工業高校になると、手のつけようのないほどたくさんありますので、一日でトーナメント競技を終えることはできません。最初の年は、先ほどの乾電池競争と同じことをしましたが、二年目からはロボットコンテストになりました。 ロボットと言うと、このごろは二足歩行のロボットも登場してきましたし、癒しのロボットや犬のようなもの、会話ができるもの、産業用ロボットなどさまざまですが、「ロボットとは何か」といった定義は非常にむつかしいのです。山にたとえると、新幹線に乗って京都へ入るとき、手前の彦根あたりの両側に山が饅頭型にポコン、ポコンと見えます。ああいう山はここから内側が山で、外側は平野だと、はっきり線が引けますが、富士山の裾野ですと、どこからが平野でどこからが山かはよくわかりません。行政的に線を引くことは可能ですが、実際にどこからが山なのか、水準器を当てて測ってみても、しようのないことです。ロボットという概念も富士山型をしていまして、頂上のほうは明らかに「これはロボットだ」と言えますが、裾野のほうはロボットなのかロボットでないのか明確に区別できないのです。たとえば、自動販売機でこの頃しゃべるものがありますが、ロボットと言えばロボット、そうでもないと言えばそうでもない。 もちろん定義がないことはありません。認識機能をもち、自動的に動き、しかも、ただ単に首が動いたり手が動いたりするだけでなく、ロコモーションといって体全体が移動して進む。さらにマニュピレーターをもっていて、それに情報処理機能が入る、そういうものを学界ではロボットと定義しています。しかし一般的には定義しにくく、ロボットコンテストのロボットは、スレスレのところの、ロボットに入るか入らないか程度のもので、リモートコントロールのものも多いのです。 さて、実際にロボコンを始めましたら、いろいろなアイデアが出てきました。NHKの番組には、たとえば「新日本人の質問」といった、正解はひとつで、あとは嘘の回答だといったような知識番組が多い。つまり、このような番組は正解を知っているかどうかに価値があり、ユニークなことを言うのが価値ではないわけです。私は知識の番組だけではなくて、知恵の番組がいるよ、知識と知恵は違うものですよ、と言い続けてきました。「知識を転じて知恵を得よ」と仏教でも教えています。人間は知恵の動物で、知識の動物とは言わない。しかも、「知識は得る」と言うように外から中に向いて入る。「知恵は湧き出す」、つまり中から外に向いて出る。矢の向きが逆なのです。ですから、創造性を豊かにするような知恵の番組を作るように進言してきたのですが、いろいろと試みてもうまくいかなかったのです。しかしこのロボコンで、ようやく知恵の番組のひとつができたように思います。 何回も放映されましたので、ご覧いただいた方もあると思います。NHKの「アイデア対決・ロボットコンテスト」は、大きくわけて今申しました高等専門学校部門と大学部門とがあります。大学部門にはMITと東工大から始まった国際部門と、その他に国内部門があります。国際部門は現在、七大学になりまして、日、英、米、独、仏、韓国、ブラジルが参加しています。このコンテストは、オリンピックのように勝った国の国旗を掲げるということはせずに、各国からひとりずつ選出して混成チームを作り、その混成チーム同士で競技をすることになっています。初め、MITと東工大で始めようとしたときに、日米対抗は嫌だとMITが言い出しました。考えてみれば、貿易摩擦問題などデリケートなときに、どちらが負けても問題が残りますから、アメリカからひとり、日本からひとり選出して一チームを作ることにしました。それが基本になっていて、現在まで進んできています。 ところで、中学校に技術・家庭科という授業があります。中学校の技術科の授業は、一般的に言って、何ともしようのないところがあります。たとえば、一石のトランジスターラジオを組み立てる、あるいは蛍光灯の組み立てをするといった程度なのです。そのためのキットが売り出されていまして、それを買って与える。開封すると説明書が入っていて、1と1´を配線しなさい。2と2´をつなぎなさい、といった類のことが書かれています。その通りに配線して、電池を入れる。うまくいかなければ配線が間違っていることになるから、ここに直しなさい。これが技術科の授業の実態です。しかも、入学試験に出るような英語や国語や数学などは大事にされますが、技術はむしろ邪魔者扱いで隅っこに押しやられている感じがいたします。これでは技術科担当の先生も教えていても面白くない。先生に熱が入らないから、生徒のほうもやる気がない。中学校自体も学級崩壊などと大騒ぎしている。 ところが、自分は一所懸命やろうとしているのに、その技術科には重きが置かれていないということで、悩んでおられる何人かの先生がいました。その先生がNHKの「アイデア対決・ロボットコンテスト」をご覧になって、「よし、これからはロボコンだ」とハッスルされたのでした。そして全国の中学校の授業にロボコンの採用があちこちで始まりました。全国に一万二千五百校ほどの中学校がありますが、今ではそのうちの約二千校で採用されています。 *——————————–*
この学校は今年で第十回目のロボットコンテストを迎えました。 写真1 は第八回のときの準備風景です。プラスチックのボールが青と赤と置いてあります。そのボールが縦に三つ入るぐらいのプラスチック性の透明の筒が九本立っています。これは「三次元三目並べ」という競技で、横でも縦でも斜めでもいいから同じ色の玉が三つ直線に揃えば一点入るというゲームです。生徒は二年の選択と三年の必修でやります。三年生の年齢は十五歳です。十五歳の子供たちは、十一月にこんなロボットが作りたいという夢のようなことから始めて、二月の中旬までかかって実際に仕上げてゆきます。どのロボットも結構大きいもので電気冷蔵庫ほどのスケールがあります。
ロボットを作るために技術室へ移動するときは、彼らは走ってゆきます。目の色も違います。それだけ面白いのです。「時間がきたからやめなさい」と言ってもやめない。「帰れ」と言っても帰らないので、「登校拒否を下校拒否に変えるロボットコンテスト」という標語ができたほどです。大学生ですと徹夜させてもいいのですが、中学生ですから七時で追い返します。すると「翌朝何時から来ていいですか」と言いますから、「六時半だよ」と答えると、雪が降っているのにも拘わらず、早朝六時から来て待っているという熱の入り方です。 さて、いよいよロボット作りが始まると、技術室は足の踏み場もないほどの戦場と化します。まことに多彩なロボットができあがってきます。それぞれ本当にアイデアに満ちていて、よくここまでのものを子供たちが作るなあと、私は感心いたしました。
こういった失敗の連続、難関を乗り越えてはトライ・アンド・エラーで作っていくのですが、夢中でもの作りをしますと、三昧の境地に入ります。仏教では坐禅の三昧を王三昧と言ったり、念仏三昧と言ったりします。三昧は我を忘れて対象そのものになるところにポイントがあるのですが、生徒たちはものを作るときに、我を忘れ時間を忘れて、まさに三昧の境地に入っています。そのことは感想文を読むとよくわかります( 写真6 )。
この感想文は、国語の授業と違って、「漢字の間違いなどは構わずに、四十五分で書きたいだけ書くように」と言って書かせたものですから、改行もしていません。このはじめの「苦しく楽しかった」というところがいいですね。苦しいだけでもだめ、楽しいだけでもだめ、正反対のものがひとつにならないと、ものごとはうまくいかない。これは仏教の教えです。ところが、この感想文を書いた出貝君には、ちゃんとひとりでに「苦しく楽しかった」ということがわかっています。事実、苦しみを乗り越えていかないと楽しくないわけで、登山でも喘ぎ喘ぎ登るところがいいのであって、ヘリコプターで登ったのでは楽しさは半減してしまいます。この感想文にはそれがよく出ています。私はそこにアンダーラインを引いておきました。 「出来上がったものを買っても、愛着はなかったし嬉しくも何ともなかった」という感想をもったことは、これは今日の大問題だと私は思います。今日は作るための部品も売っていません。完成品しか手に入らないのです。どんなに精緻な完成品でも、それを買ってもらった子供って嬉しくないのです。買ってもらわないよりは嬉しいでしょうが、自分で完成させたといった嬉しい手応えが得られないのです。それがこの作文で厳しく問われています。 「役に立たないなら役に立つようにしてやろう」と、いいことを言っていますね。仏教では、本来役に立たないものはこの世の中にないのだそうでして、本当に役に立たないと思ったときは、そう思う頭が役に立たない。つまり、すべては役に立つということですが、それを裏書きしているような文章です。ある意味で、これは仏心です。ロボコンを通して、生徒たちの心眼が開かれていくのですね。 この生徒は紙面からはみ出してまで書いています。国語の作文の時間に、誰もこれだけの量を書かないと、国語の先生は驚いていました。ところがこちらは体験談ですから書きたくてしかたがない。なかなかしっかりしたことを十五歳の少年が書いてくれています。 これもりっぱな感想文です( 写真7 )。四人一チームでロボットを作っているのですが、勝ちたい一心で、初めは必ず一人ひとりの我が出てきて自分の意見を通そうとしますから喧嘩になります。そこに先生が割って入って口に出したりするのはいけません。自分たち四人だけの力で喧嘩を乗り越えて、しかも二行目以降にある「自分の意見や他人の意見一つにとらわれずに、自分の意見と他人の意見を混ぜ合わせて、さらにいいものを作っていくことが大切」であるということがわかってきて、それを実行することによって自信がついてきます。これが何よりいい教育になっています。大人が恥ずかしくなるようなことを彼らは言ってくれています。
この作文を書いた生徒は、実は本番の日が彼のお父さんのお葬式だったのです。競技の日には四人でやるべきところを、この組は彼が休んだので三人で行いました。一所懸命に物を作ると、物に心が乗り移るのです。それで、こういう気持ちが出てくるのですね。単なる冷えた機械ではなく、ロボットは我が分身なのです。自分の分身がそこで動くわけですから、「まるで自分の子供の運動会に行けなかった大人のような気分になった」と書いています。 「その物に宿った僕の心が代わりに見てくれるのではないだろうか」といったことは、まさに技術者精神と言いますか、技術者は自分が作った物に心が乗り移らないようではだめです。「カワリ」という字が違っていますが、そういうことはここでは問いません。唯物論的には問題があるかもしれないが、観念論的にはなかなか正しいことを言っています。彼は「間違っているかもしれないが」と断って、「もしこの考え方で考えるとするならば、僕は物を絶対に粗末にしたりできないだろう」と言っています。物を大事にしなさいとは教えなくても、ロボコンでロボットを苦労しながら作ると、ひとりでに、物を大事にする心が育っています。たとえば、ここをつまんでぶら下げれば壊れるから、頑丈なところを選んで両手で持てば壊れないということをひとりでに理解していくわけです。それは自分のロボットだけではなく、他人のロボットについても同様ですから、他人の物も大事にします。ロボコンによって生徒たちのキレる顔が自然と穏やかな顔に変わります。これは偉大な教育効果です。 作文をもう一枚ご紹介します。この生徒はロボコンが本当に面白くて、先生に対する感謝の念が大変強い。どの作文も「先生、ありがとう」と言っているのですが、この生徒はその感謝だけでは済まないところがあります( 写真8 )。
二行目に「下山先生が自ら手さぐりの状態で始めたロボコン……」とありますが、下山先生というのは、技術の指導の先生です。よく先生を見ていますね。先生もうかうかしていられません。中程に見られるように、チームは好きな者同士が集まらないようにしてあって、くじで四人を決めています。そうすると、まさに人生の出会いの瞬間があって、そこから共同作業が始まります。最後の一句、「下山先生に会えてよかったです」と、生徒にこんなことを言われたら、教師冥利につきますね。本当に、この最後の一行は泣かせます。 広島の呉にある中学校の十五歳の生徒の感想文の一部にありますが、「学校に来るときでも、トイレの中でも、寝るときでも、お風呂に入っているときでも、また三人は考えました」と、ロボコンのことをしょっちゅう考えているんですね。ロボコンが始まって四ヵ月間、とにかく夢中でロボットのことを考えている。 道元禅師の著された『正法眼蔵』の現成公案に、「沸道をならうというは自己をならうなり。自己をならうというは自己をわするるなり。自己をわするるというは万法に証せらるるなり」という金言があります。生徒たちを見ていますと、まさに自己を習っているのです。まさに自己を忘れているのです。我々は「もの」を見るときに、普通は「見る者」と「見られるもの」の二つに分かれています。しかし、夢中という状態になると、「見る者」が消えて対象だけになります。そうなると、対象という意味がなくなり、そこにあるのは「もの」だけになります。「もの」だけがあって自己を忘れている状態は、完全に精神統一のとれた状態であり、これが自己を忘れるということです。西田哲学には「もの来たって我を照らす」という言葉がありますが、ロボコンでは「ロボット来たって子供たちを照らす」ということが、明らかに表れています。この十五歳の少年はロボット作りによって育てられました。 七十五人の生徒の感想文を分析してみると、先生への感謝、ロボコンに対する感謝を述べているのが六十人。チームワークの大切さを述べているのが五十五人。ロボコンは全人格教育だと述べているのが四十五人。生まれて始めてこんな感動を得たというのが四十七人。満足感で一杯だというのが十一人。お金では買えないと書いているのが三人。一生の思い出になると書いているのが三十七人。こんなに集中できたことはないというのが三十人。勝負でありながら勝ち負けを超えて、そして負けても満足して一所懸命やったことが何より嬉しいと書いているのが三十二人。これからも後輩のためい続けてくださいと頼んでいるのが二十七人。我が校の誇りだと思っているのが二十人。「下山先生、あなたは日本の教育を変えるために頑張ってください」と書いている人は八人もいました。 次の感想文は E メールで送られてきたものです。 「作った人にしかわからないすばらしい感動だった。それに、制作しているうちに、やらなければではなく、やりたいという気持ちに変わっていることに気がついた」。「しなければならない」が「したい」に変わってくる。そうでないと、やる気は出てまいりません。これは人間として大事なことだと思います。 これは次年度の感想文です。「動かない。このことがわかったのは大会の前日。リモコンの配線がおかしい、みんな慌てました。急いで新しい配線を探してきて付けなおした。たしかに慌てていた。けれどもみんな楽しそうにニコニコしていた。つられて自分も慌てながらニコニコしていた。これがロボットの教えてくれたものかと思う。なんでそこでみんなが笑っているのかわかりません。しかし自然と顔がゆるんでしまう。いくら考えても答えが出ない。いくら悩んでもわからない。でも答えが出ないこと自体が答えなのではないでしょうか。答えを出さずにいつまでもそのことを考え続ける、これがいちばん大切なのではないでしょうか。これを思うと、四ヵ月間頑張ったかいがあります。僕たちはテレビに映るから作るのでもなく、先生に褒められるから作るのでもなく、偉い先生が来るから作ったのでもない。この答えの出ない答えを、一生心のなかで考え続けるために作ったのだと、木村拓は思います。いや、作ったというよりも、僕たちは子どもを産んだ。産んだというよりも、産まさせてくれた。産まさせてくれたロボットは次の三年生に解体されようとも、木村拓の心の中であと八十年ぐらい生き続けると思います。」 この「産ませてくれた」「作らせてくれた」「教えてくれた」というところは、まさに道元の「万法に証せらるるなり」ということです。ベクトルの矢印がこちらから向こうを向いているのではない、向こうからこちらを向いている。ひとりでに彼らはそういうことを把握するようになります。 同じ『正法眼蔵』に、「自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり」とあります。向こうからの矢がこっちへ向かってくるのが悟りであるということを、私は『正法眼蔵』を読ませていただいておりましたので、理屈では理解していましたが、実際にこれを実証できたのは初めてでした。 ロボットコンテストは、単なる競技でも遊びでもありませんし、ロボットの技術だけを競うものでもありません。「もの」が人間にとってどのような立場にあるか、ロボットがいかに青少年を育てるかという証が立ったという気がいたします。 *——————————–* 結論として、私は、もの作りに二種類あるように思います。今までは人間中心型( ego 型)、つまり「もの」は人間が便利をするための材料でした。そのために「もの」を駆使することを追求していました。その態度ですと、機能は人間が作り出すものだと考えますので、どうしても発明的であり、合目的的になって、そこから出てくる姿勢は傲慢であり盲目になります。二十一世紀のもの作りは調和型( non-ego 型)で、「もの」を駆使するのではなく、「もの」を活かす。機能は人間が用意するのではなく、すでに用意され隠されている。その隠されている「もの」を人間が発見する。ですから発明ではなく発見であり、むしろ人間中心の目的ではなくて、もっと大きい、縁や出会いといったことを契機とした無目的的である。この「無目的」とは、勉強するのには目的がなければだめだといった低い意味ではなく、もっと次元の高い無目的であります。謙虚で開眼的で調和型の、二十一世紀のもの作りに対する人間の姿勢はこうでなければならないと、私は感じております。 「ロボコンは人生の縮図である」「登校拒否を下校拒否に変えるロボットコンテスト」といった、いろいろな標語ができてまいりましたが、ロボコンの中では「もの作りは人作り」という標語がいま、定着してまいりました。 教育改革が叫ばれて久しい昨今、教育のひとつの実験としてのロボットコンテストについて、ご紹介させていただきました。 急いで雑駁なお話をさせていただきましたが、ご清聴ありがとうございました。 (東京工業大学名誉教授・自在研究所社長・名大・工・昭 25 ・工博〔東大〕)
|
![図1.[第一班]人間重り式 図2.[第二班]コンデンサー充電式](/images/magazine/archives/833_01.gif)
![図3.[第三班]スロープ発車台式 図4.[第四班]重りカタパルト式](/images/magazine/archives/833_02.gif)
 その中でも、東の横綱にあたるのが青森県八戸市立第三中学校です。この学校は中学校のロボコンでは全国のトップにあります。他にもロボットのコンテストは社会人の大人が参加するものなどたくさんあって、NHKで放映される「アイデア対決・ロボットコンテスト」はほんの一部なのです。以下では八戸市立第三中学校の場合をご紹介いたします。
その中でも、東の横綱にあたるのが青森県八戸市立第三中学校です。この学校は中学校のロボコンでは全国のトップにあります。他にもロボットのコンテストは社会人の大人が参加するものなどたくさんあって、NHKで放映される「アイデア対決・ロボットコンテスト」はほんの一部なのです。以下では八戸市立第三中学校の場合をご紹介いたします。
 写真2 はエレベーターでボールを上げていって、すべり台をすべり下ろして一度ボールを宙返りさせて一気に落とそうというものです。担任の先生に赤ちゃんが生まれたので、写真をもらってきて喜んで貼ったりしています。一台二千五百円から五千円ぐらいで仕上がります。マブチからモーターを寄付してもらったり、タミヤからギヤボックスを寄付してもらったりして、あとはほとんど廃品利用で、段ボールやプラスチック段ボールを使ってこういうものができあがります。
写真2 はエレベーターでボールを上げていって、すべり台をすべり下ろして一度ボールを宙返りさせて一気に落とそうというものです。担任の先生に赤ちゃんが生まれたので、写真をもらってきて喜んで貼ったりしています。一台二千五百円から五千円ぐらいで仕上がります。マブチからモーターを寄付してもらったり、タミヤからギヤボックスを寄付してもらったりして、あとはほとんど廃品利用で、段ボールやプラスチック段ボールを使ってこういうものができあがります。
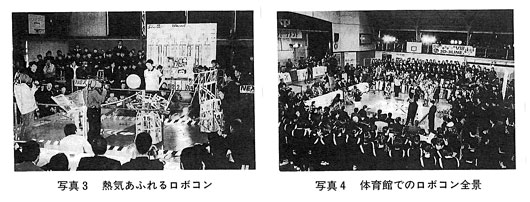
 本番の競技の日は、まさに学校あげての一大行事で、熱気のこもった状況になります( 写真3・4 )。応援するほうも一所懸命になります( 写真5 )。遠く熊本からも見学に来ていますし、しかも中学校ばかりか大学からも来るんです。昔は中学校から大学に習いに行ったものですが、このごろは大学がこの中学校の先生を特別講義に呼んで講義してもらっているほどです。実は、この中学校は青森県の八戸市では、二十二校中で最も荒れた学校でした。職員室前の廊下を自転車で走ったり、夜にガラスを割られたりと、とてもひどかったのです。私は第六回目のロボコンから付き合っていますが、生徒たちがどんなロボットを作っているのかを見るために前日に体育館に行ったら、体育館にライターで火をつけようとしている生徒がいたというのです。それをつかまえて職員室で二時間ほど油をしぼって返したのですが、そうしたら翌日、その生徒が優勝しちゃったんです。そういう劇的なこともいろいろとありましたが、今では生徒たちは礼儀正しく、八戸市立第三中学校は青森髄一の模範校になりました。
本番の競技の日は、まさに学校あげての一大行事で、熱気のこもった状況になります( 写真3・4 )。応援するほうも一所懸命になります( 写真5 )。遠く熊本からも見学に来ていますし、しかも中学校ばかりか大学からも来るんです。昔は中学校から大学に習いに行ったものですが、このごろは大学がこの中学校の先生を特別講義に呼んで講義してもらっているほどです。実は、この中学校は青森県の八戸市では、二十二校中で最も荒れた学校でした。職員室前の廊下を自転車で走ったり、夜にガラスを割られたりと、とてもひどかったのです。私は第六回目のロボコンから付き合っていますが、生徒たちがどんなロボットを作っているのかを見るために前日に体育館に行ったら、体育館にライターで火をつけようとしている生徒がいたというのです。それをつかまえて職員室で二時間ほど油をしぼって返したのですが、そうしたら翌日、その生徒が優勝しちゃったんです。そういう劇的なこともいろいろとありましたが、今では生徒たちは礼儀正しく、八戸市立第三中学校は青森髄一の模範校になりました。