学士会アーカイブス
額田女王と石川郎女――万葉集を読み直す―― 直木 孝次郎 No.825(講演特集号)(平成11年11月)
額田女王と石川郎女 ――万葉集を読み直す――
直木 孝次郎
(大阪市立大学名誉教授)
No.825(平成11年11月)号
『日本書紀』と『万葉集』にみえる額田女王
万葉歌人、額田王といえば、どなたもご存知と思います。「ヌカタノオホキミ」と読み、『万葉集』では「額田王」と書いています。しかし、奈良時代には王と女王をはっきり書き分けていますので、本日の演題には分かりやすいように「女」を付けました。ていねいに日本読みいたしますと、「ヌカタノヒメオホキミ」となります。『日本書紀』では「額田姫王」と書いています。
万葉歌人のうち五指に入る歌人といえば、一番が柿本人麻呂、次いで大伴家持、三番目に額田女王が入るかと思います。しかし、これほど有名な女性なのに、いわゆる正史とされる『日本書紀』には天武天皇二年二月条にしか姿をみせません。
天武天皇が壬申の乱の翌年(六七三年)、正式に即位いたします。その即位記事の次に、皇后や妃・夫人など、天皇の妻たち十人の名前を地位の順に列挙し、女性たちが生んだ皇子の名前が記されていますが、十人の八番目に「額田姫王」の名前が出てまいります。
まず初めに、皇后である鸕野皇女(後の持統天皇)――鸕野讃良皇女――の名前が記され、草壁皇子を生んだと書かれています。次に皇后の姉大田皇女、大江皇女、新田部皇女といった妃の名前が続きます。その後に、有力豪族である藤原臣鎌足の娘の氷上娘を夫人として入れています。さらに氷上娘の妹五百重娘、蘇我臣赤兄の娘大蕤娘と続き、次に肩書きのない三人の女性の名前が出てまいります。その最初に額田女王が登場します。原文は「天皇初メ娶メシテ二鏡ノ王ノ女額田姫王ヲ一、生二十市ノ皇女ヲ一」となります。額田女王は初め、大海人皇子(後の天武天皇) と結ばれ十市皇女を生みます。後に天智天皇(中大兄皇子)の後宮に入りますが、その時期は天智天皇の即位以前か以後か、はっきりいたしません。
この『日本書紀』の記事だけでは、額田女王と天智天皇がどのような関係にあるのかつかめませんが、『万葉集』によって補うことができます。天智天皇は早くから皇太子になっていますから、力によって弟の大海人の愛人である額田女王を奪い、額田女王は泣くなく大海人皇子のもとを離れ、天智の後宮に入ったのだと、一般には考えられています。額田女王が、後に中大兄皇子と結ばれたことは『万葉集』によって初めて分かるのです。
額田女王に関する史料には、『万葉集』のほかに『懐風藻』があります。『懐風藻』は奈良時代中期に編纂された漢詩集ですが、有力作家については簡単な伝記を載せています。その一つに葛野王という皇子の伝記があり、そこに額田女王が天武天皇との間に生んだ十市皇女の名が出てまいります。そして十市皇女と天智天皇の子の大友皇子との間に生まれたのが葛野王である、とあります。壬申の乱では、天武天皇が自分の娘の夫である大友皇子を攻め滅ぼし、その骨肉の争いのなかで、十市皇女とその母の額田女王は運命に翻弄されるといった悲劇も生まれてきます(史料1)。ただし、葛野王の伝には、額田女王の名は出てきません。次に改めて、『万葉集』にみえる額田女王のことを申し上げます。
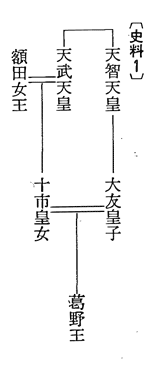
『万葉集』にみえる額田女王の歌
『万葉集』の時代区分では、額田女王が活躍した斉明・天智朝を中心とする時代を万葉第一期とし、柿本人麻呂の活躍する天武・持統朝を第二期とします。ちなみに人麻呂の歌は数多くあり、『人麻呂歌集』の歌などを合わせると百以上になるのではないかと思います。しかし人麻呂は特例で、額田女王の歌は万葉集のなかでも数の多いほうに入ります。そのうちの代表的なものをいくつか挙げてみましょう。
熟田津に 舟乗りせむと 月待てば
潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
(巻一―八)
代表作の一つです。大化改新で皇位が皇極天皇から弟の孝徳天皇に譲られますが、孝徳天皇が在位十年で亡くなってしまいますので、皇極天皇がもう一度位につき斉明天皇になります。そのときの皇太子が中大兄皇子、すなわち後の天智天皇です。
斉明朝の終わり頃に朝鮮で動乱が激しくなり、百済が新羅と唐との連合軍に攻め入られ滅んでしまいます。それを復興しようとする運動が百済に起こり、その百済側の要請により、日本は日本に来朝している百済の皇子豊璋を百済に送り返し、百済復興の戦いが始まります。そこで斉明天皇は百済救援のため、中大兄皇子とともに大軍を率いて九州へ出征します。軍はその途中、伊予の熟田津(愛媛県松山市の辺り)で停泊し、天皇、皇太子などは、石湯という温泉、いまの道後温泉にあたると思いますが、そこで一月余り滞在します。戦争に行く忙しいときに、なぜ道後温泉で長期滞在をしたのかというのも問題ですが、今日はそのことには触れません。ともかく、そこでゆっくりして、いよいよ出発というときに詠んだのが先ほどの歌と考えられます。軍船が船出をしようと月の出を待っていたら、潮の調子もよくなってきた。松山の辺りは瀬戸内海ですが潮の流れが相当速く、この流れに乗らないとなかなか次の予定地まで行けませんので、そういう状況が詠み込まれていると思います。次につづく「今は漕ぎ出でな」については諸説が出ておりますが、当時の常識からみて、神様の祭をして、船出していく情景を詠んでいるのだろう、神を祭るのは当時は女性の仕事であり、祭祀に関係していた額田女王はこのような勇壮な歌を作って船出を祝ったのではないか、といった解釈が有力です。多分、いままさに船出しようとしている軍船の上に乗って、朗々と額田女王自身がこの歌を吟唱したのだろうと思います。
三輪山を 然も隠すか 雲だにも
心あらなも 隠さふべしや
(巻一―一八)
有名なこの歌は実は反歌でして、これには長歌が付いており、「額田王、近江国に下る時に作る歌、井戸王の即ち和ふる歌」と詞書があります。「和ふる歌」とありますが、それに対応する適切な歌は付いておりません。編纂の手違いのようです。額田女王の長歌を読んでみます。
味酒 三輪の山 あをによし 奈良の山の
山のまに い隠るまで 道の隈
い積もるまでに つばらにも 見つつ行かむを
しばしばも 見放けむ山を 心なく 雲の
隠さふべしや
(巻一―一七)
大和の国を見捨てて近江へ行く。大和の国の神様が腹を立てはしないか。特に大和の国の三輪山にいる大物主の神はたいへん瞋恚が激しい。大物主とは祟りの神でもありまして、『日本書紀』によると三輪山の神の祟りで、たくさんの人民が死んだという伝説が崇神天皇の条に出てまいります。ですから三輪山の神に、別れの挨拶をしなければならない。いまでも大和では三輪山の信仰は大変行き渡っておりまして、新しい家を建てるときの地鎮祭には三輪山から御札をもらってくる習慣が残っています。大和では畝傍山や天香具山なども大切な山ですが、三輪山は土地の神として古代から連綿と強い信仰の対象でありつづけていたと思われます。
大和から近江への遷都の行列が奈良山を越えて山背(山城)の国へ入って行くと、三輪山がみえなくなる。いよいよ大和とのお別れです。大和から近江への行列が、奈良山を越えて行くときに、額田女王が代表して神に奉った歌というのが概ね定説になっています。奈良山は低いですから峠というほどのことはないのですが、そこで神様のお祭りをしたわけです。ついでながら峠という言葉も本来は手向をする場所という意味であったと思います。ときは天智六年(六六七年)、天智が正式に即位するのは近江へ移った翌年の天智七年で、それまでは中大兄皇子ですが、斉明天皇が亡くなった後は、実質上の政治は中大兄が執っていました。
話が少し前に戻りますが、中大兄皇子の指揮する朝鮮救援軍は白村江の戦いで大敗を喫し、ほとんど壊滅的な打撃を受けます。中大兄は朝鮮を放棄し総引き上げをします。その後しばらくは新羅や唐の軍隊が後を追って攻めて来ないかと不安に駆られ、西日本にたくさんの山城を作ります。結局、新羅や唐は攻めて来ませんで、そこで一安心するわけですが、近江遷都は、万一新羅や唐が日本に侵攻した場合を考えてのことかと思います。しかし、新羅、唐の侵攻はなく、平和の時期が数年つづき、文化が栄えてまいります。近江朝廷のなかでは、度々宴会が行われた状況が、『懐風藻』の序文に出てまいります。
そうしたあるとき、天智天皇が内大臣藤原朝臣鎌足に、春の山と秋の山のどちらがいいか、それぞれに歌を作って示してみせよと詔し、漢詩を以て春山と秋山の美の競争をさせ、その判定を額田女王にさせたということが、次の歌の詞書に書かれています。額田女王としてはまことに晴れの場面です。
冬ごもり 春さり来れば 鳴かざりし
鳥も来鳴きぬ 咲かざりし 花も咲けれど
山をしみ 入りても取らず 草深み
取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては
黄葉をば 取りてそしのふ 青きをば
置きてそ嘆く そこし恨めし 秋山そ我は
(巻一―一六)
春の山は美しいし、鳥も賑やかに鳴いているけれども、山に草木が茂り過ぎて花を採ることができない。ゆっくり山の奥へ入って鳥の鳴き声を聴くこともできない。秋ならば葉が枯れているので山の中へ入って紅葉狩をすることができる、そこが恨めしい。私は秋山のほうがよろしい。「恨めしい」を心憎いと解釈すれば、ほめ言葉になります。「秋山そ我は」という歌を作って判じたこの歌は、額田女王の才気を示した一首といえるかと思います。
歌や詩の催しは宴会に直結しますから、額田女王は神を祭ること、宴会の興を添えることを仕事として後宮に仕えていた女官と考えられます。額田が天智の後宮に仕えていたことを、より一層はっきり示すのが次の歌です。
君待つと 我が恋ひ居れば 我がやどの
簾動かし 秋の風吹く
(巻四―四八八)
額田女王は近江宮廷の一角に住まいを持っており、天智天皇のご入来を待っている。しかし、なかなか天皇は来てくれない、秋の風だけが簾を動かし吹いてくる、という情景ですね。まさに後宮の局といったようなところにいたことを思わせます。これに対して姉の鏡王女は、「風をだに 恋ふるはともし 風をだに 来むとし待たば 何か嘆かむ」と詠んでいます。姉の鏡王女のところへ天皇は全然訪ねてきてくれない。「そのうち訪ねてくれそうな気配の風だけでも吹いてくる、あなたのほうがましだわ」といった意味です。中国の古典にこういった趣の詩がたくさんありますので、この歌が本当に額田女王の作なのか、後の偽作ではないかという疑いをかける学者もいます。また謡口も、初期万葉にしては調子が流麗で、ある意味では調子が軽い。ですから実際に作られたのは奈良時代の初めの可能性があるように、私も思います。しかし仮にそうだとしても、その前に紹介した歌は近江朝廷に仕え、天智の側近にいなければ作ることはできません。後宮の地位の高い女官は天皇の寝所の相手もするのが普通ですから、やはり私は、額田女王が大海人皇子のもとから天智天皇のもとへ移っていった立場の女性であったことは認めていいと思います。
さらに、天智天皇が崩御したときには挽歌も作っていますので、殯の宮の行事に奉仕していたことがわかります。殯とは、天皇に限らず、人が死んで埋葬するまでの間に行う葬式儀礼をいいます。次の歌が額田女王の作です。
かからむと かねて知りせば 大御舟
泊てし泊まりに 標結はましを
(巻二―一五一)
「天皇がこのように早くお亡くなりになることを前から知っていたら、その用意をしておくのに、何も準備ができていない」と歌っています。この歌も額田が天智の側近に仕えていたことを示します。
ではなぜ、額田女王は大海人皇子のもとから天智天皇のもとへ移っていったのか。そこに問題があるように思いますが、その前に「大唐六典」から、天智朝での額田女王の仕事を考えておきたいと思います。大宝令や養老令に対応する唐の令は、実はまとまった形では残っておりませんが、「大唐六典」という唐の官制を記した書物が残っています。その一部を記したものが史料2です。
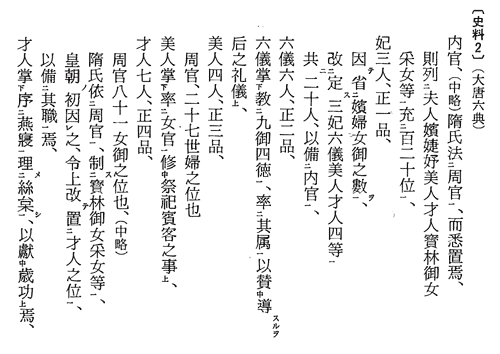
内官とは日本でいえば後宮職員で、後宮の官職を列記したものです。隋氏云々とは唐の前の隋がことごとく周の制度に則って役人、女官を置いているということです。後宮には夫人から采女まで、合わせて百二十人くらいの女性がいたのですが、それを唐はずいぶん縮減しているということが、この後に書かれています。実際には皇后は別として妃が三人いて、正一品の位である。六儀が六人いて、正二品である。六儀は二十人いたところを六人に縮小したという意味だろうと思います。六儀の儀は儀礼のことで、皇后が儀礼としてやるべきことをお教えするので儀といったのでしょう。六人の後宮女官が皇后を補佐するということであろうと思います。
次が正三品の美人です。美人とは、美しい人という意味ではなく、職名です。美人は四人いて位は正三品。美人の職掌は、女官を率いて祭祀賓客のことを治めることを司る、つまり女官頭のようなポストであって、祭りのことや客のもてなしを司ることでした。そうすると、この「美人」といった官職が歌から考えた額田女王の仕事に合うのではないかと思われます。その下に才人といって、天皇の衣服、寝床、宴会の下働きをする者がいました。日本でも特に平安時代は、尚侍、典侍などの後宮女官の上級の人びとは、天皇の寝所に持することは当然であると考えられていました。額田女王も同様であったと思います。
額田女王と大海人皇子(天武)と中大兄皇子(天智)
そこで、額田女王と大海人皇子と中大兄皇子、この三人の関係はどうであったかという問題になります。次の中大兄皇子の歌は、万葉集にはどういうときの作かの説明はありませんが、配列の順などから考えて、百済救援のために中大兄皇子が母親の斉明天皇とともに大軍を率いて、難波津を出航し北九州へ行く途中、舟をとどめて風待ちをする、あるいは航海の準備を整える、そのときに作った歌と思われます。
香具山は 畝傍を惜しと 耳梨と 相争ひき
神代より かくにあるらし 古も 然にあれこそ
うつせみも 妻を 争ふらしき
(巻一―一三)
「中大兄近江宮に天下治めたまふ天皇の三山の歌一首」と詞書があります。天皇とは天智天皇です。その反歌は「香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来し 印南国原」。反歌のほうはあとで触れるとして、長歌をみてみますと、香具山は畝傍が愛らしい、あるいは手放すのが惜しいと考えて、耳梨と争ったといっています。これは三角関係ですね。惜しまたは愛しと読むと畝傍が女山になり、香具山と耳梨の二つの男山が畝傍の女山を争ったことになる。まさに天智と天武が額田女王を争ったと解釈できます。そこで、神代より山々の間でこのような争いがあった、だからいまも私は弟と妻争いをしなければならない、と解するのが一般的です。一方、この歌は昔の伝説を思い出して詠んだだけで、現実の額田女王をはさんだ三角関係を生々しく詠んだ歌ではない、という説もあります。
反歌は『播磨国風土記』にある、出雲の阿菩大神が、三山の争いを仲裁しようとして播磨まで来たら、争いが止んだと聞いたので坐りこんだという伝説を歌ったものと思われます。印南国原は、いまの加古川の下流の平野です。出雲の神様がそこまでやって来たら争いが治まっていたと聞いて、腰を下ろしてしまったという古伝説を合わせて歌ったものだと解釈されています。そうした伝説と関係のある歌でしょうが、何かなければそのような歌を詠むはずがないと思いますので、やはり中大兄皇子の脳裏には、この三角関係があったのではないかと私は思います。
ここで一つ問題になるのは、「畝傍を惜し」を原文では、「高山波 雲根火雄男志等」と、畝傍を雄々しいと表現しています。この用字を重視すると、畝傍は男山ということになります。また、雄男志と読むと、香具山は雲根火が男らしい山と考え、いままで仲良くしていた耳梨山を捨て、雲根火に鞍替えしようとしたので耳梨との間に悶着が起こったと解釈すると、女一人、男二人の話となります。また、耳梨は女山で、以前から畝傍に思いを寄せていたとすると、女二人と男一人の問題になります。二人の男山が一人の女山を争うのか、二人の女山が一人の男山を争うのか、この歌の解釈はいろいろあります。
万葉学者のなかには、大和三山をあちらこちらから写生したり、写真を撮ったりして、山の形からどの山がいちばん男らしいかというようなことを論じられた方もいます。標高は畝傍山が一番高く、一九九メートル、香具山が一五二メートル、耳梨山が一四〇メートル。視覚的には香具山がいちばんなだらかで、男らしい感じはいたしません。背の高さ(標高)からすれば香具山を女山にみるのが、いちばん順当のようです。ただ、山の形は畝傍山はいちばん男らしくみえますが、みる角度によってはかわいい山にみえることもあります。結論を申しますと、私は香具山が女山で額田女王、畝傍が中大兄皇子(天智)と考え、香具山は畝傍と仲良くしようとして、いままで仲のよかった耳梨山の大海人(天武)と揉めたという解釈をいたしております
これは確かな証拠があるのではなく、解釈の問題になりますが、次に紹介する歌でさらにみてみましょう。額田女王の歌でいちばん有名なのは、天智天皇が蒲生野に狩に行ったときに作った次の歌かと思います。
あかねさす 紫野行き 標野行き
野守は見ずや 君が袖振る
(巻一―二〇)
これに対して大海人皇子(天武)の歌。
紫の にほへる妹を 憎くあらば
人妻ゆゑに 我恋ひめやも
(巻一―二一)
額田女王が大海人皇子(天武)に「袖を振って私にサインをお送りになると、それが人に知れますよ。あなたが私に恋心をいまも抱き続けていることが知れたら大変ではありませんか」と詠んだのに対し、大海人皇子が「いやそうおっしゃっても紫の花のように匂わしいあなたを、私が憎く思うのならば、まして人妻であるあなたのことを、私はこんなに恋い焦がれていましょうか」と返している。額田女王が天智の後宮に入った後も、大海人皇子との間に密かな愛の交流があり、額田女王と大海人の偲ぶ恋を示している歌だとするのが、かつては通説でした。
これに対していまから三十年ぐらい前に、池田弥三郎氏が新解釈を下されました。池田さんは国文学者でもあり、民俗学者柳田國男と折口信夫の高弟の一人でもあります。池田さんは次のようにいっておられます。
「袖を振るのは恋愛の意思表示だ。この時額田王は、天武のもとをはなれ天智のものとなっていたから、天智の見ている前での、天武のそうした行動(つまり袖を振る行動)をとがめたのが額田王の歌だ。それに対して天武が答えたのが次の歌だ。紫草のようにはではでしいわが愛人よ、たとえお前が人妻だって、なんで焦がれずにおられようか、というのである。これは深刻なやりとりではない。おそらく宴会の席の乱酔に、天武が武骨な舞を舞った。その袖の振り方を恋愛の意思表示と見立てて、才女の額田王がからかいかけた。どう少なく見積もっても、この時すでに四十歳になろうとしている額田王に対して天武もさるもの、『にほへる妹』などと、しっぺ返しをしたのである」(山本健吉、池田弥三郎共著『万葉百歌』一九六三年)。
これが池田さんの解釈です。千二、三百年も前ですから、四十歳といえばすでに初老といえる年頃だと思います。そういう皮肉なやり取りで、宴会の興を盛り上げるために両人の作った歌だという解釈をされました。いままで、この歌に掛けていた多くの人たちの、殊に女性の思いをひっくり返すような解釈をして、この歌を考え直す機縁を与えたのが池田さんでした。額田女王がこのとき四十歳近い年であったということは、万葉学の大家澤瀉久孝先生が早く明らかにされたところです。
確かにみごとな解釈です。学界は衝撃を受けました。しかし、それで話が終わるのだろうか。もしも天智天皇が権力に任せて額田女王を自分の後宮に引き寄せたということであれば、いくら宴会に興をそえるのが「美人」、つまりホステスとしての額田女王の役目であるとしても、なぜ、額田女王はこのようなからかい歌を、かつて子供まで成した愛人に対してできたのだろうか、という疑問が起こってまいります。
ここで私は、発想を改めたいと思います。これが本日の演題に、「万葉集を読み直す」という大袈裟な副題を付けた所以であります。
いままで、われわれは額田女王を考えるときに、男の立場からばかり考えてまいりました。権力に任せ天智天皇が大海人皇子から額田女王を奪ったのだという観点から、額田女王は哀れな女性、といった見方をしておりました。この解釈の背景には、明治、大正における男性中心社会があるのではないでしょうか。当時、柳原白蓮は心ならずも九州の炭鉱王伊藤伝右衛門と結婚します。山川登美子は与謝野鉄幹への思いを諦め、父の命のままに同族の駐七郎と結婚します。またフィクションですが、菊池寛の小説『真珠夫人』も同様です。意に染まない不幸な結婚をした女性が多かった時代ですから、額田女王もそのような結婚を強いられて天智の後宮に入ったのだという解釈が受け入れられて、定説となっていました。しかし、そうではないかもしれない。額田女王は若い頃は、大海人皇子の容姿、あるいは態度に引かれ愛情を抱き、結婚し子供まで成したが、年を経て考えてみれば天智のほうが立派であると思うようになり、自ら天智のもとへ行ったのではないか。天智が権力に任せ額田女王を奪ったにしては、大海人皇子へのからかいの歌は理解しにくいのです。むしろ額田は自ら進んで大海人を捨て、中大兄のもとへ走ったのではないか。額田女王の主体性を、われわれは見過ごしていたのではないか。
こう解釈いたしますと、額田女王が宴会の席で、大海人皇子へのからかい歌を歌っても不思議はありません。「あなたはいつまで私を想ってくよくよしているのですか、私はすっかり天智天皇に惚れているのですよ」という意がこの歌の背後にあるとしたら、理解しやすいと思います。「私は泣くなく、あなたのところから切り離されて、天智の後宮に入ったのです。私の気持ちはいまでもあなたのものよ」というのでしたら、このからかい歌は作れないのではないかと思うのです。また大海人皇子にしても、額田が大海人のもとから引き裂かれていった不幸な女性であったら、その容姿をからかい、中年女性の弱点をつく意地の悪い歌を作るでしょうか。額田が大海人を捨てて、自ら天智のもとへ走ったとした場合、これらの疑問が解けるのです。
実はこの時代には、こういう立場の女性は額田女王一人ではありません。そこで石川郎女に登場してもらいます。
草壁皇子・大津皇子と石川郎女
石川郎女は『万葉集』において、天智と天武の次の世代に登場いたします。石川郎女と関わる大津皇子は天武の息子で、時代は天智の没後十数年後の話になります(史料3)。
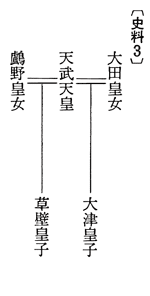
次に大津皇子の歌を挙げますが、詞書に「大津皇子、石川郎女に贈る御歌一首」とあります。
あしひきの 山のしづくに 妹待つと
我立ち濡れぬ 山のしづくに
(巻二―一〇七)
大津皇子は石川郎女とデートの約束をしたが、すっぽかされて約束の場所で長いこと待っている間に松の露でびっしょり濡れてしまった、と女を怨んでいます。
石川郎女がこれに答えて歌を詠んでいます。
我を待つと 君が濡れけむ あしひきの
山のしづくに ならましものを
(巻ニ―一〇八)
「それなら、私が山の雫になってあなたに濡れかかりたかったのに」という非常に巧みな歌を返しています。デートのすっぽかしを、逆にあなたをこんなに恋しく思っているのですよ、という歌に変えてしまっています。その石川郎女に、大津皇子の腹違いで一歳上の兄草壁皇子がやはり思いを寄せていました。「日並皇子尊、石川郎女に贈ふ御歌一首 女郎、字を大名児といふ」という詞書のある歌を彼は詠んでいます。
大名児を 彼方野辺に 刈る草の
束の間も 我忘れめや
(巻二―一一〇)
日並皇子尊とは草壁皇子のことで、皇太子ですから日並皇子尊と呼ばれています。大名児は石川郎女の呼び名です。「彼方野辺に 刈る草の」は、束を言い出すための序の言葉に過ぎないので、「大名児、あなたを束の間の短い時間も私は忘れない。いつもあなたのことばかり思っている」という意味になります。ですから石川郎女は、大津と草壁の二人の間をうまく行き来していたことになります。石川郎女は皇太子である草壁皇子と結婚したという史料はありませんので、その点は天智天皇と結ばれた額田女王とは違いますが、当時の最有力な皇子二人と、何らかの関係を持っていたという点では、共通性があります。そういった男女関係は、当時としてはそれほど珍しくなかったのではないかと思います。
大津皇子の歌をもう一つ次に挙げます。
大舟の 津守が占に 告らむとは
まさしに知りて 我が二人寝し
(巻二―一〇九)
この歌の詞書は、「大津皇子、竊かに石川郎女に婚ふ時に、津守連通、その事を占へ露はすに、皇子の作らす歌一首 未だ詳らかならず」となっています。「竊かに」とありますから、二人は正式に結婚していない。あるいは、石川郎女は確認されていないけれども、草壁の後宮に入っていたのかもしれません。大津と石川郎女の二人が密かに会って関係を結んだときに、陰陽道に通じ、占いの大家である津守連通が占いで二人の密通を明らかにした。そのときの皇子の歌です。「私が石川郎女と寝ることは、津守連通の占いで知られているだろう。しかし、それは承知の上だ。それでも私は石川郎女と寝る」といった大胆な歌を作っているわけです。いくら津守連通が占いの大家だからといって、占いで男と女が寝たかどうか、わかるはずがない。実際はスパイを使って二人を尾行し、偵察して知っているのだろう、と解釈する学者もいます。大津皇子も自分が監視下にあることは知っている。誰に監視されているかというと、草壁皇子の母親の鸕野皇女(当時皇后、後の持統天皇)であって、その命令によって、津守連通は大津皇子を監視したのでしょう。彼女にとって息子草壁皇子の最大のライバルは大津皇子ですから、大津の弱点を何としてもみつけ出して葬ってしまわなければなりません。確証はありませんが、石川郎女は草壁皇子と婚姻関係にありながらも、大津皇子との間にも深い関係があったと思われます。そしてそれは、誰からの強制でもなく、石川郎女が自ら選び取ったものと思います。主体性をもって選んだのです。
従来の万葉研究者は、石川郎女に対しては二人の男とうまく付き合っているセクシャルな、あるいはコケティッシュな女であるなどと、わりと厳しい評価をしております。一方、額田女王は悲恋の女王、薄命の佳人とみている。おそらく、その評価のもとには、額田女王は系譜ははっきりしませんが、皇族の一人と思われるので尊敬する。石川郎女は、それよりは身分の低い出自であるから、そういう女性は少しセクシーで男をたぶらかすような技巧をもっているというような偏見――それこそ私の偏見であるかもしれませんが――があったのではないかと思います
妻訪い婚時代の男女関係
ところで、七世紀という時代は、一夫一婦制とか、貞女は二夫にまみえずという道徳はまだなかったようです。当時は、女が二人の男と通じることが不倫や不貞とは思われていなかったのではないかと思います。天武天皇の夫人藤原五百重娘は、後に藤原不比等の妻になり麻呂を生んでいます。県犬養宿祢三千代という女性は初め美努王の妻になり、葛城王(橘諸兄)や佐為王などを生み、それから美努王と別れて藤原不比等と再婚し光明皇后を生みます。特に三千代の場合は、光明皇后の母親として聖武天皇の側近にあって大いに活躍をしています。いわば天平時代における後宮のトップレディでした。美努王の死去より早く、不比等と再婚しているのですが、不倫ともいわれずに宮廷で活躍できる、そういう時代でありました
つまり万葉の頃は男が女のところへ通っていく妻訪い婚が普通でした。男は何人もの妻が持てる。しかし、通い妻は同居しておりませんから、妻もまた何人も夫が持てる。一夫多妻、逆にいえば一妻多夫ということになります。実際のところ、どこまで自由であったかはわかりませんが、論理的に一妻多夫が可能であったのが七世紀です。下級の民衆は労働時間など、いろいろな制約がありますから簡単にはいきませんが、その時代はまだ儒教道徳があまり日本に入っておりませんので、不倫・不貞と咎められることはなかったのです。八世紀に入り儒教道徳が採用され、大宝令、養老令の戸令では不倫は禁じられるようになっていきます。しかし元来、日本社会の風習として、自由な婚姻関係を結んでいたことが当時の歌からも窺えます。
『万葉集』には上総の末の珠名娘子のことを歌った次の歌があります
しなが鳥 安房に継ぎたる 梓弓
末の珠名は 胸別の 広き我妹 腰細の
すがる娘子の その姿の きらきらしきに
花のごと 笑み立てれば 玉鉾の
道行き人は 己が行く 道は行かずて
呼ばなくに 門に至りぬ さし並ぶ
隣の君は あらかじめ 己妻離れて
乞はなくに 鍵さへ奉る 人皆の
かく迷へれば うちしなひ 寄りてそ妹は
たはれてありける
(巻九―一七三八)
上総(いまの千葉県中央部)の珠名娘子はとても美しく、道行く人、何人とも自由に結婚している。美人が多くの男を相手にしてくれて結構なことだといわんばかりの歌で、珠名娘子を不道徳とはいっていません。
同じ『万葉集』でも時代が降ると、葦屋の菟原処女――ウバラヲトメ、あるいはウナヒヲトメ――は千沼壮士と菟原壮士の二人に求婚されるのですが、二人の男を迷わせるのは女の道にはずれるというのでしょうか、死んでしまったほうがましだといって自殺をしてしまう。そして自殺した菟原処女の話が伝説になってお墓ができる。『万葉集』にはそのような伝説を詠んだ歌があります(巻九―一八〇九)。時代も降ると、女性の地位が下がってきて、恋愛の自由が制約され、男性社会のなかに女性が埋没していくようになります。関口裕子さんの『処女墓伝説歌考』(吉川弘文館) には、そういった女性の歴史が『万葉集』の歌を例にして細かく考証してありますが、男女の関係も時代とともに変わってまいります。
額田女王の時代は七世紀の半ば過ぎです。壬申の乱で天智天皇の後継ぎの大友皇子が亡くなるのが六七二年で、天智天皇はその一年前の六七一年に亡くなっています。その頃には女が男を選ぶということは十分にあり得ましたので、その観点から額田女王と天智、天武の三人の関係をもう一度見直してみるべきではないかというのが、私が本日申し上げたい主眼でごさいます。
ご清聴ありがとうございました。
(大阪市立大学名誉教授・京大・文博・文・昭1)
(本稿は平成11年4月20日午餐会における講演の要旨であります)