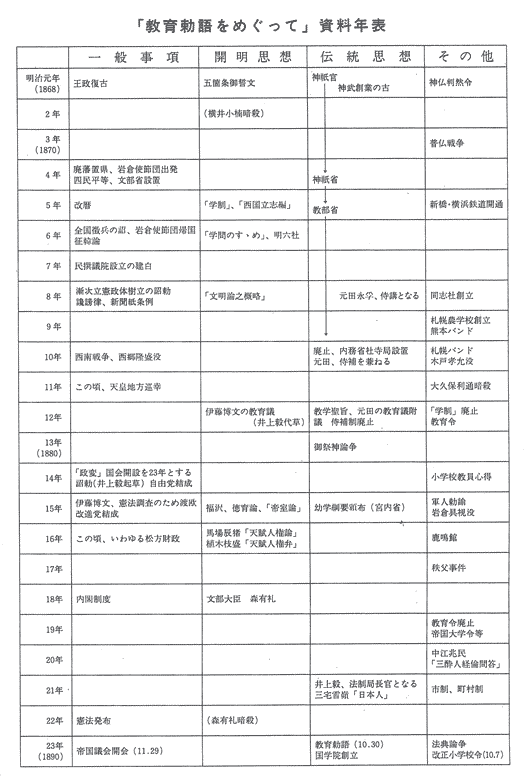学士会アーカイブス
教育勅語をめぐって―明治前期の開明思想と伝統思想― 安嶋 彌 No.798(平成5年1月)
本日は教育勅語をめぐる問題を、その成立過程というよりはもう少し広い観点から、つまり明治前期の思想の大きな流れの中で、お話申し上げたいと思って参上いたしました。しかし、何分にも時間が限られておりますので、要点だけを端折って申し上げることになるかと思いますが、その点をお許しいただきたいと存じます。
伝統思想の流れ
この神武創業の古に復るという考え方から、神祇官という官職が設けられます。これは当初太政官の上に置かれ、後に太政官と同格になり、逐次その影を薄くして、明治四年には神祇省に、明治五年になりますとさらに教部省になります。教部省は神道の思想と仏教の思想とをもって国民の教化に当たろうとするのですが、この二つはなかなか折り合わず、結局空中分解をきたし、廃止になってしまいます。これに伴い、明治十年に内務省に社寺局が設置され、この時点でこれまで時代をリードしてきた国学的な思想あるいは神道的な思想は一旦は途絶えます。 ちなみに、この内務省の社寺局は、明治三十三年に至り、神社局と宗教局に分かれますが、これには、条約改正により外国人の内地雑居が認められたことの関連から、キリスト教対策をどうするかということがその政治上非常に大きな問題となっていたことが背景にあります。ご承知のとおり、当時は国家神道が行われ、神社は国の営造物、また宮司以下の神職は官吏でありました。他方、一般の宗教は、いわゆる教派神道、仏教、キリスト教でありましたから、社寺局はいわば必然的に神社局と宗教局に分かれたといえます。そして、宗教局の方は大正二年に文部省に移管され、残った神社局は、昭和十五年に神祇院という内務省の外局(総裁内務大臣)になり、明治初年の神祇官が復活したような形になります。つまり国学的・神道的な思想は明治十年頃に表面から一旦は消えたものの、昭和十五年、皇紀二千六百年という時代の状況のもとにおいて復活したといえます。
横井小楠と開明思想 横井小楠は大変幅のある、端倪すべからざる人物と伝えられております。肥後藩ではこの人物を扱いかねたようですが、小楠は松平慶永のもとめで、越前藩に朱子学の教授として招かれます。後に橋本左内が安政の大獄で刑死しますと、その後をうけて松平慶永の枢機に参画します。横井は、当時としては一頭地を抜いた思想を持っておりまして、次のようなことを語っております。 米国の開祖のワシントンなる者は、堯舜以来の聖人である。あるいはこれよりすぐれているかもしれない。なぜかというと、大統領の権柄は賢に譲って子に伝えず、君臣の義を排して一向に公共平和をもって務めとしている。ワシントンの行った政治というものは、ほとんど三代の治教に符合する。すなわち、堯舜禹のすぐれた政治と一致する。「君聞かずや、洋夷各国の治術明らかなるを」。洋夷各国の政治がいかに公明であるか、精励してよく上、下情に通じ、人材を公選して俊傑上がる、というように、アメリカの民主政治、共和政治を賛美しております。 それから血統論については「ああ血統論、これあに天理に順ならんや」と批判の目を向けております。また、道は天下の道である、わが国の、外国のという区別はない、道のあるところは外国といえども「中国」である、無道であれば、わが国も中国といえども、「夷」である、と唱えております。さらに、君主に才能がなく、あるいは人格が劣っているならばこれを廃して、他から養子を迎え、君主を新たにして国を治めるべきである。治めることのできないような君主は君主ではない、臣があっての君であって、社稷国家にはかえがたい、つまり君主よりも社稷国家の方が大切である、ということを小楠は慶永に忠言しております。慶永はこれが大変不満で、「君臣紀綱紊乱の端緒を開けり」と小楠を非難するに至ります。こういう思想の持主でしたから、結局明治二年に十津川郷士らによって小楠は暗殺されます(森鷗外の歴史小説『津下四郎左衛門』は、この事件を主題にしている)。このときの軒奸状には、「今般夷賦に同心し天主教を海内に蔓延せしめんとす」と記されております。後に明治二十二年憲法発布の日の朝、文部大臣の森有礼が暗殺されますが、その暗殺の理由もほぼこれに近いものでありました。森有礼はアメリカから帰って間もなく、明治改元の直後、横井小楠を熊本に訪ね、大いに意気投合しております。この明治二年の横井小楠の暗殺と明治二十二年の森有礼の暗殺とは不思議につながっているように思います。
横井小楠の三つの門流 この矢島家と徳富家の系統がこの後大変ユニークな動きをいたしますが、これから、一つは熊本で自由民権運動に走るグループ、もう一つは京都や東京でキリスト教活動に走るグループが生まれます。矢島家の長女久子は横井小楠の、在郷の一番弟子徳富一敬に嫁ぎ、蘇峰や蘆花の母親になります。矢島家の次女つせ子は横井小楠の後添いになり、その子の横井時雄は同志社大学の総長になります。時雄の妹の横井みや子はやはり同志社大学の総長海老名弾正の妻となります。三女の矢島順子は熊本女学校長になります。この学校は今日の大江女子高等学校です。順子の夫、竹崎律次郎のつくりました日新堂という学校からは小崎弘道、金森通倫、北里柴三郎といった明治の錚々たるエリートが育っております。それから四女の矢島楫子は女子学院の院長、日本キリスト教矯風会の会長になります。さらに、徳富一敬と矢島久子の娘初子は湯浅家に嫁して、その子の湯浅八郎も同志社の総長になっております。こうして矢島家、徳富家の一統は、熊本ではいわゆる豪農民権家として時の県令に対抗して自由民権運動に走り、あるいは全国に散ってキリスト教を広めていきます。 ちなみに、明治初期の日本のキリスト教には三つの系統がありまして、まず一番古いのが横浜バンドといわれる、ブラウンやヘップバーン(ヘボン式ローマ字のあのヘボン)に代表される人達のグループ。もう一つが札幌農学校でクラーク博士の影響を受けた内村鑑三、新渡戸稲造というグループ、これは札幌バンドといいます。そしてもう一つのグループがいま申し上げました矢島、徳富らの、熊本のグループで、これを熊本バンドといい、その指導者はジェーンズというアメリカ人でありました。 横井小楠を明治前期の思想の水源地にたとえれば、そこから流れ出た第一は元田永孚、井上毅(井上の方は、横井の直系とはいえませんが)というグループ、第二は熊本バンドというキリスト教のグループ、第三は地元の自由民権のグループ、という三つの流れになります。こうした明治前期の典型的な思想がともに横井小楠に関係があるということは、大変注目すべきことであろうと思います。
学制と西国立志編の開明性 「人々自ら其身を立て其産を治め其業を昌んにして、以って其生を遂ぐるゆえんのものは他なし、身を修め智を開き才芸を長ずるによるなり、(中略)其身を修め智を開き才芸を長ずるは学にあらざれば能わず。(中略)されば学問は身を立つるの財本とも言うべきものにして、人たるものたれかは学ばずして可ならんや。かの道路に迷い飢餓に陥り家を破り身を喪うの徒のごときは、畢竟不学よりしてかかる過ちを生ずるなり」 つまり「学問は身を立つるの財本」、立身出世をするためには学問が必要だということでありまして、その考え方は一種の功利主義といってよろしいかと思います。 同じ年に『西国立志編』という本が出ております。これはイギリスのサミュエル・スマイルズの『セルフ・ヘルプ』(自助論)という本の翻訳でありますが、当時は『西国立志編』のタイトルで出ております。これは文字通りヨーロッパにおいて志を立てて成功をした人々の物語であり、翻訳したのは、後の東京大学教授の中村正直であります。努力、勤勉、倹約、忍耐、発明、創造といった徳目を説き、たとえばスチーブンソンがいかに苦労して蒸気機関をつくったかとか、あるいはウェッジウッドがいかに苦労をして陶磁器の技術を確立したかというような具体的な例をあげております。産業革命に成功した、イギリスのヴィクトリア朝のこうした事例は、ちょうど明治という、文明開化、殖産興業の時代の要請にぴったり合っておりましたから、この本は『学問のすすめ』とともに当時のベストセラーになりました。『西国立志編』の序文で中村正直は次のように書いております。 自助論 第一編序 西国立志編 序 こうした考え方はやはり開明思想、普遍思想であります。中村正直はもと幕臣でありまして、二十四歳で昌平黌の教授方出役を命ぜられる程の俊才でした。彼は明治七年にキリスト教の洗礼を受けて、その年の暮れに日本で初めてクリスマスを祝ったといわれております。いわば儒教の本道を歩んで、天道というものを深く信じていた中村正直は、 「世の儒者あるいは予をもって異端を助くるものとし、かまびすしくこれを責む。しかれどもその実は孔子を敬仰する始終変わらず、かつ深く孔子の道上等社会に行われ治平の大本とならんことを願う」 と語って、キリスト教の神と儒教の天あるいは天道というものを実にすらりとつなげております。同じ儒者でありましても元田永孚の方はキリスト教を終始敵視しているのに対して、中村正直は天理天道というものとキリストの教えというものは同じものだと受け取っている。そこのところが大変興味のあるところだと思います。ちなみに、西郷隆盛が用いました「敬天愛人」という言葉は、古川哲史さんの説によりますと、中村正直から出ているのであろうといいます。正直の号の「敬宇」も、敬天と同義といえましょう。 開明思想、普遍思想のもう一つの典型として、福澤諭吉の『学問のすゝめ』があります。これはご承知のとおり、「天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらずと言えり」という文章で始まり、さらに、「されば賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによって出で来るものなり」ということを述べています。この点は「学制」序文の思想と全く同じであります。ところが、学制の理念や福澤、中村の考え方に対して、明治十年代に入ると漢学系統から批判が生まれてきます。これが明治前期をリードする第三の思想ということになります。その中心人物が、横井小楠の門下を自負する元田永孚その人です。
徳育をめぐる議論 教学聖旨には次のように述べられております。 「輓近専ラ智識才芸ノミヲ これにはさらに、条目というものがついておりまして、 「去秋各県ノ学校ヲ巡覧シ、親シク生徒ノ芸業ヲ験スルニ、或ハ農商ノ子弟ニシテ其説ク所多クハ高尚ノ空論ノミ。甚キニ至テハ善ク洋語ヲ言フト雖ドモ、之ヲ邦語ニ訳スルコ卜能ハズ。此輩他日業 と、指摘されております。 これに関連して伊藤博文が「教育議」という文書を陛下に差し上げます。そして、この教育議の代草者が他ならぬ井上毅であります。その内容を簡単に申しますと、維新以来道徳が大変乱れてきている、過激な議論が世の中に広がって人心を煽動し、国体を破壊し、禍乱を醸成している、そういう弊害を何とかしなければならないという議論があるけれども、世の中が変わった結果そうなったのであって、そうした弊害が出たり、憂うべき状態になっているのは、明治初年以来の政治、行政の結果としてやむを得ないことである、今までの教育が間違っていたから今日の弊害が出てきたとはいえない、そういう弊害にのみ着目をして従来の方針を変えるようなことがあってはならない、また、もし以前のやり方をここで蒸し返すようなことがあったならば、これは百年の大計とはいえない、そういう弊害を矯正するために儒教の教典や何かを斟酌して「国教」というものをつくりあげるということも適当ではない、かつまたそういうことは政府が「管制」することではない、これからの教育はどうあるべきかというと、高等の生徒を訓導するためには、科学的な学問を授けるべきであって、政談に誘うべきではない、いまの学生は大抵漢学生徒の種子から出ている、口を開けば政理を説き臂を掲げて天下のことを論ずる、そういうことはよろしくない、若い学生には工芸技術、百科の学を修めさせなければならない、というのが伊藤、また井上の主張であります。そして、明治天皇は、伊藤博文の、この意見を容れて、「教育令」をご裁可になりました。 ところが、伊藤の意見に対して元田永孚は「教育議附議」というものを書いて反駁します。これはどういう内容か、簡略に申し上げますと、西洋にも修身という科目があって、大変重視されているけれども、その根本には耶蘇教がある、しかし、耶蘇教の教えは儒教の上に出るはずがない、従って、これからの日本の教育は四書・五経をもとにして進めるべきである、教育の最終の目的は決して科学技術教育に尽きるものではなく、やはり道徳が基本である、国教を樹立するのは反対だと伊藤はいうけれども、それは陛下のお気持ちを十分理解していないものだ、陛下のお気持ちを自分が敷衍すれば、国教は新たに立てるというのではなくて、祖訓、祖先の教えを承継するということがその内容である、と強く主張しております。この考え方が後の「教育勅語」の伏線になっていきます。そして、明治十五年には「幼学綱要」が元田永孚の手によってつくられ、宮内庁から直接学校などに頒布されます。 ちょっと戻りますが、明治十二年に「侍補制」が廃止になっております。侍補というのは、天皇の側近にあって天皇に諫言をしたり、あるいは天皇を補佐する(常侍規諫闕失ノ補益)という趣旨の職で、明治十年に設けられております。しかし、この侍補が政治あるいは人事の問題にまで発言するに及んで、伊藤博文等の当時の太政官のメンバーは、天皇の側近がそういう発言をしては困ると、これを廃止します。そのころは宮中、府中の別ということが特に意識されていなかったようでありまして、侍補・侍講の元田永孚などは、何が天皇のご意向であるかを公言してはばからなかったのです。今日ならば、宮内官はこれは天皇のご意思だなどとは絶対にいわないと思いますが、元田は、これが天皇のご意思であるとか、それはご意思とは違うとか、あからさまにいっております。この辺は、やはり憲法施行以前の時代の一つの特色といえるかと思います。
内閣制度の発足と徳育問題 森有礼は明治二十二年憲法発布の日の朝暗殺されて、榎本武揚が次の文部大臣となります。このころ徳育の問題が非常に大きな問題になっておりますが、榎本武揚は、理化学教育には大変熱心であったけれども道徳教育にはあまり熱心ではなかったといわれております。まして、森有礼がもし存命であったら、「教育勅語」が出たか出なかったか、これは歴史上の一つの疑問でありましょう。榎本の次の文部大臣が芳川顕正で、内務次官から文部大臣になった人です。そのときの総理大臣は山縣有朋で、かれは派閥をつくることで知られていますが、芳川はその後山縣派の重鎮になっていきます。芳川が文部大臣になると、徳育に関する準則をつくってはどうかという声がにわかに活気を帯びてきます。そこで芳川は、先ほど申しました中村正直に勅語の案をつくってほしいと依頼します。中村正直は、『西国立志編』やミルの『自由之理』を訳し、天理天道を信じ、かつキリスト教の洗礼も受けている人ですから、彼の書く勅語の原案というものは、いきおいそういう方向のものになってしまう。その案といわれるものの一部を読んでみますと、 「人々其独ヲ慎ミ之ヲ畏レザルベケンヤ。吾ガ心ハ神ノ舎スル所ニシテ天下ト通ズルナリ。天ヲ敬シ神ヲ敬センニハ先ヅ吾ガ心ヲ清浄純正ニセザルベカラズ。苟モ吾ガ心清浄純正ナラザルトキハ、イカニ外面ヲ装ヘルモ天意ニ協ハズ、君父ニ対シテ忠孝トナラズ、世間ニ向ヒ仁愛トナラズ、信義トナラザルナリ。善ヲ好ミ悪ヲ悪ムハ人性ノ自然ニ出ヅ。而シテ善ニ福シ淫ニ禍スルハ天道 と、こういう風でありますが、これはまさに普遍思想の勅語原案といっていいと思います。 当時中村正直は帝国大学の文科大学の教授であります。中村から原案を受けとった文部大臣の芳川は、それを総理大臣の山縣のところに持っていきます。山縣がさらに法制局長官の井上毅に相談いたしますと、井上は猛反撃を致します。井上は、この勅語は政治上の他の勅語と同一に扱ってはならない、これは君主の個人的な著作物という形の扱いにすべきである、今日の立憲政体の主義に従えば、君主は臣民の良心・自由に干渉しないのが建前である、いま勅語を発して教育の方向を示されるならば、政治上の命令と区分して社会上君主の著作公告としなければならない、つまり、命令ではなくて、君主のいわば個人的な著作という形でお示しになるならば、それはよろしいでありましょう、また、天を敬するとか神を尊ぶとかいったような語句は入れるべきではない、哲学上の理論は避けなければならない、儒教のような物のいい方とか、西洋かぶれのような感じも出してはいけない、等々のことをいいます。そういうことで、井上毅はこの中村正直の案を百パーセント否定をする。そこで、山縣の意向により、結局その起草の仕事は井上毅に回り、彼が、皆さまご承知の教育勅語にほぼ近い原案を書くことになります。その過程において元田永孚と緊密に連絡をとり原案を練り上げていくことになります。教育勅語が下賜されると、文部大臣の芳川は、文部省訓令(井上が起草した)を発して、教育上の遵守を命じます。そして、この体制は敗戦時まで続きます(ちなみに井上は、明治八年の漸次立憲政体樹立の詔勅及び明治十四年の、二十三年を期し国会を開設する旨の詔勅を起草し、また十五年の軍人勅論の起草にも関与しております)。
教育勅語をどう考えるか いろいろ申しましたが、幕藩制以後二十年ちょっとの間に、あのような近代的な憲法をつくり上げたことを思うと、明治という時代は、やはり偉大な時代であったと考えざるを得ません。今日明治憲法を批判する方はたくさんあります。伊藤博文は専制主義者であり、あるいはプロシア型の憲法を日本に導入した元凶であるといういい方もされます。しかし、伊藤は近代憲法の基本が君権の制限にあり、国民の権利の保障にあるということを明確に意識して明治憲法をつくっております。さらに、あの時点において、三権分立という近代憲法の大原則を織り込んだ憲法ができたということは、先進国を範としたとはいえ画期的なことといわざるを得ません。その内容がワイマール憲法に及ばないとか、新憲法に及ばないといった批判は、当たらないのであって、私はあの時代としてはほとんど望み得る最高の選択であったと思います。新憲法にしても、明治憲法五十五年の運用なくしては考えられないものでありましょう。 同じように教育勅語も、あの時代においてはほぼ妥当な選択であったろうと思います。私は、教育勅語が失効したといって、快哉を叫ぶような人々に同ずることはできません。また今日「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」を軍国主義的だという人がいます。しかし当時、国家の独立ということがいかに大きな課題であったか、また勅語発布の時期が日清戦争以前であったことも考えなければなりません。 要するに普遍思想は開明的ではありますが、一面解体的であります。特殊思想、伝統思想は守旧的ではありますが一面統合的であります。国家社会の順当な発展には、それぞれの時代の状況に応じて、「解体的」な要素と「統合的」な要素との、適切なバランスが必要なのであります。明治という時代は、こうした二つの思想の鬩ぎあいの中で展開したともいえます(後にこのバランスが崩れていきます)。ちなみに明治二十三年頃、民法の施行をめぐって「法典論争」が起こっておりますが、問題の所在はみな同じといってよかろうと思います(井上は、法制局長官であったが、施行延期論者であった)。 さて、這い這いをしている赤ん坊がよちよち歩きをしますと、親は大変喜びます。よちよち歩きの赤ん坊に対して、ちゃんと歩けないではないかとか、走れないではないかといって非難することはしません。這い這いからよちよち歩きに至ったという、その進歩を評価するのであります。私は歴史の見方、評価も、そのようでなければならないと思っております。このことを最後につけ加えさせていただきます。 時間が少なかったこともありまして、いい足りないことも多く、整わぬ話となりましたが、以上で私の話を終わらせていただきます。 (元文化庁長官・昭和女子大学特任教授・東大・法・昭19)
(本稿は平成4年9月21日午餐会における講演の要旨であります)
|
||||