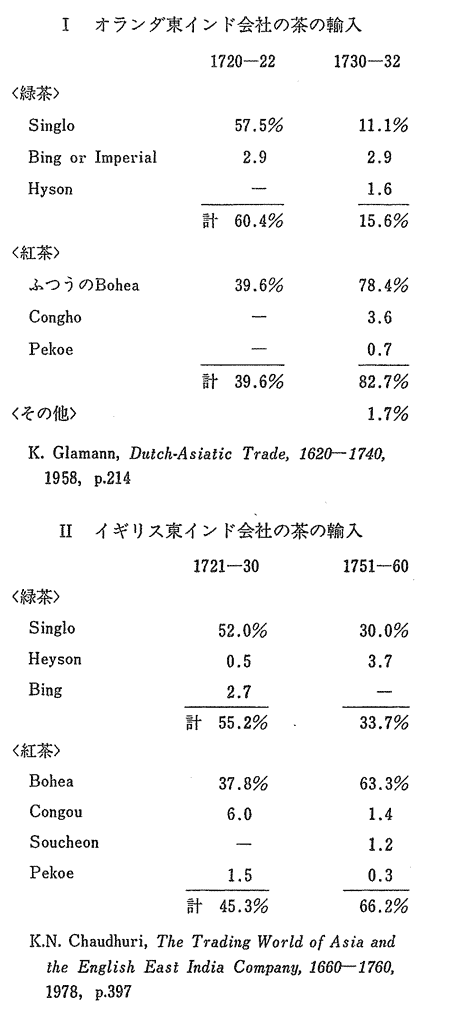学士会アーカイブス
イギリス人が最初に飲んだお茶 角山 榮 No.769(昭和60年10月)
私は先年『茶の世界史』(中公新書、昭和五六)を書いた。しかし私の心にまだ未解決のまま残っている問題がいくつかある。その一つは、イギリス人が最初に飲んでいたお茶というか、イギリス人を魅惑した茶とは、いったいどんなお茶であったのかという問題である。もとより当時の茶の現物が残っていない以上、確かめようがない。だから分らないといってしまえばそれまでである。しかし現在の茶から過去を類推するならばある程度分るかもしれない。本稿での試みはここにある。 さて一七世紀から一八世紀にかけ、中国茶の輸入に力を入れていたのがオランダとイギリスである。グラマン教授及びチョウドリ教授の研究によれば、茶の輸入が本格化した一八世紀前半における、オランダ東インド会社及びイギリス東インド会社によるそれぞれの茶の輸入はつぎのようになっている。(次表参照) 次の表はとくに輸入茶を緑茶と紅茶の二つの種類に分け、それぞれの輸入比率を示すベく作成されたものである。なお一言付け加えておくと、輸入茶はすべて中国茶であること、そしてオランダの輸入した茶のかなりの部分がイギリスへ再輸出されたことである。このことを念頭においてこの表をみると、輸入茶は初め緑茶が半分以上を占めていたのに、しだいに嗜好が紅茶へ移っていったことが分る。オランダ東インド会社は一七二〇―二二年のシングロ緑茶輸入から、十年後には早くも主力をボヒー紅茶輸入へ切り換えている。イギリス東インド会社もだいたい同じ傾向を辿ったが、一八世紀中頃に到ってもなお緑茶に対する根強い需要があって、緑茶は輸入茶のほぼ三分の一を占めていた。
イギリス人の愛好した緑茶 (1)ビング。ビングまたはイムペリアルとよばれる緑茶は輸入量は少なかったが、実は緑茶のなかでも最高の品質を誇るもので、価格も高かった。一七七一年の『ブリタニカ』(初版)の「ティ」の項には、「良質の緑茶(ヘイスンとかイムペリアル)は、葉が大きくあまりシワがなく、乾燥中に葉が殆ど巻きこまないようにつくられている。色はブルー・グリーンに近い薄い色で、実に何ともいえない素晴しい香りがする。ふつうの緑茶よりも、渋い味がするが、それでもはるかに心持よい味である。茶にだすと、薄いグリーン色になる」とある。ビングというのは漢字の「茗」、その方言の発音mingが訛ったものである。茗とは、「茶の芽」という意味である。 (2)ヘイスン。『オックスフォード英語辞典』によれば、ヘイスンとは (3)シングロ。シングロという名称は、元来安徽省南部のSung-lo丘陵地帯の地名に由来するといわれる。しかしその地名を中国の地図で確認することは容易ではない。林左馬衞氏の御教示によれば、松羅茶。あるいは「雄路」ではなかろうか、と。「雄路」の場所は イギリス人は当時から茶を飲むときには、ミルクと砂糖を入れて飲んだのであって、その点緑茶であろうが紅茶であろうが、茶の種類によって異なることはなかった。因みに日本が緑茶をさかんにアメリカ、カナダに輸出していた明治、大正時代、現地の人びとはやはり緑茶にミルクと砂糖を入れて飲んでいたのである。そんな飲み方をすれば、緑茶本来の味と香りが台なしになると思うのは、日本人の偏見かもしれない。しかし西洋人が緑茶からしだいに紅茶を撰択するようになるのは、肉食料理によく合うことと、紅茶の円やかな味と香りがミルクと砂糖とよく調和するからかもしれない。 イギリス人の嗜んだ中国紅茶 (1)ペコー。それは厦門語の 実は二週間の中国旅行中、私はずっと白茶を捜して歩いた。北京から上海、杭州、桂林と訪れた先はもとより、通訳の人にもひとりひとり白茶のことを尋ねてみたが、中国人は誰一人知るものはない。彼らは口を揃えて見たことも聞いたこともないという。だいたいふつうの中国人は、日常家庭で茶を飲んでいるものは少なく、多くは白湯を飲んでいるようだ。だから茶の知識が乏しいのもやむをえない。殆ど諦めつつ、旅の終りに広州へきた。そこでは、恰も交易会が開かれていた。交易会々場には輸出向きの商品が並んでいたが、なんとその中にこの白い茶「銀針白毫」があった。私はようやくめぐり逢えた喜びに思わず大声をあげてしまった。しかし買い求めようとしても、一キロ単位でないと売れないという。一キロ単位では残念ながらとても買えない。諦めて広州から香港へ。香港の百貨店でやっと罐に入った「銀針白毫」を手に入れたというわけ。 私が「銀針白毫」にこだわるのは外でもない。これがかつてイギリス人によって愛好された最高の紅茶ペコーを解く鍵になると考えるからである。しかし現在の白茶をみる限り、とても紅茶とは思えない。白毫である以上、当時からwhiteであってblackではなかったはずである。紅茶というのは発酵茶のことで、葉茶を発酵させるとふつうは黒色になる。だから白茶は現在でも分類はむずかしい。中国茶に詳しいある中国人は「白茶は緑茶でなく、また紅茶やウーロン茶でもない。どちらかといえば緑茶であるが、火力をあまり用いていないので、いくらか発酵している」(陳東達著『茶の口福』文化出版局、昭和五五)という。因みに今日ロンドン市場でペコーというのは、白毛の生えた若芽を意味せず、大柄なサイズの葉をさすようだ。 ともかく一八世紀初めのオランダやイギリスでは、この緑茶とも紅茶とも分らないペコーが貴族の間で珍重され、最上のもてなしに用いられ、贈り物にしたといわれる。それでは、彼らはこれをどのようにして飲んだのであろうか。私は試みに銀針白毫をいろんな方法で淹してみた。茶湯の色は無色か、ほのかに淡い橙色で、といって味も香りもとくにあるとはいえず、煎茶や紅茶に馴れたものには、何とも頼りないお茶である。それなら砂糖とミルクを入れて試してみたら、もはや茶でなくなってしまった。ものの本によると、オランダでは数本の銀針白毫をガラスコップに入れて客に出すのが最上のもてなしで、コップの蓋をすると、やがて茶柱が立つようになれば蓮花に喩えられ、底に沈むと雨後のたけのこに喩えられたという。もしそうであるならば、ペコーは飲み物というよりか、貴族階級の観賞用の茶であったということになる。それにしても紅茶ペコーの謎は解けそうにない。果してイギリス人はどのようにして飲んだのであろうか。 (2)スーチォン。ペコーにつぐ高価な茶はスーチォンである。漢語では「小種」と書く。これは成育した葉を小種にしてつくる。福建の特産で、とくに武夷山系の高原茶畑に産する。この地方は気温が低く雲霧が重くたちこめて、茶葉は肥えて厚く、発酵させると茶の色はからすの如く黒く潤いのある色になる。スーチォンにもいろんな種類があるが、イギリス人が好んだのは、烘焙のあと、特異なスモーキングで香味をつけたものであったといわれる。肉食のあとには、今日のウーロン茶のように脂肪を解かす力があったので歓迎された。 ただ価格の方は、ペコーと同じくらい高価であり、イギリス東インド会社の送り状にはときにはぺコーを上回る値がついていた。従って会社の輸入は、ペコーと併せても全体の二パーセント以下にとどまった。貴族以外には需要は大きくなかった。 (3)コングー。コングーの語源は、中国語の「 (4)ボヒー。日本ではしばしばボへアという名で知られるが、英語のBoheaは福建省の「武夷」が訛ったもの。一八世紀の輸入茶のなかで最大のシェアを占め、価格もポンド当り平均四シリングで、安ものの大衆紅茶であった。茶はふつう一番茶がもっとも香りもよく値打ちがあるが、ボヒーはもっとも晩く摘んだ葉茶からつくった紅茶である。すなわち夏の盛りに摘んで紅茶に加工したのち、バイヤーはそれを広東の商人のもとへ送り、そこで包装して輸出した。こうして広東へ新茶が到着するのは、九月から十二月にかけての時期であった。 それがイギリスへ輸入され人気を博したのは、東洋の霊験新たかな妙薬というふれ込みと同時に、肉食料理に消化がよく、イギリス人の食生活にもっともよく調和したことも一つの理由であろう。しかし一方では、ボヒー茶を飲み過ぎると、神経に害があり、例えば震え、中風、胃病(Vapours)、発作といった病気になる恐れがあるとされた。(S.Hardy, The Tea Book, 1979, p.76)それにもかかわらず、一八世紀をつうじボヒー茶の人気は上から下まで、広い階層にわたって拡大する一方であった。 こうしてみると、イギリス人の飲茶の歴史は緑茶から始まって、しだいに紅茶へと嗜好撰択を重ねていったことが分る。しかも紅茶といっても、 一方、古くから中国と交流があり、鎖国後も長崎をつうじて貿易関係を維持していた日本に、中国茶の情報が入ってきていたはずであるのに、不思議なことに紅茶そのもの及び紅茶輸出に関する情報はまったく日本に伝わらなかった。だから開港後、世界市場向け商品として茶の輸出を要請されたとき、政府は紅茶製法を学ぶため、中国の技術者をわざわざ招かねばならなかったほどである。 どうして日本は隣国中国における紅茶情報に疏かったのか。また茶の国でありながら、葉茶を発酵させるというかんたんな技術開発にどうして遅れたのか。ここではこうした問題を論ずる余裕はないが、中国における紅茶の歴史は、意外に新しいという説がある。紅茶の起源を古くは一五世紀中頃とする説もあるが、守屋毅氏は『お茶のきた道』(NHKブックス)のなかでつぎのようにのべている。「紅茶は明末、清初(一六四三年)に創製された。それが折しも東洋と接触しはじめていたヨーロッパ人、就中、イギリス人の嗜好に合い、ついにイギリスは自らの植民地インド、スリランカで、この製造にのりだし、やがて中国の茶葉を凌駕して、世界にイギリス風の紅茶文化を普及させることになる」(同著、九一頁)と。もしそうであるならば、茶の新製品紅茶の出現は、茶の二〇〇〇年の歴史上せいぜい三百四、五十年前のことにすぎない。しかもその紅茶市場を最初に開拓したのは、中国ではなくて、茶をたまたま知ったイギリスであったというのは歴史の偶然であろうか。 (和歌山大学教授・京大・経博・昭20) |
||||