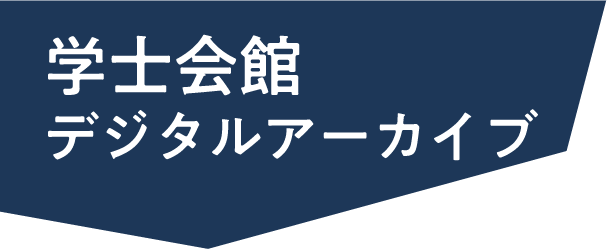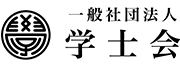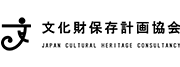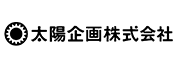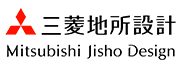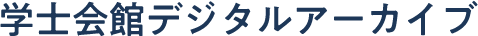
【学士会館について】
学士会館は、旧帝国大学(現在の国立七大学)出身者からなる学士会会員の親睦と知識交流を目的とした倶楽部建築として、1928(昭和3)年に誕生しました。関東大震災後に建設された震災復興建築の代表作としても知られています。
1937(昭和12)年には新館が増築され、また2002(平成14)年には改修工事が行われ、学士会会員だけでなく一般の人も利用できるようになりました。
学士会館の設計は、コンペ(設計競技)によって選ばれた髙橋貞太郎が担いました。髙橋は「住宅における間取りと気持ち」を解釈し、L字形の平面に各階の部屋を納めました。1階は「居間」として談話室など、2階は「御客用」として大食堂(201号室)など、3階は「書斎」として会議室、4階は「寝室」として宿泊室を設けました。つまり会員たちが親しみと落ち着きを感じ、アットホームな気分で過ごすことのできる会館こそ、髙橋が目指すものでした。
※学士会館は、老朽化による再開発のため2024年末をもって閉館(一時休館)いたしました。リニューアルオープンは5~6年後を予定しています。
【「学士会館デジタルアーカイブ」について】
学士会館は約1世紀にわたり、多くの人々が訪れ、様々な歴史を経て、地域のランドマークとしても愛される存在となっています。
「学士会館デジタルアーカイブ」は、フォトグラメトリ技術を用いて作成した、休館前の学士会館旧館・新館を記録するデジタルアーカイブです。360°動画、バーチャルツアーといったVRコンテンツを通じて、学士会館の歴史や空間を紹介しながら、学士会館の魅力を紐解いていきます。
※VR…バーチャルリアリティ
360°動画「学士会館へようこそ-イントロダクション」
動画を再生すると、学士会館の様子が360°お楽しみいただけます。
この動画では、学士会館の外観と、「学士会館デジタルアーカイブ」に登場する各部屋をダイジェストで紹介しています。
外観


外壁は、縦方向に引っかき模様を刻みつけたスクラッチタイルを大部分に貼っています。
-続きを読む-
1階まわりは富国石と呼ばれる人造石を碁盤目状に貼り、正面玄関のアーチと地覆石には日出石と呼ばれる砂岩を使用しています。また、外壁コーナー上部にはブロンズ製のメダリオン装飾を掲げています。
髙橋は会館の設計に際して、学士会会員の交流の場であり社会に対して持つべき態度を表すべく、「簡素質実」で「端麗にして、冒し難き気品」を外観に有するべき、と述べています。
外観 3DCGモデル
フォトグラメトリによって作成された学士会館外観の3DCGモデルを自由に見ることができるビューアーです。
マウス等で操作するほか、モデルに浮かぶ数字を押すと固定されたアングルのモデルを楽しむこともできます。
1階 正面玄関

外観でひときわ特徴的な半円アーチをくぐると、正面玄関があります。
-続きを読む-
アーチの頂部にはオリーブのレリーフを施したキーストーンを打ち込み、中央には篆書体で「學士會館」と館名を刻んでいます。
内部空間は、落ち着いた灰色の国産大理石で取り囲み、天井に立体感のある石膏装飾をあしらっています。
1階 広間

玄関から入ってすぐに広がる1階の広間は学士会館の中心の間で、あらゆる部屋に通じています。
-続きを読む-
広間を囲む壁や柱には淡黄色の人造石(富国石)が施されています。また、十二角形の柱には真鍮製の鋲があしらわれた斬新なデザインが施されており、ウィーン・セセッションの影響がうかがえます。
1階 カフェ&ビアパブ「セブンズハウス」(旧・娯楽室および新聞雑誌室)

この部屋は、かつて会員たちが囲碁や将棋を楽しむための娯楽室に、新聞や雑誌の閲覧室を併設して利用されていました。
-続きを読む-
周囲の壁はナグリ加工を施した木製押縁とその間に張られた壁紙で、当初は日本の趣を感じさせる落ち着いた空間であったと言われています。
1階 レストラン「ラタン」(旧・談話室)

この部屋は、かつて会員たちが歓談を楽しむ談話室として使用されていました。
-続きを読む-
壁は格子状に框を組んだ南洋材の腰羽目板を高くまで張り、天井には木製のような小梁を見せるチューダー様式の内装が施されています。英国由来のチューダー様式の採用は、会員たちの交歓する様子に英国紳士の姿を重ね合わせた意図が感じられます。
旧館1階 3DCGモデル
フォトグラメトリによって作成された学士会館旧館1階部分の3DCGモデルを自由に見ることができるビューアーです。
マウス等で操作するほか、モデルに浮かぶ数字を押すと固定されたアングルのモデルを楽しむこともできます。
1階 廊下、談話室

旧館と新館を結ぶ広々とした廊下と談話室は、新館の増築に伴い旧館の事務室を改装して生まれた空間です。
-続きを読む-
廊下に面して開放的な一室は、当初は会員専用の娯楽室として作られ、休館前には一般利用が可能な談話室として使われていました。
新館

学士会館は1928(昭和3)年の開館と同時に多くの会員の利用が集中し手狭となったため、早い段階で増築計画が立てられました。
-続きを読む-
1937(昭和12)年に完成した増築部分は「新館」と呼ばれ、設計は藤村朗が担いました。対して本体は「旧館」と呼ばれるようになりました。
新館の外壁は旧館に合わせて筋面タイル張りとして、全体の調和が図られました。
1階 新館玄関・広間

新館の内装は旧館に比べて軽快な印象を持っています。
-続きを読む-
梁下の彫刻やステンドグラスの意匠はアールデコ調の幾何学的な線で構成されています。
また新館の玄関は、壁面にイタリア産の大理石「トラバーチン」を全面的にあしらい、明るい雰囲気に満ちています。
360°動画「学士会館へようこそ– 1階」
動画を再生すると、学士会館の様子が360°お楽しみいただけます。
この動画では、髙橋貞太郎が「居間」のように設計した、皆様が最もなじみのある学士会館1階の各部屋を紹介します。
大階段

会館の中央部分でダイナミックに上下階を連絡しているのが、大階段です。
-続きを読む-
南洋材でつくられた手すりの質感やゆったりとした空間が特徴です。かつては手すり子の間にも装飾を施した鋳鉄製のグリルが嵌め込まれていましたが、戦時中の金属供出のために失われてしまいました。
2階 広間

大階段を上って2階にたどり着くと、天井の高い広間が目の前に現れます。
-続きを読む-
広間の壁には南洋材の羽目板が高い位置まで張られおり、彫刻の施された柱の持ち送りや天井繰形は重厚で格式高い内装を演出しています。
2階 201号室(旧・大食堂)


学士会館の中で建設当時の姿を比較的よく残す最も華やかな大宴会場です。
-続きを読む-
天井が高く柱のない大空間を実現するために、両側面の柱はH型鋼で頑丈につくられています。また梁を支える大きな持ち送りには、豊かさの象徴として葡萄唐草のレリーフが施されています。
奥の壁には高い位置に演奏用の奏楽所が設けられ、室内には優雅な音楽を響きわたっていたことも想像できます。ドラマや映画撮影のロケ地としても多く使われる学士会館の中でも、最も知名度が高い一室です。
201号室・広間 3DCGモデル
フォトグラメトリによって作成された学士会館201号室と広間の3DCGモデルを自由に見ることができるビューアーです。
マウス等で操作するほか、モデルに浮かぶ数字を押すと固定されたアングルのモデルを楽しむこともできます。
2階 202号室(旧・大集会室)

講演会や演奏会で多くの人数が集うための部屋が、大集会室です。
-続きを読む-
内装の大部分は改装されていますが、梁や天井には音の反響を防ぐために施されたコルク吹付け仕上げの凹凸が残されており、当初の面影をわずかに感じることができます。
2階 210号室

新館2階に位置する、最大で300人の宴席が収容可能な大空間です。
-続きを読む-
アーチ状の構造で骨太に設計されているのが特徴です。
側面の窓台と正面の暖炉に黒色大理石が用いられており、特に正面暖炉には黒地に金と銀の模様が入るイタリア産の高級輸入大理石「ポルトロ」が贅沢に用いられています。
3階 301号室(旧・特別会議室)

大小の会議室が集まる3階の角部屋に位置し、特別な内装が施された会議室です。
-続きを読む-
学士会の重要な会議はこの部屋で行われてきました。
洋風の暖炉の両脇に和風の床の間が付け足される造作など独特な雰囲気を持っています。
3階 チャペル(旧・読書室)

学士会館では、開館当初から数多くの婚礼が執り行われてきました。
-続きを読む-
新館5階には神前式の式場が設けられていましたが、時代のニーズに応じて2002(平成14)年に読書室を改装して教会式の式場を新設しました。
この改装設計では、既存の木製造作や大理石製の窓台、天井の持ち送り装飾などを巧みに保存し内装に活かしています。
4階 客室

4階は中廊下を挟んで両側に宿泊室が配置されています。
-続きを読む-
宿泊室の内部は、天井高さを低く抑えて落ち着きのある小部屋となっています。アーチ窓を通して入り込む外からの風と光は何気なく室内に親しみを与えています。休館前は一般利用も可能なホテルとして営業していました。
360°動画「学士会館へようこそ– 2階・3階・4階」
動画を再生すると、学士会館の様子が360°お楽しみいただけます。
この動画では、髙橋貞太郎が「御客用」として設計した旧大食堂(201号室)をはじめとして、
特別な日にご利用され、皆様の思い出に残る学士会館の2~4階の諸室について紹介します。
旬菜寿司割烹「二色」(旧・球戯室)

現在の「二色」

球戯室の竣工写真(「學士會館」『建築雑誌 510号』日本建築学会、1928)
1階広間の正面奥に位置する一室、日本料理を提供していた旬菜寿司割烹「二色」の店内は、かつて会員がビリヤードに興じる「球戯室」の空間でした。
-続きを読む-
リノリウムが敷かれた広々とした床には9台のビリヤード台が置かれ、その横にはバーカウンターも備えられていました。
高い天井にはタバコの煙が漂い、室内はビリヤードの玉を突く音が絶えず響いていたと言われています。
球戯室は別の場所に移されましたが、現在も会員に愛用され続けているビリヤード台(キャロムテーブル)は、昭和3年に導入されたものです。
360°動画「在りし日の学士会館– 旧球戯室の復元」
動画を再生すると、学士会館の映像が360°お楽しみいただけます。
この動画では、建築当初の「旧球戯室」の復元CGや古写真などを通して、「在りし日」の学士会館の様子をお楽しみいただけます。
学士会館の立地
学士会館が立つ場所は、近代高等教育の聖地です。
-続きを読む-
幕末の蕃書調所を端緒として、明治維新に至り文部省管轄の洋学研究・教育機関として開成学校が設立され、後に東京大学がこの地で創立されました。付近に神田古書店街や出版社が多く立地し、神保町界隈が本の街と呼ばれる理由とも関係が深いと言われています。
学士会館と戦争
学士会館は絶えず当局から徴用の的とされてきた歴史があります。
-続きを読む-
太平洋戦争が勃発すると、会館内の照明器具や装飾金物などが金属類回収令のために供出され失われてしまいました。また、会館の屋上には高射機関銃陣地が設けられ日本軍が駐留したこともありました。終戦後は、1945(昭和20)年9月から連合国軍総司令部(GHQ)に接収され、極東空軍高級将校の宿舎や将校クラブとして供用される時代が約11年間も続きました。学士会に返還され、学士会館として再開したのは1956(昭和31)年のことでした。
学士会館の構造
学士会館はそれまでの焼失被害や関東大震災の教訓を元にして、耐震と耐火を兼ね備えた構造として、鉄骨鉄筋コンクリート造が採用されました。
-続きを読む-
柱や梁の骨組みは、当時世界で最先端の米国ベツレヘム社製の鉄骨を大量に輸入して組み立てています。鉄骨は鉄筋コンクリートで覆い、外表面には不燃材料であるタイルや人造石、砂岩などを用いて耐火構造としました。また重量のある建物を地面の下で支えているのは、軟地盤に打ち込まれた約700本の松杭でした。
バーチャルツアー
360°バーチャルツアーを体験し、学士会館の中を見渡しながら歩き回ることができます。